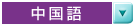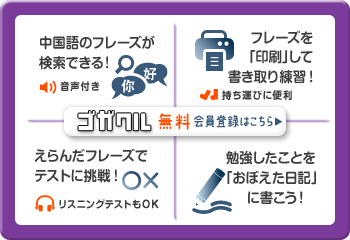採用や昇進でTOEICの基準点を設けたり、社内公用語を英語にしたりする企業のことが話題になっています。ある日突然「今日からわが社は英語で会議するぞ」と宣告された社員の人たちは、一体どんな気持ちなのだろうと思います。
中国語の会議通訳者も英語と格闘することが増えています。
専門用語や固有名詞はまず英訳を調べ、そこから中国語訳や日本語訳にたどり着くこともあれば、会議資料として英文のスライドがドンと送られてくることもあります。
英語の発言を「リレー通訳」する際に英文資料しか入手できないのは「仕方ないか...」と観念するにしても、発言言語は日本語又は中国語のはずなのに、英文資料しか頂けない時は、タメ息が出て来ます。
決して英語が嫌いなわけではありません。
ただ、そもそも中国語と日本語の通訳を生業とし、英語を専門としない者にとっては、必ずしも英文をスラスラと読めるわけではありません。こと医学やエネルギーなど専門的な会議で使用される英文のスライドやアブストラクトは専門用語のオンパレード。その日本語訳と中国語訳の両方を調べるのは、気の遠くなる作業なのです。
国際会議の通訳をするのだから「英語くらい読めて当たり前」と思われているのかどうかはわかりません。しかし本来守備範囲ではない英語とどこまで「戦えば」いいのでしょうか?
「英文資料は全くお手上げ!」と開き直るのではなく、その主旨や少なくともキーワードや専門用語は把握しておきたい。そうなれたらいいなあというのが私の個人的な考えです。
震災後に通訳需要がガクンと落ち込み、少々まとまった時間ができたのを機に、改めて英語を「コソ勉(=こっそり勉強すること)」し始めました。
そこで感じたこと。
どの言語であれ、語学はやはり「听(リスニング)」、「说(スピーキン)」、「读(リーディング)」、「写(ライティング)」のどれも練習しなければ上達しませんね。わかっているつもりでも英語の「读(リーディング)」ばかりを気にしていた自分を反省。
もうひとつは「語学は、エレベータを逆に上がろうとするのと似ていて、足を止めたら後退する。」と英語の先生からアドバイスを頂いたこと。
中国語で言うなら"逆水行舟,不进则退"――やらなければ何も始まらないし、前に進めないのだと改めて実感しています!

最近はネットで調べることの方が多くなりました。