■「ゴガクル」サイト終了のお知らせ■
長い間、みなさまの学習にお役立ていただいてきた本サイト「ゴガクル」(株式会社NHKエデュケーショナルが運営)は、 2025年9月30日 正午をもって終了することになりました。これまでご利用いただき、誠にありがとうございました。 続きはこちら>
Chiquitaさんの おぼえた日記 - 2018年5月5日(土)

この日記をフォローしているユーザ
この日おぼえたフレーズ(英語・中国語・ハングル)
- おぼえたフレーズはありません。
おぼえた日記

Reading “THE HIDDEN LIFE OF WOLVES” (3)
4. The Wolf’s Society
Of the two wolves, the couple named the bald and perky one Kamots. In the native American language, it means “freedom.” A group of wolves consisted of a leader named Alpha, the middle class, and Omega, which means the bottom of hierarchy. As a decision maker, Kamots established himself in Alpha’s status, took responsibility for safety and healthy life of the whole group. He also never failed to look out for the group not to miss any signs of danger.
The other brother wolf was named Lakota, which means “a friend” in the Native American language. He was cowardly and liked to follow his brother. Lakota became Omega and was harassed by the middle class wolves. However, when wolves started to fight, Omega showed his surrender and released the tense atmosphere of the group. He often initiates play by bowing playfully and encourages others to play together. Hence, Omega has an important roll of relieving tension within the group. This two contrasting wolves brings the group stability and makes harmonious prosperity possible.
What’s more, in this group, the wolf named Matsi stands close to Lakota (Omega). Matsi is ranked as No.2 and its name means “kind and brave.” Matsi runs to save Lakota when he is bullied too far. The two often play together which shows even wolves have friendship. When they play, they sometimes exchange their status and Matsi showed his obedience to Lakota. The couple commented on this scene as being very heart purified and healing.
The word, “disperser” means an independent wolf. In case of humans, it has an impression of rough individualism, meaning they are independent, never accept compromise, explore their life by themselves, and seldom mingle with others. However, young wolves that leave the group two years after their birth find their partner soon, promote friendship, and ask for friends that they can bind eternal ties with. In other words, wolves are very social animals, and therefore, the period when they are dispersers is very short.
Comparing a wolf society to human history, both have aimed at social stability by establishing a hierarchy. Hence, the middle class constantly struggled for power to keep their status. The interesting point is that while people at the very bottom of the social ladder were forced to lead a hard life and give up hope, the wolf at the bottom, Omega, takes a respectable roll of relieving tension and keeping stability of the whole society.
Reference:
THE HIDDEN LIFE OF WOLVES, Jim and Jamie Dutcher with James Manfull, X-Knowledge, NATIONAL GEOGRAPHIC, 2013
「オオカミたちの隠された生活」を読んで (3)
4. オオカミ社会
2頭のうち、大胆な性格で元気いっぱいの1頭をカモッツと名付けた。それは先住民のことばで「自由」の意を示す。オオカミの群れは「アルファ」というリーダー、中間層、そして「オメガ」という最下層で成り立っている。カモッツは、このアルファの立場を確立し、群れ全体の安全で健康な暮らしに責任を持ち、意思決定者としてふるまった。また危険の徴候を捉えそこなうことがないように、常に警戒を怠らなかった。
もう一頭は、同じ兄弟でも小心者で、兄弟の後をついて歩くことを好み、ラコタと名付けられた。ラコタは、先住民のことばで「友」という意味だ。ラコタは「オメガ」になった。「オメガ」は、中間層のメンバーから常に手荒い扱いを受ける。しかし中位のオオカミ同士のケンカが始まると、「オメガ」は服従を示し、群れの緊張感をほぐす。またしばしば、プレイ・バウ*と呼ばれる、身をかがめて群れの仲間を誘って遊びに引き入れる。このように「オメガ」は、群れの緊張を緩和するという重要な役割を担っている。この「アルファ」と「オメガ」の対照的な2頭は、群れに安定をもたらし、調和のとれた繁栄を可能にした。
しかもこの群れの場合、「オメガ」のラコタに寄り添うオオカミが、アルファに次ぐNo.2の地位にあるマツィなのだ。マツィは「優しくて勇敢という意味だ。マツィは、「オメガ」のラコタへのいじめが限度を越すとすぐにやってきてラコタを救う。2頭はよく遊んでいた。彼らは、オオカミにも友情があることを示してくれた。彼ら2頭だけで遊ぶときは、時々身分が入れ替わり、マツィがラコタに服従を示すポーズをとることがあるそうだ。日頃から虐げられているラコタを見てきた夫妻は、このような光景を「とても心が洗われ、癒される」と評している。
「一匹狼」(ディスパーサー)という言葉がある。人間では、妥協を許さず独立心に富み、自分の力で自分の進む道を切り拓く、仲間付き合いなど全くしない、荒っぽい個人主義という印象がある。しかし生後2年ほどで群れを出る若いオオカミは、すぐにパートナーを見つけ、常に友情を育み、終生続く絆を結べる仲間を求めているとても社会的な動物なので、「一匹狼」でいる期間はきわめて短い。
オオカミの社会と人間の歴史を見ると、どちらも序列をつくることで社会の安定を目指してきたように思える。そのため地位の不安定な中間層はその地位の安定のため絶えず権力闘争をしてきた。面白い点は、人間社会の最下層の人々は、苦しい生活を強いられ希望を持てないでいるが、オオカミの場合、最下位の「オメガ」は社会全体の緊張緩和と安定のための役割をりっぱに果たしている。
プレイ・バウ* 頭を低く下げ、前肢を広げて突っ張り、尻を持ち上げて、尾をぱたぱたと振る。
引用資料:
オオカミたちの隠された生活、ジム&ジェイミー・ダッチャー、(株)エクスナレッジ、2014年5月1日
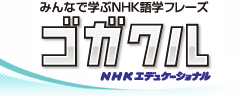
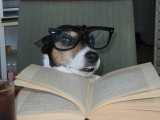





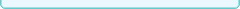
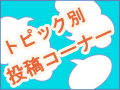







しんちゃんグランマさん、kimshaさん、
かなり長い文章だったので2回に分けようかと思ったのですが、一気に読んでいただいた方がよくわかるかなと思い、オオカミ社会については全文を一度に載せました。お付き合いいただきありがとうございます。
昆虫の世界も同じですが、それぞれが社会の役割を果たしているのが生き物の世界です。まさに安倍内閣が唱えているけど実現していない「誰もが生きがいを感じて、その能力を思う存分発揮する」社会ですね。しかもオオカミのリーダーはちゃんと群れ全体の安全で健康な暮らしに責任を持ち、利益を私物化しません。chieさんやkimshaさん、しんちゃんグランマさん、Charさんもご指摘のように、人間も見習っていただきたい!です。
私もMariNZさんがお書きになっているように一匹狼の期間が短いというのに驚きました。やはり本質的に「群れ」の動物なのですね。
PS. Charさん、ご主人に「お友達になれて光栄です!」とお伝えください。
人間が オオカミ社会から 学ぶこと 多いですね。
アンディはとうとう、エリザベスカラー着用になりました。
野生動物は本能で種を絶やさないベストの法則を選んで生きているのでしょうか。そう考えると人間社会は種を絶やしてしまう戦争を自ら選んだり...、そういう意味では野生動物の方が人間より進歩的なのかな、と思ってしまいますね。
(先日の子供の頃のChiquitaさんとコロちゃんのお写真、可愛いですね。)
何回も再生して、夫にもまるで自分のお友達みたいに紹介してしまいました。(#^.^#)
一つの集団を構成するためには、それぞれの役割分担が必要で、それはどの生き物にとっても言えることなのかなと思います。人間の場合は、役割分担をして集団を構成するという大前提を見失って、本当は集団全体のことを考えて献身的に振舞わなければならないはずのリード格の人達が、自分たちに都合の良いことばかり考えるからおかしなことになっていると思います。特に、今のニホン。