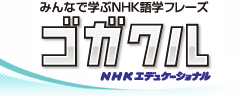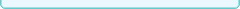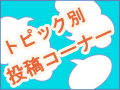HUITTさんの おぼえた日記 - 2025年1月21日(火)

この日記をフォローしているユーザ
この日おぼえたフレーズ(英語・中国語・ハングル)
- おぼえたフレーズはありません。
おぼえた日記

※ caption : Noh "Takasago" by Hiroshi Nakamura
01/21(火)
「誰をかも知る人にせん高砂のー」
英語で読む百人一首 ピーター・J・マクミラン
不思議の国の和歌ワンダーランド 第34番
2022年10月07日 京都新聞デジタル所載
誰をかも
知る人にせん
高砂の
松も昔の
友ならなくに
(百人一首カルタでの英訳)
Of those I loved, non are left.
Only the aged pine
of Takasago
has my years, but, alas,
he is not an old
friend of mine.
Fujiwara no Okikaze
[現代語訳]
いったい誰を昔から親しく知っている人にしたらよいであろうか。知人はみな亡くなり、同じように年を経た、あの高砂の松でさえも、昔からの友ではないのだから。
* 歌は新編国歌大観の「百人一首」を原本とし、表記は適宜、かなを漢字に改めています
🌲🌴🌳🌴🌳🌊🌊🌊🍁🎭
和歌から能へ、重層的な広がり
高砂は、播磨国(兵庫県)の地名で、松の名所として知られる。松は長寿というイメージが前提にある。
この歌は、老いを嘆いているという点においては、とても普遍的であるように思う。『百人一首』を選んだ当時、74歳であった定家と通う気持ちがあったとする説も見られる。誰しも老いを嘆くものだろうか。その一方で、下の句の「松も昔の友ならなくに」については、英語的な感覚からは新鮮さを感じる。なぜなら、松は人ではないため、そもそも松が友人ではないため、松が友人になることなどあり得ないからである。しかし「松も昔の友ならなくに」=「松も昔からの友人ではない」ということは、つまり今では松が友人であると言い換えることもできるだろう。巧みな擬人化によって、ありえないはずなのに、不思議と納得してしまい、まんまと罠(わな)にはめられて死mさったかのような感覚さえ覚える。
松は『万葉集』の時代から歌によく詠まれている。常緑樹であることから、天皇の御代(みよ)が長く続くことや長寿の象徴として詠まれることが多い。それ以外にも、「待つ」との掛詞(かけことば)として詠まれる場合もある。
また、松と言えば、この歌に詠まれる高砂の松のほかにも、現在の大阪府である住吉の松が有名で、『古今集』仮名序には「高砂・住の江(住吉)の松も相生(あいおい)のやうに覚え」というように、両地名が見える。さらに、世阿弥はこの歌をもとに「高砂」という謡曲を書いた。彼は物まね中心であった能を歌舞中心の優美なものへと昇華した人物として知られ、現在でも多くの作品が上演される。
「高砂」のあらすじは次の通りである。阿蘇神社の神主が上洛の途上、高砂を訪れ、ある老夫婦に「高砂の松」の謂(いわ)れを問う。すると老夫婦は「仮名序」にあった高砂と住の江の松の「相生」や、松のめでたい謂れ、歌道の繁栄を述べつつ、御代を言祝(ことほ)ぐ。老夫婦は、自分たちが高砂・住の江の「相生の松の精」であることを語り、住吉の地で待つと言って姿を消した。神主が住吉へ着くと、住吉明神が出現し、舞を舞って御代を祝福して、終曲を迎える。「高砂」という作品の優美さは、世阿弥の豊かな古典への造詣の深さに支えられている。
第28番の「やまざと」の回でも触れたが、以前、外国人の学者が、和歌はつまらないと言っているのを耳にしたことがある。恐らく彼らが和歌に対してつまらないと感じる理由は、和歌の伝統的な詠み方を重んじる傾向にあるのだろう。しかし、今回の例に見えるように、これまでの伝統、古典的な詠み方を下敷きとして展開していく知の豊かさは、歌の世界のみならず、能の世界にも生きている。歌に詠み継がれた多くの型や文句が、またさらに継がれていくことによって、作品世界に重層的な広がりと深みが生まれるのだ。その伝統の中核にあった和歌にこそ、現代においても人々を惹(ひ)きつけてやまない、この国の伝統文化の魅力が詰まっているのではないだろうか。
📜🌙小倉山日記🪔🖌️ 🪷🪷🪷 🍉🍉🍉 🦆🦆🦆
行きつ戻りつ季節は進む
ここ嵯峨嵐山に住み始めてから、自然のささいな変化に気づくようになった。ある日突然、鶯(うぐいす)はさえずるのをやめた。スイカがありとあらゆる店から姿を消し、代わりにサンマが並ぶようになった。いつまであるのかなと毎日、小倉池に咲く)蓮はす)を眺めていた。最後に蓮の花が落ちたのは9月26日だった。その後、池の一面に広がった蓮は黒がかって見えた。
涼しくなって、ジャケットを心地よく着られるようになった。その夜は2枚の毛布を被(かぶ)って寝た。我が家の猫も寒かったらしく、夜中にふと目を覚すと、毛布の中で猫を腕枕していた。これも春以来のことだった。翌朝、空には無数の小さな雪があった。その雪は太陽の光に輝く貝殻のようだった。
行きつ戻りつしながら季節は進む。数日後にはまた暑くなったのだが、私はこの嵯峨の地で、ようやくやってきた秋の涼しさを楽しんでいる。
詠み人 藤原興風
ふじわらのおきかぜ 生没年未詳。藤原道成の子。宇多期に活躍。『古今集』時代の代表的な歌人。三十六歌仙の一人。