■「ゴガクル」サイト終了のお知らせ■
長い間、みなさまの学習にお役立ていただいてきた本サイト「ゴガクル」(株式会社NHKエデュケーショナルが運営)は、 2025年9月30日 正午をもって終了することになりました。これまでご利用いただき、誠にありがとうございました。 続きはこちら>
おじぎ草さんの おぼえた日記 - 2025年9月4日(木)

この日おぼえたフレーズ(英語・中国語・ハングル)
- おぼえたフレーズはありません。
おぼえた日記
2025年9月4日(木)のおぼえた日記
前の日フランス語応用編
vendredi 22 aôut
Leçon38
De l’Èsorit des lois De l’èducation(2)
モンテスキュー「法の精神」:「教育について」(後編)
🔖今日のテクスト
L’extrême obéissance suppose de l’ignorance dans celui qui obéit:elle en suppose même dans celui qui commande:il n’a point à délibérer, à douter,ni à raisonner: il n’a qu’à vouloir.
和訳例
行きすぎた服従というものが成り立つためには、服従する者が教育を受けていないことがまず必要である。それにはまた、命令する者も無教育であることがやはり必要である。命令する者は、熟考する必要も、あれかこれかと考える必要も、思慮する必要もない。ただ欲するだけでよいのである。
◯語彙説明・構文のポイント
L’extrême obéissance suppose de l’ignorance dans celui obéit:
extrême極限の、極度の、行きすぎた
obéissance服従。l’extrême obéissanceは恐怖によって支配する専制的な政治体制のことを指す。
suppose主語+supposer他動詞qcで(物)は〜を前提とする。この場合、A supposeBは「Aが成り立つためにはBが必要である」「Bがあってこそ初めてAは成立する」とも訳せる。ここではこの訳例を用いた。
ignorance無知。ここでは文脈から「教育を受けていない状態」という語義を採る。抽象名詞ignoranceに部分冠詞がついているのは、supposerの直接目的語となるから、一般に、抽象名詞が不特定の部分量として捉えられるとき、特に他動詞の目的語となる場合には、部分冠詞を用いる。
dans celui qui obéit服従する者における
elle en suppose même dans celui qui commande:
elle 前文のl’extrême obéissanceを受ける。
en前文のde l’ignorance を受ける中性代名詞。この文の主語と動詞については前の文をほぼそのまま反復する構造をとっている。dans 以後の状況補語même dans celui qui commandeの部分が全文とは異なっており、その点で対句的表現となっている。
même dans celui qui commande命令する者においてすら。celui qui commandeは、前の文のcelui qui obéit、すなわち専制国家の国民とは逆に、専制国家の為政者である暴君の王を指す表現。したがってこの文の意味は「極度の服従は、命令する者においてすら、無知を前提とする。
il n’a point à délibérer,à douter,ni raisonner:
il /celui qui commande命令する者を受ける。
ne~point現代フランス語のne~pasと同じ意味。ne pas avoir à+不定詞で「〜する必要はない」。行為をモンテスキューは次の3つの動詞で列挙する。
délibérer熟慮する、思慮する。ラテン語のlībrā(天秤)に由来する語で「天秤によって2つのものを比較する」が語源上の原義。
douter疑う。これも語源に立ち返ってみると、ラテン語のdubitāre2つのものの間で迷う、ためらう」が原義。すなわち「あれか、これかと考える。
raisonner論証する、議論する。語源はラテン語のratiō(比率、割合)。複数のものの大きさや量を比較考慮するが原義。
*上の動詞délibérer,douter,raisonnerは、いずれも複数のものを互いに比べ合うという点で共通する。
il n’a qu’à vouloir.
n’avoir qu’à *不定詞「〜しさえすればよい」
vouloir〜を欲する、望む。専制君主は一人で自分のしたいことをする、熟慮や議論などの必要はない。これはモンテスキューによる皮肉な表現。
extrême
◯Explication de texte
「法の精神」の続きです。極めて緻密に構築された政治哲学的な洞察が、印象深く提示されています。全体の構成は3つの文から成ります。一つ一つがそれぞれ印象的です。どんなテーマを取り上げているかを見てみましょう。
最初の文がl’extrême obéissance「行きすぎた服従」という表現から始まる点に注目すべきです。extrêmeと言う形容詞の使用は、単なる服従のことではなく、その極限的なな形態を批判的に捉えていることを示しています。supposeという動詞の選択も重要です。これは単なる論理的前提以上の意味を持ちます。「AがBを必要とする」という意味合いは、極端な服従と、教育を受けていない状態、つまり「無知」ignoranceとの間に不可分の関係があることを強調しています。すなわち、専制政治が成立するためには、非統治者の無知が不可欠であるという洞察を示しているのです。啓蒙思想家として、彼は教育を単なる知識の伝達ではなく、政治的自由と密接に関連するものとして捉えています。この解釈は逆に、知識が、権力構造を脅かす可能性があるという認識をも示唆しているでしょう。教育は、権力構造を変革する潜在力を持つという視点にも通じています。
2番目の文、 « elle en suppose même dans celui qui commande »は最初の文のcelui qui obéit服従する者に対して対句表現celui qui commande 命令する者を導入しています。モンテスキューはこうして支配ー被支配の関係を明確に示しつつ、支配者の側も同じ「行きすぎた服従」の下にあること、彼もまた被支配者の側と同様に、「無知」の状態にあるという逆説的な状況を浮き彫りにしています。すなわち、専制政治は統治者自身の成長や学びを阻害し、結果として社会全体の停滞をもたらすという洞察です。
3番目の分 « il n’a point à délibérer,à douter,ni à raisonner,il n’a qu’à vouloir, »は、このテクストの核となるモンテスキューの思考を凝縮した部分と言えるでしょう。これらの語の起源に遡ると、いずれも「比較」「熟考」「判断」という意味合いを持っています。君主は、臣下のさまざまな意見によく耳を傾けて、いくつかの可能性を挙げて討議し、その中から最もよいものを選ぶべきだという合意があります。これは、理想的な統治者像、すなわちさまざまな意見を聞き、熟考し、最善の判断を下す者ーを暗示する者でしょう。ところが、これに対して専制君主はこれらを一切行わず、単に「vouloir」(欲する)だけでよいとされています。これは極めて皮肉な表現です。命令者は « il n’a qu’à vouloir »「ただ欲するだけでよい」というこの主張は、専制政治における権力行使の恣意性を批判する者でしょう。
この対比は、理性的な統治(délibérer,douter,raisonner)と恣意的な専制(vouloir)の対立を鮮明に描き出しています。これはモンテスキューの三権分立の発想と深く関わると同時に、政治制度の批判を超えて、人間の理性と意思の関係、さらには自由と専制の本質的な違いを哲学的に問いかけているのです。
モンテスキューのこの一節は、極めて簡潔でありながら、専制政治の本質、教育の政治的意義、理性的な統治のあり方、そして人間の理性と意志の関係という、複数の重要なテーマを巧みに織り込んでいます。その語彙選択と文構造の緻密さは、彼の思想の深さと表現力の卓越性をよく示すものです。
現代的な文脈で考えると、この一節は情報社会における権力と知識の関係や、民主主義における批判的思考の重要性といった問題に新たな光を当てるものでしょう。「行きすぎた服従」と「無知」の関係は、現代のメディアリテラシーの問題や、ポピュリズムの台頭といった現象を分析する上でも有効な視点を提供しています。
モンテスキューは18世紀の思想家。1748年に「法の精神」出版の年、日本では徳川家重の時代。「べらぼう」で振り返ると田沼意知が殺傷されたのが1784年です。「天は見ておる」と言いながら無念の死を遂げた家治の父、家重の時代です。
フランスではブルボン王朝ルイ15世の時代(在位1715−1774)。モンテスキューも男爵の貴族です。匿名で王政批判をしています。
田沼意次、家重の時代、経済政策を打ち立て経済重視の時代背景です。歴史に残る思想家は安藤昌益(1703−1762)吉宗から受け継がれた文治主義の時代です。
どういう時代か具体的には理解していません、実利の時代で、政治思想は未熟だったのかもしれません。安藤昌益、名前しか知りません。あの時代に、三権分立と言っても、ピンと来なかったでしょう。
初めての日本語訳は英訳からの翻訳で,何礼之訳、自由民権運動に影響を与えました。
モンテスキューは現代政治に受け継がれている三権分立を打ち立てた画期的な政治思想家でした。現代の民主主義にも通じるメディア、ポピュリズム、等の問題も先取りしています。選挙で政治家を選ぶことができる民主主義の時代でも、専制政治の国がかなりあるのもまた、歴史と現実政治でしょうか。
時代をさかのぼると1651年にホッブズが「リヴァイアサン」を出版しています。古典中の古典です。岩波文庫の白帯、青帯、中央公論社の世界の名著シリーーズ、日本の名著シリーズを、テキストにしていました。
ほんの一節ですがモンテスキューの「法の精神」をフランス語で触れられたのは、喜びです。退職すると時間を贅沢に使えます。機会があれば、ホッブズを読みたいですが、難しそう。
「源氏物語」は1008年には文献として出ています。後一条天皇出産時の記述が「紫式部日記」にあります。その頃、「源氏物語」を書いているのが知られていました。大河の「光る君へ」に出ていたように。政治思想ではありませんが、時代の古さは他に比べるものはないでしょう。古文で読めるのも日本の教育のおかげです。
何やかやでありがた山です。
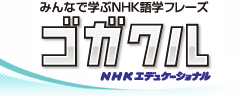





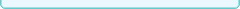
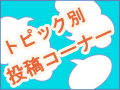







日本語が今も生き残っていることを有難く思っています。
学生時代、古文・漢文の授業が苦手でしたが、もし今日日本語がなくなっていたら歴史を知ることはできなかったことと思うと苦労してよかったと思います。
日本語がローマ字にならなくて良かったですね。 そうなっていたら、古典は読めず、
また、ひらがなのみにもならずに。ひらがなだけのしょうせつはとてもよめたものではございません。 北杜夫の作品で、ひらがなばかりがえんえんとつづくものがありましたがうんざりしました。
田沼意次・意知は商業重視であまり好きではなかったですが、安藤昌益は農業重視の考えだったので同感できました。
江戸時代後半はいろいろな考えが交差しおもしろいですね。