アメリカ民主主義さんの おぼえた日記 - 2015年1月18日(日)

この日記をフォローしているユーザ
この日おぼえたフレーズ(英語・中国語・ハングル)
- おぼえたフレーズはありません。
おぼえた日記
<マリー・アントワネットに別れをつげて>(Les adieux à la reine)
いつもTSUTAYAに行くと貸し出し中で借りられなかったので、この映画はいつか見たいと思っていた。しかも、主演がレア・セドゥ(Léa Seydoux)。ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコルでも好演し、『アデル、ブルーは熱い色』(La vie d'Adèle)でも評判の女優である。事前の期待は膨らむばかりであった。
しかし、個人的にははずれの映画であると思う。豪華なキャストでフランス革命下のベルサイユ宮殿が描かれるのは良いのであるが、フランス革命下の非常にミクロな話で終わってしまっており、ストーリーには物足りなさが残った。
フランス語の勉強という意味では、会話の内容が難しくはないので、良い教材であるとは思う。
<パリ白熱教室 2回目>
2回目はトマ・ピケティー教授の所得格差である。
実は、19世紀のフランスは格差社会であった。1%しかいない貴族が大半の富を所有しており、そこから得られる収入(不動産賃料や配当所得)を独占していた。だから、労働をしなくても裕福な生活ができたのである。
面白いことに、この構図が崩れるのは1929年の大恐慌ではない。このデフレの時代には、社会全体の所得に対する金持ちの所得は増加している。これが崩れるのが第二次世界大戦後である。インフレのせいで、金持ちの所得割合が減少する。そして、フランスの場合は、1968年の五月革命により、最低賃金の上昇などがあり、金持ちの所得割合は減少をたどるのである。
これと対象的なのがアメリカである。アメリカの場合は、労働所得の格差が拡大していくのにつれて、富の偏在も強まっている。そして、この傾向が続けば、フランスの貴族社会以上に、アメリカの所得格差が拡大するという。
アンシャンレジームはフランス大革命で崩壊したのかと思いきや、第二次世界大戦まで続いていたとは興味深い。このことを知らないと、19世紀末の芸術、例えば印象派の画家たちの絵などは理解を深められないように感じた。ドガのエトワールで描かれるバレリーナのパトロンの存在などがその一例であろう。
2回目も英語音声で聞いた。英語で経済の授業を聞くことはまだまだハードルが高いが、「ジニ係数」「ストックオプション」などの経済用語は知っていたので、教授の話はおおよそ理解できた。ただ、生徒の質問が難しい。






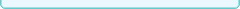







『マリー・アントワネットに別れをつげて』の映画も、宮殿内部の生活を知るために見ていれば、良くできた映画だと思います。ピケティー教授の話を聞くと、民衆がパンを食べるためのお金がないのに、貴族は贅沢ができる理由が少しわかりました。