■「ゴガクル」サイト終了のお知らせ■
長い間、みなさまの学習にお役立ていただいてきた本サイト「ゴガクル」(株式会社NHKエデュケーショナルが運営)は、 2025年9月30日 正午をもって終了することになりました。これまでご利用いただき、誠にありがとうございました。 続きはこちら>
蠱毒さんの おぼえた日記 - 2019年12月1日(日)

この日おぼえたフレーズ(英語・中国語・ハングル)
- おぼえたフレーズはありません。
おぼえた日記
CARLSEN MANGA Carlsen Verlag GmbH・Hamburg 2011
Aus dem Japanischen von Miyuki Tsuji
NARUTO by Masashi Kishimoto
【 接続法第1式について 】
11月29日の日記にアップした登場人物の紹介文のうち
カカシの紹介文の一番最後の文
So viel sei aber verraten : Er kann damit ganz spezielle Kampftechniken anwenden!
前半の So viel sei aber verraten は、sei があるので「接続法第1式」を使っていることはすぐわかったが、イマイチ意味がわからなかった・・・
まぁ何とか、オンライン辞書 Globe で以下の文を見つけたので、上記の文を訳す際の参考にした。
↓
Nur so viel sei gesagt: Die Ursache und der Zweck gefühlsbedingter Tränen bleiben unerklärlich.
ここでは、感情が高まると涙が出る理由と目的ははっきり分かっていないと言うだけにとどめておきましょう。
↓
なので、So viel sei aber verraten の部分は、直訳するなら
「だが彼の秘密を漏らすのは、次のことを述べる程度でとどめておこう。」
という感じか?
さて、接続法第1式についてだが、
ラジオ講座ではあまり語られることがなく、また自分自身もきちんと勉強せずに、きちんと理解しないまま、ここまできてしまっている。
今回はちょうどいい機会なので、接続法第1式の勉強する。
NHK出版「これならわかるドイツ語文法 入門から上級まで」
270・271ページ
◆要求話法
発話内容を「これから起こるべきこと、起こるのが望ましいこと」として語る態度で、ッ接続法第1式を使います。時制は現在です。
(1)要求・希望
2人称に対する要求は命令法で表しますが、
3人称に対する要求・希望には接続法第1式を用います。
Man beachte die Ironie zwischen den Zeilen.
行間に漂うアイロニーに注目するように。
Das sei dahingestellt.
それは不確かなままにしておこう。(これ以上そのことは詮索しない)
Gott sei Dank!
神に感謝あれ(やれやれ、よかった)。
※ Gott が3格、Danke が1格主語。
Möge dir das neue Jahr viel Glück bringen!
新年があなたに多くの幸福をもたらしますように。
↑
上の例文のように
要求話法では定形が文頭に置かれる場合があります。
1人称複数に対する勧誘や、2人称敬称に対する要求も、接続法第1式を用いて表します。
この場合、[定形 - 主語]という語順になります。
Reden wir jetzt über ein anderes Thema!
別のテーマについて話しましょう。
Seien Sie mir bitte nicht böse!
気を悪くなさらないで下さい。
(2)意図・目的
意図・目的を表す従属の接続詞
damit「~するために」によって導かれる副文では
接続法第1式が用いられます。
Wir haben laut gesungen, damit unsere Müdigkeit weiche.
私たちの眠気が消えるようにと歌った。
↓
ただし、目的であることは damit で明示されるため、現在では接続法第1式の代わりに直説法が用いられる傾向にあります。
とりわけ口語では直説法が主流です。
↓
Wir haben laut gesungen, damit unsere Müdigkeit weicht.
なお、例文のように主文で過去のことが述べられている場合でも、
damit 文で述べられるのは「これから実現されるべきこと」であるため
damit 文の時制は、たいてい現在です。
damit で述べられる意図・目的は多くの場合、[um + zu 不定句]を用いて表すこともできます。
281・282ページ
◆間接話法
報道やルポルタージュの文章、小説などには他者の発言の引用がちりばめられています。引用には大きく分けて2通りの方法があります。その発言を引用符に入れてそっくりそのまま引用する方法と、話者の視点から組み替えて本文に組み込んでしまう方法とです。前者を直接話法、後者を間接話法と言います。
直接話法
Max sagte : „Es hat mir viel Spaß gemacht.“
マックスは「楽しかった」と言った。
間接話法
Max sagte, es habe ihm viel Spaß gemacht.
マックスは楽しかったと言った。
間接話法は、話者 / 書き手が他者の発言を自分の視点で語り直す方法、話者の視点を経た間接的な形で引用する方法です。話者の目を通して語られることにより、引用される発言には変更が加えられます。上の例では、マックスの発言の中の3格目的語が mir から ihm に書き換えられています。
加えて間接引用の指標として、定形が接続法第1式になっています。
(1)間接話法の定形
間接話法では通常、接続法第1式が使われます。
接続法第1式によって話者は、その部分が引用であることを表し、
同時に「その内容が事実であるかどうかわからない」
という自分の判断も伝えています。
„Der Messwert stimmt nicht,“ sagte der Arzt.
「計測値がおかしい」と医者は言った。
Der Arzt sagte, der Messwert stimme nicht.
医者は、計測値がおかしいと言った。
接続法第1式が直説法と同形の場合には、代わりに接続法第2式が使われます。
Der Arzt fragte mich : „Haben Sie Beschwerden?“
医者は私に「痛みはありますか?」と尋ねた。
Der Arzt fragte mich, ob ich Beschwerden hätte.
医者は私に痛みはあるかと尋ねた。
話し言葉では接続法第1式はごくまれです。
多くは直説法が用いられ、接続法が用いられる場合には第2式になることがほとんどです。
Der Schüler meint, er hat / hätte die Aufgabe nicht verstanden.
その生徒は、自分は課題が分からなかったと言っている。
ドイツ語の間接話法では、地の文との時制の一致は行いません。
元の発言の定形が現在時制なら接続法第1式現在を、未来時制なら[werde ~ 不定形]を、次例のように現在完了や過去時制なら接続法第1式過去を、それぞれ用います。
„Es war draußem ein Gräusch,“ sagte sie.
「外で物音がした」と彼女は言った。
Sie sagte, es sei draußen ein Geräusch gewesen.
外で物音がしたと彼女は言った。
命令や要求、依頼を間接的に引用する場合には、話法の助動詞を用います。
Der Arzt sagte mir : „Fahren Sie zur Kur!“
医者は私に「療養に行きなさい」と言った。
Der Arzt sagte mir, ich solle zur Kur fahren.
医者は私に療養に行くように言った。
依頼を表す場合には、mögen が用いられます。
Der Sekretär sagte : „Bleiben Sie bitte am Apparat!“
秘書は「電話を切らずにお待ちください」と言った。
Der Sekretär sagte, ich möge bitte am Apparat bleiben.
秘書は、電話を切らずにお待ちくださいと言った。
(2)間接話法の人称代名詞・所有冠詞
間接話法では、他者の発言が話者の視点から再構築されます。
人称代名詞や所有冠詞もこの視点から選ばれます。
Der Reiseleiter flüsterte : „Ich habe meine Stimme verloren.“
添乗員は「私は声が出なくなってしまった」とささやいた。
Der Reiseleiter flüsterte, er habe seine Stimme verloren.
添乗員は、自分は声が出なくなってしまったとささやいた。
直接話法の du や ihr に対する命令文では主語が現れませんが、
間接話法で再現する際には文脈に応じて主語を添える必要があります。
Die Mutter sagte mir : „Pass auf! Du bekleckerst dein Kleid!“
母は私に言った「気をつけて! ワンピースにシミをつけちゃうわよ!」
Die Mutter sagte mir, ich solle aufpassen. Ich würde mein Kleid bekleckern.
母は私に気をつけるように言った。ワンピースにシミをつけてしまうと。
(3)間接話法を導入する接続詞
引用される元の発言が平叙文の場合には、
間接引用を導く接続詞として従属接続詞 dass を用います。
Er sagte : „Ich habe mich geirrt.“
彼は言った「僕は思い違いしていたよ」
Er sagte, dass er sich geirrt habe.
彼は、自分が思い違いをしていたと言った。
元の発言が決定疑問文の場合には ob が、
補足疑問文の場合には、元の疑問詞がそのまま接続詞として用いられ、
元の疑問文は間接疑問文(副文)になります。
Sie fragte: „Kommst du mit?“
彼女は尋ねた「一緒に来る?」
Sie fragte, ob ich mitkomme.
彼女は私に一緒に来るかと尋ねた。
Die Leute fragten das Kind : „Wo sind deine Eltern?“
人々はその子に尋ねた「両親はどこ?」
Die Leute fragten das Kind, wo seine Eltern seinen.
人々はその子に両親はどこかと尋ねた。
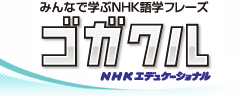





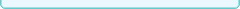
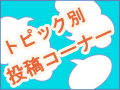







接続詞が使われないこともよくあります。
定形が接続法第1式であれば間接引用であるのが明らかなので
引用を示す接続詞はなくてもよいのです。
Nach Informationen der Nachrichtenagentur hat der Chef des Sportverbandes illegal Geld erhalten. Er habe Hilfsgelder für Erdbebenopfer zur Seite geschafft und für private Zwecke verwendet.
通信社の情報によると、スポーツ協会の会長は不法に金銭を得ていた。彼は地震被災者のための援助金を流用し、私的目的のために使っていたということだ。