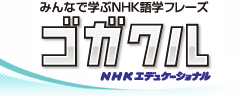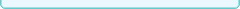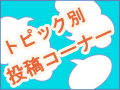HUITTさんの おぼえた日記 - 2024年12月20日(金)

この日記をフォローしているユーザ
この日おぼえたフレーズ(英語・中国語・ハングル)
- おぼえたフレーズはありません。
おぼえた日記

※ caption : Shakespeare Sonnet ⅩⅤⅢ
12/20(金)
「ひさかたの光のどけき春の日にー」
英語で読む百人一首 ピーター・J・マクミラン
不思議の国の和歌ワンダーランド 第33番
2022年9月30日 京都新聞デジタル所載
ひさかたの
光のどけき
春の日に
しづ心なく
花の散るらん
(百人一首カルタでの英訳)
Cherry Blossoms,
on this calm, lambent
day of spring,
who do you scatter
with such unquiet heats?
Ki no Tomonori
[現代語訳]
日の光がのどかに差している春の日に、桜の花は落ち着いた心もなく散ることよ。どうして静かな落ち着いた心もなく、あわたただしく散るのだろうか。
* 歌は新編国歌大観の「百人一首」を原本とし、表記は適宜、かなを漢字に改めています
🌸🌕🌕🌸🌬️🌬️🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌱🌸🍃🌿🌸
同郷の恩師に捧げる儚き美の歌
「ひさかたの」は「ひかり」にかかる枕詞(まくらことば)。一般的に枕詞は現代語訳に反映されない。しかし何らかのイメージを喚起させる場合もあり、『万葉集』では「ひさかたの」は「悠久の」や「不変の」という文脈で使われることが多い。作者の友則は『万葉集』をよく勉強していたらしく、そのことを踏まえるならば、彼のよんだ「ひさかたのひかり」は悠久の光であって、太古の昔からずっと変わらない光と解釈することができる。そうした光が降り注ぐのどかな春に、せわしなく桜が散る。これは太古の昔から繰り返され、またこの先も続くであろう。このように、春の暮れゆくさまに対する感動を詠んだ歌として友則の歌を理解する説もある。ただし、今日一般には「こんなにのどかな春の日に、どうして桜の花はせわしなく散っていくのだろう」という、桜に対する恨みを詠んだ歌として理解されている。そのため、現代語訳は通説に近いものとした。
英訳においては、一般的な解釈と、春が暮れゆくさまの感動を詠んだとする解釈のどちらでも味わえるようになっている。しかし、個人的には、後者の解釈でこの歌を捉えた方がしっくりくるように思う。桜があっけなく散ってしまうものであることは、今も昔も変わらない。つまり、桜というのは本質的に儚(はかな)いものであり、その「あはれ」がこの歌に詠まれているのではないだろうか。下に紹介したシェイクスピアのソネットに表れる、美は永遠に生き続けるものという英語詩の感性とは対照的だ。
この歌に触れると、いつも加藤アイリーンさんのことを思い出す。アイリーンさんは私と同じアイルランドの出身で、私の恩師であるとともに佳(よ)き友人でもあった。彼女は和歌の中でもとりわけこの歌が好きだった。もともとアイリーンさんは、アイルランドの偉大な詩人であるイェイツの詩をこよなく愛していたのだが、日本の古典文学と出会い、ドナルド・キーン先生に古典を学び、遂(つい)には女性としても外国人としても初めての天皇陛下の御用掛にまでなった。まさにアイルランドと日本の架け橋となった人である。アイリーンさんが亡くなった後、私はアイリーンさんとキーン先生を題材として「エリスの橋」という新作能を作った。
実は、私が『百人一首』の翻訳に初めて取り組んだ時、アイリーンさんに添削をお願いしていた。アイリーンさんから戻ってきた原稿には、あちこちに赤いペンで修正が加えられており、その真っ赤になった原稿は今も宝物だ。また、アイリーンさんとは、生前、一緒に京都を巡ったこともある。その時には、常寂光寺や二尊院などに案内してもらったのであるが、数十年後にまさか自分がこの二つのお寺のある嵯峨に住むことになるとは思わなかった。アイリーンさんに出会わなければ、私が『百人一首』の翻訳をすることも、こうして京都新聞で連載をすることもなかったかもしれない。心からの感謝を込めて、このエッセイをアイリーンさんに捧(ささ)げたい。
💠💠 英語詩の世界から
シェイクスピアのソネット第18番
When in eternal lines to time thou grow'st,
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee
訳 人間が息のできる限り、目の見える限り、この歌は生き続け、あなたに命を与えていきます。この永遠の歌の中で、あなたは永遠に生きます。
詠み人 紀友則
きのとものり 生年未詳。905年ごろ没。紀貫之のいとこ。『古今集』選者の一人だが、完成前に亡くなっている。三十六歌仙の一人。