Keona Keahiさんの おぼえた日記 - 2011年4月26日(火)

この日おぼえたフレーズ(英語・中国語・ハングル)
- おぼえたフレーズはありません。
おぼえた日記
中国といって真っ先に思い浮かぶ作家は星野博美さんなんだけど、著作・エッセイがあまり多くないので読み始めたらすぐに全部読み終わってしまう。
もったいないので中国の紀行3部作を読んだ後は、ちょっと読むのを休んでる。新しいエッセイが出たら旧作をひとつ読み始めるという感じで細く長く読んでいきたい。
ネットに情報も少なく、唯一の公式情報といえるのは星野さんの師匠橋口譲二さん主催のAPOCCくらいだ。それがちょっとさびしいけど、そういうスタンスの作家だから好きだという面もある。
JICA横浜でベトナムの子どもたちによる写真のワークショップが開かれたときに、スタッフだった星野さんをお見かけした。見かけたというより、個人的には星野さんに会うために横浜まで出かけて行ったのだけど。
でも結局、声をかけることもなくシンポジウムを聞いて帰宅した。星野さんの個展ではなかったので、なんとなく場違いな気もして。たぶん私の姿を会場風景を撮影していた星野さんのカメラは捉えている(笑)。
私はコミュニケーション下手だ。インタビューとかそういう仕事モードなら可能だけど、素の自分として人と相対するのが苦手だ。常に演じていなければ落ち着かない。それで損してると思うことも多々ある。
JICAのときもそれでちょっと悔しい思いも残ってる。文章を書くようにしゃべれたらもっと違った生き方が出来たのではないかと思う。
きっと外国語を覚えてもコミュニケーション下手は直らないだろう。押しの強い中国人とのコミュニケーションなんてほとんどできないような気がしている。
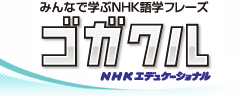






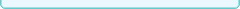
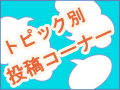






ま、2言語といっても中国語はやってるといえませんけどね。
それにしてもゴガクル事務局は我々を甘く見てましたね(笑)。40人までしか皆勤賞紹介に対応してなかったとはっ!40人が50人になり、そのうち100人を超えて月間皆勤賞が意味無くなってしまうくらい自然なことになればいいですが。
ただやっぱり日本語だけ書いていくというのはなんだかゴガクル日記でやる必要がないので、できるだけ外国語を綴りたいとは思ってます。中国語もハングル上達のための道具にしたいと思います。
私は語学をコミュニケーションの道具、手段としてとらえていました。
なので、Keona Keahiさんの日記に「韓国語への熱意、学校英語への憎悪」と
「洗練された日本語」をみて、言語という大きなカテゴリの中では同じなのに
何故だろう、とすごく不思議でした。
でもそんなところが読む人をひきつけてやまないのかなぁ…
ただ、私は学校英語について書いておられるのを読むと
どうしてだか、いつも胸が痛むのです。自分が英語学習者だから、とかじゃなく。
最後になりましたが、2言語での(!)皆勤賞おめでとうございます。
私自身の語学に対するイメージは「無人島に残された人類最後の一人になってもやってる」というものでした。学校英語、受験英語のせいでそのような究極の無駄というイメージを持ってしまった不幸な語学体験をいまゴガクルで徐々に解きほぐしている、あるいはリベンジしているところです。
語学はコミュニケーションの道具にも使えますが、知的好奇心を拡大する道具でもあるので、おそらく私の場合は後者ですね。話せなくても読んで書けて聞ければ情報をインプットできるので。その意識が変わらないとなかなかコンミュニケーション上手にはなれないんでしょうね。
ただ「あの人はコミュニケーションが上手だな」と見える人も、実際は数えきれない失敗を重ねてもめげなかった人だってことかもしれませんね。Keona Keahiさんは韓国語をかなり勉強されていますが、変化はありませんか。私は英語の表現を学んで、日本語での説明が少しうまくなって感情(好き、うれしい)表現が言葉にできるようになった気がします。
コメント欄に長々とすみません。