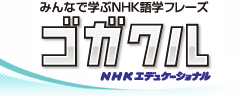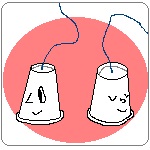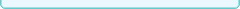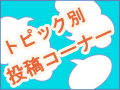■「ゴガクル」サイト終了のお知らせ■
長い間、みなさまの学習にお役立ていただいてきた本サイト「ゴガクル」(株式会社NHKエデュケーショナルが運営)は、 2025年9月30日 正午をもって終了することになりました。これまでご利用いただき、誠にありがとうございました。 続きはこちら>
風鈴さんの おぼえた日記 - 2022年5月4日(水)

この日記をフォローしているユーザ
おぼえた日記
スッキリ!初めてのドイツ語 名詞の格と動詞、そして構文 Mittwoch, 4. Mai
第4回 中級への道、名詞の格と動詞、そして構文
① 格と動詞
格は基本的には名詞が文中でどのような働きを持つのかをハッキリさせる手段である。前置詞に支配されるときは、格の働きが見えにくくなる。格が格らしく働く場合、つまり格が動詞と一緒に働く場合を考える。
1格は動作を行う人、4格は動作を受ける人やモノ。と考えるが、実はそんなに簡単ではない。受動態では、動作を受ける人やモノが1格になるし、受動態でなくても
Mir gefallt das Lied. 私はその歌が好き
●mir [miːrミーア] 人称代名詞ichの3格
gefallen [ɡəfálən](自)(~³の)気に入る
das Lied [liːtリート] n. 歌 song
このように1格に気に入られる物、3格に気に入る人が現れます。格は名詞の文の中の働きはしますが、それが文中の役割と一対一で結びついているかというと、そうでもないことが分かる。確かに1格が動作を行う人で、4格が動作を受ける人や物を表すことが多いがこれは典型的な場合に過ぎない。ではどう考えるか。
▶ ある格の名詞は単独では使わず、動詞と一緒に使う
つまり、それぞれの動詞がどんな格と使われるのか知っておけばいい。動詞がどの格と一緒に使われるのか、つまり動詞の格支配を知ることが役に立つということだ。
② 動詞が格を支配する?
動詞がどんな格の名詞を取るのか、いくつ名詞を取るのか、研究者は考えてきた。文を作る際にドイツ語は日本語とは違い、主語や目的語が省略されず表せることが多い、どれが文を作るのに必要な動詞の要素なのかが問題になる。
Das kind löst eine Aufgabe. 子どもが課題を解く
●lösen [løːzənレーゼン](問題を⁴)解く solve
lösen は1格、4格の2つ名詞をとる動詞
Die Lehrerin lehrt die Schuler Deutsch.
先生が生徒にドイツ語を教える
●lehren [léːrənレーレン] (〔…⁴に〕…⁴を)教える teach
lehren は1格、2つの4格を取る動詞
Die Großmutter legt ihre Brille auf den Tisch.
●legen [léːɡ°ənレーゲン] …⁴を…に(前置詞句)置く、しまう put
legen は auf den Tisch 前置詞句をも必要としていると考えられている。4格の目的語とともに必ず必要なので「前置詞目的語」とされている。
Ich wohne in Berlin.
●wohnen [vóːnənヴォーネン] (+場所) ~に(場所)住んでいる live
in Berlin も必ず必要なので同じく前置詞目的語です。
▶ 動詞が格を支配すると考えれば、helfen が人「を」助けるなのに3格で使う、fragen が「たずねる」が「に」なのに4格が使われるのも、動詞がそう決めているからだといえます。
格の意味は気にすることはありません。
③ 構文が格を決める?
しかし、ドイツ語では動詞が格を支配しているだけでは説明が難しい文がある。
Die Kleine isst Reis, niest ihn in die Schüssel zurück.
小さい女の子はご飯を食べるが、くしゃみをしてご飯を器に戻す
●niesen [níːz°ənニーゼン] くしゃみをする
●Schüssel [ʃʏsəl] f. 深皿 bowl
niesen は4格と使われているが、本来4格を取らない動詞である。日本語でも「ご飯をくしゃみする」とは言えない。niesen は4格を支配してるわけではない。
この文では必ず4格と in die Schussel という方向の前置詞句がないといけない。
「動詞」+4格名詞+方向の前置詞句」という型がある
これ全体が「動詞の動作することで4格名詞が前置詞句で表せる方向に移動する」という意味の構文になっている。この構文に niesen のような動詞が入ったのがこの例になる。そのために「くしゃみでご飯を器に戻す」という意味が表される。ここで格を決めているのは動詞ではなく、動詞を取り囲む構文である。
▶ ほかにもある構文
Sparen Sie sich reich! 節約してお金持ちに!
●sparen [ʃpáːrənシュパーレン] 節約する
sparen+4格名詞+形容詞:4格名詞が形容詞の状態になる、という構文。
「動詞+方向の前置詞句」
Die Straßenbahn quietschte um die Ecke.
路面電車がキーキーと音を鳴らしながら角を曲がった
●quietschen [kvíːtʃən] キーキーきしむ
quiettschenの様態で前置詞句方向に移動する
動詞の周囲の型自体に意味があり、それに動詞と合わさって全体の意味が生じると考えられている。
④ 動詞と構文は助け合う
動詞が格を決めるのか、それとも構文が格をきめるのか。どちらの場合もあるというのが結論になる。それがドイツ語だ、ってことにしておこう。
ドイツ語は英語に似ている。第4文型目的語(名詞)を2つ取る動詞(授与動詞あげる・くれる動詞)、ちょっと難しい第5文型SVOC「目的語(名詞)+形容詞など」や動詞+前置詞句(前置詞+名詞…の構文は英語でもずいぶんやったなぁ。