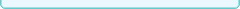HUITTさんの おぼえた日記 - 2024年7月13日(土)

この日記をフォローしているユーザ
この日おぼえたフレーズ(英語・中国語・ハングル)
- おぼえたフレーズはありません。
おぼえた日記

7/13(土)
"Homage to Catalonia"George Orwell
「カタロニア讃歌」ジョージ・オーウェル
continuation from last time(jul.10'24)first appearance(jun.19'23)(初出)
_
And at the back of town there was a shallow jade-green river, and rising out of it a perpendicular cliff of rock, with houses built into the rock, so that from your bedroom window you could spit straight into the water a hundred feet below. Innumerable doves lived in the holes in the cliff. And in Lerida there were old crumbling buildings upon whose cornices thousands upon thousands of swallows had built their nets, so that at a little distance the crusted pattern of nets was like some florid moulding of the rococo period.
町の裏手に翡翠(ひすい)のような緑色の浅い川が流れている。そこから、切り立った岩の断崖がそそり立ち、その岩の中に家が作りつけになっているので、寝室の窓から唾を吐くと、百フィート下の川へまっすぐに落ちていく。崖の穴には、無数の鳩が住んでいた。レリダには、古い崩れかけた建物があり、その突き出た軒じゃばらに、何千というツバメが巣を作っていた。ちょっと離れたところからながめると、その表面にこびりついている巣の格好が、何かロココ時代のけばけばしいじゃばらとそっくりだった。
It was queer how for nearly six months past I had had no eyes for such things. With my discharge papers on my pocket I felt like a human being again, and also la little like a tourist. For almost the first time I felt that I was really in Spain, in a country that I had longed all my life to visit. In the quiet back streets of Lerida and Barbastro I seemed to catch a momentary glimpse, a sort of far off rumor of the Spain that dwells everyone's imagination. White sierras, goatherds, dungeons of the Inquisition, Moorish palaces, black winding trains of mules, grey olive trees and groves of lemons, girls in black mantillas, the wines of Malaga and Alicante, cathedrals, cardinals, bull-fights, gypsies, serenades - in short, Spain. Of all Europe it was the country that had had most hold upon my imagination. It seemed a pity that when at last I had managed to come here I had seen only this north-eastern corner, in the middle of a confused war and for the most part in winter.
六か月近くものあいだ、このようなものがまったく目に入らなかったというのもおかしな話である。除隊許可証をポケットに入れたとたんに、私はまた人間に帰ったような気がして、ちょっぴり観光客気分にもなったのだ。私は、ほとんど初めて、自分がほんとうにスペインに来ているのだな、という気がした。一生に一度はいってみたいと憧れていたこの国に。レリダやバルバストロのひっそりとした裏通りでは、あらゆる人びとの想像の中に住んでいるスペインをちらとながめ、その遠いざわめきのようなものをちらと耳にした思いだった。鋸(のこぎり)の刃のように尖った白い山脈(やまなみ)、山羊飼い、中世の宗教裁判の土牢、ムーア人の宮殿、黒々とうねるように続くラバの行列、灰色のオリーブの木、黒い大きなスカーフをかぶった若い女たち、マラガやアリカンテの葡萄酒、大伽藍、枢機卿、闘牛、ジプシー、小夜曲(セレナーデ) ー 要するに、スペイン、なのだ。すべてのヨーロッパの中で、私の想像をいちばん強くとらえてやまない国なのだ。せっかくその憧れの国へやってくることができたのに、戦争騒ぎのまっさいちゅうで、しかもほとんどが冬のあいだとあって、この北東の片すみを見ただけというのは、いかにも残念な気がした。
It was late when I got back to Barcelona, and there were no taxis. It was no use trying to get the Sanatorium Maurin, which was right outside the town, so I made for the Hotel Continental, stopping for dinner on the way. I remember the conversation I had with a very fatherly waiter about the oak jugs, bound with copper, in which they served the wine. I said I would like to buy a set of them to take back to England. The waiter sympathetic. 'Yes, Beautiful, were they not? But impossible to buy nowadays. Nobody was manufacturing them anylonger. This war - such a pity!'We agreed that the war was a pity. Once again I felt like a tourist. The waiter asked me gently, had I liked Spain; would I come back to Spain? Oh, yes, I should come back to Spain. The peaceful quality of this conversation sticks in my memory, because of what happened immediately afterwards.
バルセロナに帰ったときは、もう時間が遅くてタクシーはなかった。町のはずれにあるモーリン療養所まではとても行けなかったので、コンティネンタル・ホテルへいくことにして、途中で夕食をとった。私は、葡萄酒を入れて出してくれた、鍋のたがのはまったカシの水さしのことで、人のよい親爺さんふうな給仕と交わした言葉のやりとりを、今でもおぼえている。こいつを一組買って、イギリスへ持って帰りたいんだけどねえ、と私は言った。老給仕は同情顔に言った。「いや、ごもっともです。きれいなもんでしょう? でも、今ごろは手に入らないんですよ。作るものがもういないんです ー だれも作りません。この戦争がねえ ー ほんとに困ったもんですよ!」 この戦争が困ったもんだという点で、われわれの意見は一致した。私は、観光客のような気分になって来た。老給仕がていねいな口調で聞いた、スペインがお気に召しましたか、またスペインへいらしていただけますか? ええ、そりゃもちろん、また来ますとも。このような性質のもの静かな言葉のやりとりは、その直後に起こった事件が事件だけに、私の記憶にこびりついて離れない。
When I got to the hotel my wife was sitting in the lounge. She got up and came towards me in what struck me as a very unconcerned manner; then she put an arm round my neck and, with a sweet smile for the benefit of the other people in the lounge, hissed in my eyer:
ホテルに着いてみると、妻が休憩室(ラウンジ)にすわっていた。彼女は立ち上がると、びっくりするようなひどくよそよそしい態度で歩み寄ってきた。それから、私の首に抱きつくと、休憩室(ラウンジ)に居合わせたほかの人たちに感づかれないようにわざとやさしくにっこりしながら、私の耳に小声で鋭くささやいた。
'Get out!'
'What?'
'Get out of here at once!'
'What?'
'Don't keep standing here! You must get outside quickly!'
'What? Why? What do you mean?'
「出ていってちょうだい!」
「何だって?」
「ここからすぐに出ていってちょうだい!」
「何だって?」
「ここに立ってちゃだめなの!すぐに出て行かなくちゃいけないのよ!」
「何だって?どうして?何いってるんだ?」
She had me by the arm and was already leading me towards the stairs. Half-way down we met a Frenchman - I am not going to give his name, for though he had no connexion with P.O.U.M. he was a good friend to us all during the trouble. He looked at me with a concerned face.
彼女は、私の腕をつかんで、ぐいぐいと階段のほうへ連れていく。階段を降りる途中でひとりのフランス人に会った ー 彼の名前は伏せておく、というのは、POUMにはまったく関係のない人だが、あの市街戦のあいだじゅうずいぶん親切にしてくれたからだ。彼は心配そうな顔で私を見た。
'Listen! You mustn't come in here.
「いいですか!あなたはここへ来てはいけないんです。