gongongonさんの おぼえた日記 - 2024年4月9日(火)

この日記をフォローしているユーザ
この日おぼえたフレーズ(英語・中国語・ハングル)
おぼえた日記

I'm not sure but I would guess 〜
(確信はありませんが〜だと思います)
I'm not sure で確信が持てない様子を、さらに guess を使っているため、確信度はかなり低く(20%程度)なります。 そのため、控えめに自分の意見を主張する表現になります。
相手の意見に賛成できない際に、それを柔らかく伝えることができます。
A. I'm not too knowledgeable about paintings, but these look very expensive.
<私は絵画には疎いけど、とっても高そうな絵ばかりね。>
B. How much do you think this painting is worth?
<この絵画はいくらの価値があると思う?>
A. I'm not sure, but I would guess it's probably worth a million dollars.
<確信はないけど、たぶん100万ドルくらいの価値があると思うわ。>
A. What time do you think you'll be back?
<何時くらいに戻れると思う?>
B. I'm not sure, but I would guess it'll be around 7pm.
<定かではないけど、だいたい19時ぐらいかな。>
A. Okay, I'll be waiting for you here.
<了解、ここであなたを待ってるわね。>
なお、guess は口語で使うのが一般的で、書き言葉ではあまり使われません。また、カジュアルな印象を与えるため、使うシーンには注意しましょう。
I'm confident that 〜
(私は〜だと自信があります)
that 以下の内容に関して、
「確信している、自信を持っている」という意味で使います。信念の強さや、実現への期待が伺える言葉です。
hit it off
(意気投合する/気が合う)
初対面の人と出会ってすぐに
意気投合して盛り上がったり
すること、ありますよね。
そのような「ウマが合う」「話が合う」人と出会った時に使えるフレーズです。
A. I went to your company for my job interview yesterday.
<昨日、あなたの会社の面接に行ったわよ。>
B. How did it go? Did you talk with the vice president?
<どうだった?副社長と話した?>
A. Yes. We hit it off from the start, and I was hired on the spot.
<ええ。最初からすごく話が合って、その場で採用されたわ。>
I suppose
(私は〜だと思います)
「〜と思う」と言うときに一番
よく使うのは " I think " ですよね。
I suppose も日本語訳は同様ですが、その確率に違いがあります。
I think の確率を50%とすると、I suppose 20%〜30%程度です。 これは、ほぼ根拠なく意見を述べる " guess " と同じですが、suppose は
よりフォーマルな言い方です。
I believe
(私は〜だと思います)
believe にはご存知のとおり
「信じる」という意味があります。 したがって、「きっとそうだと思う」のように強い期待をもっている場合や、何かしらの確実性が伴う場合に使われます。
A. May I help you?
<承りましょうか?>
B. Yes, I'm wondering if I could sign up for this course.
<はい、このコースに申し込めるでしょうか。>
A. You may, and it's a good choice too. I believe this course will help you improve your English.
<はい、申し込めますよ。いい選択ですね。このコースは英語力を向上させてくれると思います。>
p.s. 写真は深大寺植物公園の桜、品種は忘れました。
『ユダヤ人』
ユダヤ教は紀元前に出来上がりました。 そのころ日本はまだ縄文時代です。 二千年以上にわたって、ユダヤ人の宗教的ライフスタイルは、基本的に同じ形を保持しています。
神の名はヤハウェだが、名を口にするのは異れ多いというので、ユダヤ人はただ「主」とだけ呼ぶようです。
一番大事とされるのは律法です。 律法の解釈ができる学者をラビと呼びます。 キリスト教の牧師にあたる指導者です。
ラビは律法を読みこなして、人々の相談に答えます。 人々が礼拝をする施設を、シナゴーグといいます。 これはキリスト教の教会堂に相当します。 ユダヤ人はふっう、1週間に1度の安息日を守ります。 これは祈りの日であり、絶対に労働してはいけないのです。 ただし、これを厳密に守ろうとすると、めんどうなことになる。 調理も、車の運転も、労働だからだ。だから、戒律に厳格に従おうとする人は、安息日には仕事をしなくてすむようにしておきます。
こうした戒律をみなが厳格に守るわけではないのです。 厳格に守ろうとする人々は「正統派」。適当にやるのは「改革派」。その中間が「保守派」。
戒律をあまり守らない人でも、成人式(男子は13歳、女子は12歳)などの儀式は守るのがふつうです。
そのほか、ユダヤ暦に沿った年中行事もたくさんあります。 一番大事なのは、「過ぎ越しの祭り(ペサハ)」という行事で、この日には家族や親戚が集まって、お祈りをしたりごはんを食べたりします。 なにしろ、行事があるたびに一族が集まって過ごす習慣です。 なかなか楽しい宗教だという人もいます。
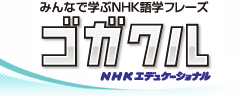






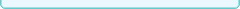
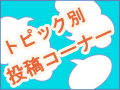






男子13歳、女子12歳の成人式とは、ずいぶん早いのですね。日本だとまだまだ幼いイメージがあります。
今季は、まだまだ桜が見られるでしょうか?
ユダヤ教は一族の結束が強い宗教のように感じました。
今日は朝から強い雨が降ってますね。
ユダヤ人ですと、シャイロックが連想されます。
時代と共に、安息日を厳格に守るのは、難しくなっていそうですね。