gongongonさんの おぼえた日記 - 2024年10月27日(日)

この日記をフォローしているユーザ
この日おぼえたフレーズ(英語・中国語・ハングル)
おぼえた日記

Do over(やり直す)
do overは何かをやり直すことを意味する日常表現です。
do againと意味は似ていますが、do overにはより良くするためにやり直したり改善するニュアンスが含まれます。
報告書の誤りを書き直したり、練習中に失敗をやり直すような状況で使われます。
There are too many mistakes. Do it over.
(間違いが多すぎます。やり直してください。)
You just have to keep doing it over and over again until you get used to it.
(慣れるまでは何度も何度も繰り返すしかありません。)
If I could do it all over again, I’d travel more in my twenties.
(もし人生をやり直せるのであれば、20代のうちにもっと旅行をします。)
Not ____ enough(十分に〜でない)
直訳で「十分に〜でない」となるこの表現は、日本語に訳しづらい日常表現の一つです。
例えば、セミナー会場を探している時に紹介された部屋が小さすぎると思った時、多くのネイティブは“This room is too small.”と言う代わりに“This room is not big enough.”と言うでしょう。 その他、「お肉に十分が火が通っていない」は“This meat is not cooked enough.”、「スープがぬるい」は“This soup is not hot enough.”のように表現します。この表現は、基本的に“not + 形容詞 + enough”の形式で表します。
That box is not big enough. Do you have a bigger one?
(その箱は小さすぎます。もっと大きい箱はありませんか?)
I can’t reach it. I’m not tall enough.
(私は背が低すぎて届かないよ。)
This extension cord isn’t long enough. What should we do?
(この延長コードでは長さが足りません。どうしましょうか?)
Big fish in a small pond(お山の大将、井の中の蛙)
直訳で「小さな池の中の大きな魚」を意味するこの表現は、小さなグループの中で誰よりも影響力や権力、知識を持っている人を指し、ことわざの「お山の大将」や「井の中の蛙」とほぼ同じ意味になります。
一般的にこの表現は、小さなグループの中では力があっても、大きなグループに入るとほとんど影響力がないというニュアンスで使われます。
Going to college made me realize I was just a big fish in a small pond in high school.
(高校時代の自分は井の中の蛙に過ぎなかったということを、大学に進学したことで実感した。)
He talks big, but he’s just a big fish in a small pond.
(彼は偉そうなことを言っていますが、お山の大将に過ぎません。)
When I was living in the countryside, I felt like I was a big fish in a small pond.
(田舎に住んでいた頃、自分は井の中の蛙のように感じていました。)
Deep down(心の底では)
deep downは表に見せることのない本心を表し、「心の底では」や「内心は」を意味します。
日常会話では、deep down insideやdeep down in my heartのように表すこともよくあります。
I think deep down, she knows what she did was wrong.
(彼女は心の底では自分のやったことが間違っていたとわかっていると思います。)
He doesn’t say much, but deep down, he really cares about you.
(彼はほとんど何も言わないけど、心の底ではあなたを大切に思っています。)
I know he comes off arrogant, but deep down, he’s a good person.
(彼は傲慢な印象を与えますが、根は良い人なんです。)
Come out of one’s shell(真の自分をさらけ出す)
shellは「殻」、come out ofは「〜から出る」を意味することから、come out of one’s shellは「真の自分をさらけ出す」ことを意味します。
特に内気でシャイな人が社交的になったり、自己表現をしながら積極的に人と話すようになる状況で使われることが多く、「打ち解ける」や「心を開く」ことを意味します。
It took me a while to come out of my shell.
(真の自分をさらけ出すのに時間がかかりました。)
I’m sure he’ll eventually come out of his shell.
(彼はきっとそのうち心を開くと思うよ。)
It looks like Lisa really came out of her shell. She’s really friendly and talkative now.
(リサはかなり打ち解けたみたいだね。今では、彼女はとてもフレンドリーでおしゃべりだ。)
p.s. 写真は昨日の富士山と蕎麦の花。
初冠雪待ちどうしいですね。
『茶は東にありき』
お茶のルーツは中国にあり、人類とお茶との出会いは遥か5000年も前、紀元前2737年に遡るといわれています。
世界最古の茶のバイブル書『茶経』によると、お茶を発見した人物は、中国の神話伝説に登場する三皇五帝の一人、炎帝神農。
「医薬の神様」とも呼ばれる神農は、野山を駆け巡り、あらゆる種類の草木を口にして薬草の研究を続け、東洋医学や漢方の基礎を築いた祖ともいわれています。
そんな神農とお茶が出会った瞬間は、とてもロマンティックに語り継がれています。
ある日、神農が木陰で白湯を飲むために休んでいたところ、手にした湯のみの中に風に吹かれて数枚の木の葉がハラハラと舞い降りたそうです。しばらく眺めてから口にしたところ、今まで味わったことのない素晴らしい香りと味に、たちまち魅了されたといいます。
その葉こそカメリア・シネンシス=お茶の葉で、ここから長い茶史がはじまったとされています。
(最近読んだ英国流アフタヌーンティーより、続きます)
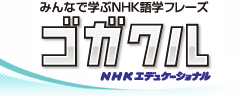






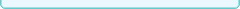
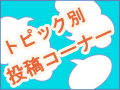






はるか昔でしたら、10月10日ごろには北岳(3193m)雪ふりました。
お茶はほのかな香りとまろやかな味で体に優しいですね。