ぴのみさんの おぼえた日記 - 2024年10月24日(木)

この日記をフォローしているユーザ
この日おぼえたフレーズ(英語・中国語・ハングル)
- おぼえたフレーズはありません。
おぼえた日記
◇ラジオ英会話 2024.10.17&24 L134 説明ルール①リポート文
★主語の思考・発言・知識をリポート=説明ルール
I don’t know if it’s the same person or not.
I think / believe / know he’s a good guy.
He promised me he would marry me.
I’m sure that you’ll get the job.
Let me know what happened.
ダグ、雨戸は閉めた?
Doug, did you close the storm shutter?
☆storm shutter 雨戸
閉めたよ、シホ。窓はもう大丈夫だ。
Yes, Shiho. The windows are protected.
ありがとう。この地域の台風は強力だから。
Thanks. Typhoons here are powerful.
☆Typhoons限定詞を伴わない名詞「~一般」
ねえ、ちょっとこれを見てもらえる?
Hey, can you take a look at this?
☆take a look at ~ ~をちょっと見る
どうしたんだい?
What’s up?
このメールなの。本物のメッセージがどうかわからなくて。
It’s this email. I can’t tell whether this is a real message or not.
☆tell whether ~ (or not) ~かどうか判断する
どういうことだい?
What do you mean?
アーノルド・シルベスターという人から送られてきたの。
It was sent by a person named Arnold Sylvester.
☆受動態 過去分詞を説明語句に用いた「説明型」
あの有名な俳優の?
The famous actor?
そうらしいわね。でもこれが本人かどうかわからないけれど。
この島に来てみたいんですって。
It seems like it. But I don’t know if it’s the same person or not.
He wants to visit our island.
◎Target Forms
私は、それが同じ人かどうかわかりません。
I don’t know if it’s the same person or not.
私は、彼はいい人だと思います/信じています/知っています。
I think / believe / know he’s a good guy.
彼は、私と結婚すると約束しました。
He promised me he would marry me.
あなたはその仕事をきっと手に入れますよ。
I’m sure that you’ll get the job.
何が起こったのか私に教えてください。
Let me know what happened.
◎Grammer in Action
それはすばらしいアイデアだと思います。
なぜ私がそれを思いつかなかったのかわかりません。
I think that’s an excellent idea.
I don’t know why I didn’t think of that.
彼は、私たちはここに駐車することはできないと言いました。
私たちは車を動かさなくてはなりません。
He told me that we can’t park here.
We have to move the car.
申し訳ありませんが、あいにく私たちはあなたの部屋を変更することができません。
ホテルは現在のところ満室なのです。
Sorry, but I’m afraid that we can’t change your room.
The hotel is currently full.
◇ラ・ガブリュイエールを読む Leçon 5 jeudi 24 octobre
Dans cent ans「100年後には」 ①
◎今日のテクスト
Dans cent ans le monde subsistera encore en son entier : ce sera le même théâtre et les mêmes décorations, ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue, ou ce qui s'attriste et se désespère sur un refus, tous auront disparu de dessus la scène.
100年後、世界はまだすっかりそのまま残っているだろう。劇場は同じ。舞台装置も変わらない。役者は同じではない。恵みを受けて喜ぶ者、拒否されて悲しみ絶望する者、みな舞台から姿を消してしまうのだ。
◎語彙説明・構文のポイント
Dans cent ans le monde subsistera encore en son entier:
①dans cent ans 「100年後に」。[前置詞 dans + 時間を表す数量 表現]で「(今から)~後に」。現在を起点とした将来のある時点を表す (= au bout de cent ans)。「100年後」は古典古代の文学では、現在のすべての世界が消え去り、新しく移り変わる世界のもろさやはかなさを示すトポス(定型的詩的表現)の一つだった。
②le monde subsistera encore 「世界はまだ存続し続けているだろう」。le monde は「世界」「宮廷社会」を指す。subsistera は動詞 subsister「存続する、断続する」の直説法単純未来形3人称単数形。
③en son entier 「その全体のままで」。entier「全体、総体」。ラテン語の integer 「手つかずの、全体の」が語源。同じ語源からの派生語に intégral「完全な、全面的な」。dans/en son entier は dans sa totalitéと同じ。「どこも欠けていない総体として」の意味。
ce sera le même théâtre et les mêmes décorations,
①指示代名詞 ce は形式的主語で前文の説明をしている。「(残り続けた世界にあるのは)同じ劇場、同じ舞台装置だろう」。
②décoration「舞台装置」(=décor)。
ce ne seront plus les mêmes acteurs.
①同じくceは形式的主語で前文の説明。ne~plus「もはや〜でない」。「(残り続けた世界にいるのは)もはや同じ役者たちではないだろう」。
Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue, ou ce qui s'attriste et se désespère sur un refus,
①tout ce qui 関係代名詞 quiの先行詞ce は、通常はことやものを表すが、ここでは例外的に人を指す。
②se réjouit < se réjouir 「喜ぶ、浮かれ興じる」
③sur「(基礎や支えとなるものを指して)~を根拠に、~を理由に」
④grâce 「(位の上の人からの)寵愛、厚意」
⑤reçue 「受けた、授かった」(recevoir の過去分詞)
⑥ou ce qui s'attriste et se désespère 「あるいは悲しみ、そして絶望する人」。ceは前述と同じ。ここも例外的用法。
⑦sur un refus「拒絶されたそのために」。surは上述と同じ。
tous auront disparu de dessus la scène.
①tous auront disparu 「すべての人々は消え去ってしまうだろう」。 tous は不定代名詞 tout の複数形で「すべての人々、みんな、全員」。 auront disparu は disparaître の前未来形(「今日の表現」を参照)。
②de dessus la scène 「舞台の上から」。de dessus 「~の上から」。
◎Explication de texte
今回のラ・ブリュイエールのテクストでは、世界や宮廷を「劇場」と見立てています。
世界は劇場で人間は役者だとするのは、古代から続く伝統的なイメージ です。
世界を「大きな劇場」と比べる ≪Theatrum mundi≫(世界劇場)ですね。「世界劇場」のイメージは、バロック時代の文学でもとても重要な主題でした。シェイクスピアにもあります。
テクストの音の響きにも注目してください。古典悲劇などに見られる12 音節のアレクサンドラン形式で始まり、続く2行目≪ ce sera ≫ から 3行目 « ce ne seront plus ≫ に至る部分も均斉の取れた音律構造で語られます。
*アレクサンドラン形式:フランス詩・韻文で特に古典的な格調を持つものとして用いられる韻律法のこと。
しかし3行目の文は否定文で、意味は肯定から否定へと急転しています。
音の均衡が意味上の対比、落差を際立たせています。
テクストの後半は4行目 ≪Tout≫ から最後までです。
後半では≪ Tout ce qui... ce qui ≫の先行詞≪ce≫に注目しましょう。
動詞「喜ぶ」≪ se réjouir≫や、「悲しむ」 ≪ s'attrister ≫、「絶望する」 « se désespérer » の主語は、感情を抱く、具体的な人格を持った人のはずですが、ここでは通常はものを表す≪ce≫が主語になっています。
フランス語でこれをchosification と言いますが、人格を持たない「ものを表す ce」が主語になることで、宮廷社会の人間性の喪失が暗示されているのです。
chose「もの」ということばの入った概念で、日本語に訳せば「モノ化」といえるでしょうか。人が人を「ひと」ではなく「もの」として扱う状況のことをいいます。
このテクストでは、最初の文(テクスト前半)で世界の永続性と対比される人間の儚さが描かれています。続く第2文(テクスト後半)では、この虚無感をより強調するためなのか、時間の流れがどんどん加速されている印象があります。
ラ・ブリュイエールは、宮廷という巨大な世界と、その中で、ただ他者の評価に翻弄されるのみの虚ろな宮廷人の世界を、豪華な舞台と影のように生きる役者の人生との対比として描いています。
それを笑うべき喜劇と名づけるべきか、哀しむべき悲劇と名づけるべきか、ラ・ブリュイエールは明らかにしてはいません。
☆今日のレッスンでは「世界は劇場で人間は役者だ」という比喩について、古代から中世を経て近世のヨーロッパに流れ込んだ伝統的なイメージとの説明がありました。世界を大きな劇場ととらえるイメージは、バロック時代の文学ではとても重要な主題だったようです。「All the world’s a stage And all the men and women merely players.」こちらはシェイクスピア「お気に召すまま」の一節で「この世は舞台であり、人は皆役者なのだ」という意味ですが、ラ・ブリュイエールはこの常套句をアレンジしたのだそうです。
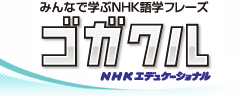





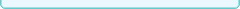
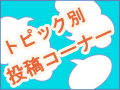






AIが台頭し、未来の主役が人から機械に変わったら、この言葉は消えてしまうのかな...などと漠然と思って、ちょっと不安になってきました。
その様に思ったことありませんでした。
役者の方はどの様に思っているのでしょうね。
世界は舞台、人間は役者、という言葉はどこかで聞いたことがあり、私も納得した言葉です。
今活躍している方々を見るとそんな感じもします。
自分はどうかな?
時には役者になって演じてみるものいいですね。
シェイクスピアの生誕450年にイギリスに行った時のことを思い出しました。
Theatrum mundi とても、興味深いです。
ラ・ブリュイエールの著書『カラクテール』和訳: 『人さまざま』を読みたいです。
Merci mille fois