 みなさん、10月からスタートしたテレビ講座の みなさん、10月からスタートしたテレビ講座の
「3か月トピック英会話」をご覧になっていますか?
タイトルは「ハートで話そう!マジカル英語塾」で、講師は
大西 泰斗先生。今期の講座は「ハートで感じる」シリーズの第3弾です。
実は、今回初めて番組をじっくり拝見させていただきました。
テンポよく耳に入ってくる明快な解説がとても心地いいですね( ̄▽ ̄*)
指をパチン!と鳴らしながらのリズミカルなトークが楽しいです。
この番組のテキストにはわかりやすいイラストや例文がたっぷり。
「ネイティブが持っている感覚的なイメージ」を知ることができます。
解説やコラムも充実しているので、気ままにパラパラとながめている
だけでも楽しいです。
以下は先生が書かれていたコメントです。
----------------------------------------------------------------------
●大事なのは単語単位で並べるのではなく ブロック全体をまとめて扱う意識
●それを意識して例文を何度も読んで「ブロックの操作」ができるようになると
「読む力」も「聴解力」も一気にあがる
----------------------------------------------------------------------
その通りだなあと実感しています。
私がかじっている多言語も最初は「意味不明のカタマリ」でしたが、
ブロックに区切ることが少しずつできるようになると、
だんだん意味が取れるようになってきました。
この番組を見ている時にいつも、「他の言語にも当てはまる部分があるなぁ~」
と感じています。もちろんブロックをならべていく順番は、ドイツ語や
フランス語など言語によってそれぞれ違います。
でも、伝えたい内容の「核」の部分に、説明するブロックをプラスして
文を作っていく感覚は、似ているなーと感じるのです。
とても興味深いので、これからのレッスンも楽しみです( ̄▽ ̄)♪
この番組のフレーズ集を作りました。手軽におさらいできて便利です。
●フレーズ集「 ハートで話そう!マジカル英語塾 」
----------------------------------------------
↓自分の語学メモ。いろんな国の文字が見れます。
[まんが・フォト]ほかの国のコトバ8
http://gogakuru.exblog.jp/ | 









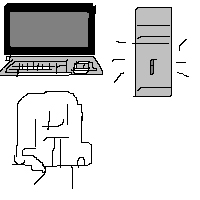
 みなさん、10月からスタートしたテレビ講座の
みなさん、10月からスタートしたテレビ講座の
