
2014年2月19日 (水)
無料語学学習アプリDuolingo 今月の頭にここでも紹介した、無料の語学学習アプリ「Duolingo」ですが、1月10日から使い始めて一ヶ月と少しが経過しました。 英語をベースにして学習できる言語は、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語そしてポルトガル語の5つ。私はもちろん、週に一度の教室と宿題以外ではなかなか毎日の学習ができていない、ドイツ語選んでスタートしました。 始めた頃は、1日2日と触らないで済ませることも多かったのですが、このアプリとにかくしつこいのです。 iPadを使っていると、アプリからメッセージが表示され、1日触らずにいると「やってないよ」、続けていると「その調子」と、とにかくほっといてくれません。アプリのメッセージとは別に電子メールも届きますから、下手をするといつもフクロウに見張られているかのよう。 でも、根が怠け者なのでなんでも「明日やればいいや」と先延ばしにしがちな私にとっては、このくらいの刺激があってちょうど良いくらいです。 それが証拠に、最近ではほぼ毎日アプリを使うようになってきています。 継続させるうまいしかけ 私でも継続できるのには、やはりそれなりの秘密があります。 まずひとつは、上述したフクロウからのメッセージの存在です。ちょっと油断していると叱られるので、「わ、やらなくちゃ」と思い出せるのですね。 先日などは、お風呂に入りながらYouTubeで音楽を聴いていて(iPad miniを防水ケースに)、さて、そろそろ上がろうかと思っていた矢先にフクロウからのメール。あわててその場で学習スタート。 ふたつめのしかけは、やはり携帯電話やタブレットのアプリがメインだということ(PCで使えるWEB版ももちろんあるようです。私は全く使っていないのですが)です。 これだと、仕事中とか人と話している時でもない限り、すぐにその場で学習が開始できるので、後回しにしないで済むのです。私の場合、文字入力が楽なのでほとんどの場合はiPadを使いますが、スマートフォンでもそれほど使いにくい、ということもありません。 みっつめは、これも学習の場所を選ばないよう、マイクに向かって発音する問題はオフにすることもできます。 自宅で以外の場所、通勤電車内や喫茶店などでも、マイク機能をオフにすれば音声自体はイヤホンで聞きながら学習を進められます。まさにいつでもどこでも。 自室の机でないと学習できないのでは、かなり勤勉な人だって毎日続けるのは難しいでしょう。 5週間でレベルは6に このアプリでは、学習を進めるにしたがってポイントが蓄積されていき、レベルが上がります。ちょっとRPGっぽい。 5週間を終えたところでレベルは6、次の7まではもうすぐのようです。ポイントは学習量を表すので、これが設定した学習ページにきちんと乗っているかどうかをチェックする目安となるのです。 あわせて、各単元を終えるとルビーが与えられ、これは各単元を終了するための不正解の限度数を一回ぶん緩和してくれるポーションやらに引き換えできます。遊びの要素が邪魔にならない程度に入っているのも悪くありません。 学習ペースは各自が設定できるのですが、標準の「毎日10分」にしておくと、概ね毎日一単元ずつのペースで進めれば良い感じ。実際には5~7分くらいの学習時間になります。 このペースは5分、10分、20分そして30分と設定できますし、メールやアプリのメッセージによるチェック機能もオフにできるので、意思が強くてフクロウからのメールなんか邪魔なだけ、という場合には受け取らないようにもできます。 この程度の適度な負荷なのと、毎日届くメールがあって、しかも思い立ったらその場で(お風呂の中でも!)学習できるところが、このアプリがうまくできているところでしょう。 問題があるとすれば、学習者の言語が英語であることが前提(ドイツ語などの各言語から英語を学ぶこともできます)なので、レッスンが進むに連れて対応する英語の難易度も高まっていくこと。どこかで自分の英語力を超えてしまうポイントがやってくると、学習どころか二重苦になってしまいます。 でもまあ、中級程度の英語力があれば、そう心配もいらないでしょう。なんといっても無料ですから、いちど試してみて、損はないと思います。 |

2014年2月 1日 (土)
無料サービス花盛り 語学学習に限らず、SNSやオンラインのストレージ、写真やビデオの共有など、私たちは非常にたくさんの「無料で提供されるサービス」を使っています。 あまりにも便利なものが提供されるものだから、何かのサービスにお金がかかるとなると、たとえそれが数百円であってもすごく割高な気がしてしまいますね。これではデフレから抜け出せないのも仕方がないのかも。 とはいえ、たとえ有料サービスの試用程度であっても、新しいサービスを無料で使い始められるのはありがたいものです。買ったはいいけれど使えないまま放置したもの、とくに語学教材、みなさんの自宅にもたくさん転がっていませんか? 今回私が試しているのは、なんと試用レベルではなく本当に無償のままで使い続けられる外国語学習サービス(アプリ)の「Duolingo」です。イメージとしては、よく書店の店頭などでデモ販売をしている黄色いパッケージの有名語学学習ソフトに似ていますね。これがなんと無料。 ただし日本語なし このサービスで学べるのは、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語とポルトガル語で、英語を使ってこれらの言語を学ぶほか、逆にこれらの言語を使って英語を学べます。日本語には現在のところ対応していません(後述する理由から、これは難しいと思われます)。 つまり、すでに英語(ないしは学習に使用する言葉)を多少は理解できる状態でないと使えないわけですが、少なくとも初級レベルではそう難しい表現が出てくるわけではありません。中学校程度までの英語力、英会話教室半年とか1年目くらいの状態でも十分に使えるのではないかと思われます。 たとえばドイツ語でいうと、「The man」は「Der Mann」といった基礎単語からスタートして、これでもかというくらい何度も類似の表現が繰り返して出題されます。 英語をドイツ語にする、そしてその逆、音声が流れて対応する英語を入力する、出題された単語に相当するものを選ぶ、マイクに向かって表示された単語やフレーズを実際に読む、といった非常にシンプルな訓練が繰り返されます。 学習は20問程度のセクションに細かく分かれていて、同じテーマでの単語や表現が繰り返されますから、記憶にも残りやすいでしょう。 この細かなセクションが2つから5つ程度、徐々に表現や単語の数を増やしながら繰り返され、一つのブロックになっています。ブロックにはたとえば「野菜」とか「動物」などの単語のグループであったり、「複数形」「形容詞」といった文法上のくくりになっていてこれらを順番にクリアしていくのです。 各セクションはせいぜい5分程度しか必要ないので、寝る前とか昼休みとか、ちょっとした時間があれば使えるのが良いところでしょう。 学習の進捗はクラウドに記録され同期できるので、自宅ではタブレット、外出先ではスマートホンで使っていても、常に最新の学習ステップから再開できます。これはクラウドサービスならではですね。 フクロウさんからのメッセージ 一つのセクションをクリアするには、間違いを3問以内におさえることが必要です。 今の所ベーシックな問題ばかりなので、間違うとするとTypoか勘違い(出題の英単語が複数形だったのを見落とすなど)ばかりですが、この先進んでいくとミスも増えそうです。でも、なにもペナルティはなくて同じセクションを繰り返せば良いだけ、気楽ですね。 私が使い始めたのは1月10日で、今のところ3週間強が経過しました。 このサービスでの学習ペースは、概ね毎日1セクションを終える程度に設定されているようで(毎日の学習ペースは設定画面で調整できます)、なんとかこのペースにはついて行っています。 とはいえ、1日2日と間が空いてしまったり、その結果学習ペースが遅れてしまうこともままあります。そんなときは、メールボックスに「Hi ⚪︎⚪︎⚪︎, keep the owl happy! Learning a language requires practice every day」とか「Hi ⚪︎⚪︎⚪︎, you are on a 3 day streak! Use Duolingo today to make it 4」といったメッセージが届きます。 Owlとあるのは、このサービスのキャラクターである緑色のフクロウのこと。 1日の遅れならばフクロウが出てきて「頑張れ!」で済むのですが、3日4日と遅れが出てくるとメラメラと燃えるカレンダーの絵が届いて学習を促されます。 スマートホンやタブレットで学習できる大きなメリットは、そのメッセージが届いたらその場で学習を再開できること。これが、わざわざPCに向かわなければならないとか、テキストや教材を鞄から出さなければならないのだったら、「また後で」となってしまいがちです。メールを読んだらすぐにアプリを切り替えて5分だけ集中すれば良いのですから、私のような継続力に欠け自分に甘い学習者には合っています。 日本語対応は さて、こんなに優れた、しかも無料の学習サービスがあるなら、ぜひ日本語でも学べるようになってほしいと思うのは当然ですね。 もちろん不可能ではないのでしょうが、特に現在は初級ステップにいることもあって、難しいだろうな、と思わされることも多いです。 たとえば、冠詞の存在です。 出題の中では、「A boy eats an apple.」と「The boy eats the apple.」とはきちんと別物として、それぞれ「Ein Junge isst einen Apfel.」「Der Junge isst den Apfel.」と回答しなければなりません。 さて、これをどう日本語にしましょうか? 学校での英語の授業風にやれば「ある少年がリンゴを食べる」「その少年がそのリンゴを食べる」などとできないことはありませんが、これって生きた日本語とはいえません。複数形でも同じような問題は生じますね。 現在対象とされている言語がドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガルであることからも理解できるとおり、今のところは英語と類似の文法構造を持つ言語間での学習サポートをするのが、このサービスの対象範囲ということになります。 同じヨーロッパの言語であっても、たとえばフィンランド語には冠詞が存在しませんから、対応させるのはそう簡単ではないと思われます。 そんなわけで、日本語対応ができるとしてもちょっと先になりそうですが、上述したとおり、少なくとも初球から中級の範囲では英語自体はそう難易度の高いものは出てきません。英語の訓練と同時にフランス語やスペイン語の基礎が学べると思えばむしろ一石二鳥。 全くの無償サービスで変な広告も出ません(どうやらサービスとしては利用者が入力する訳文を翻訳サービスに役立てる、というかたちで成り立っているもののようです)。一度試してみてはいかがでしょう。 |

2013年10月21日 (月)
網膜、なんて単語 「網膜」という言葉自体は知っていても、英語でなんというか、なんてまったく知りませんでした。そう、あのスマートフォンの発売までは。 2010年に発売されたiPhone4には、それまでの4倍もの高精細な液晶パネルが使われ、非常に細やかな表示ができるようになりました。Appleでは、肉眼ではそのピクセルを認識できないほどの高解像度ということで、このパネルに「Retina(=網膜)ディスプレイ」という名前をつけました。いや、命名が上手ですね。 その後、iPhoneだけでなく、ノートPCのMacBookやiPadにもこの「Retinaディスプレイ」が採用され、おそらく「Retina」という単語もすっかりおなじみとなりました。 最近では、スマートフォンの5インチ画面でフルHD(1920×1080)なんていうディスプレイも出現していて、この高解像度パネルはAppleの専売特許ではなくなっていますが、最初に世に出したこととキャッチーな名前をつけたおかげで未だに本家本元、というイメージがあります。 iPadで雑誌は読みにくかった 私は3年前にフィンランドへでかける直前、現地でPDFファイルのパンフレットやGoogleの地図などを使えれば便利だろう、ということでiPadを買っていきました。 ヘルシンキの市内ではかなりの場所で無料のWiFiが使えたこともあって、狙いはあたりました。これがあればガイドマップなんていらなくなるのではないかと思えるほど。 せっかく買ったのだから、と、定期購読している雑誌をデジタル版もセットになっている契約に切り替え、デジタル版よりはだいぶ遅れて届く紙の雑誌は(紙とデジタルのセットしかないのです)封も切らずに積んでおくようになりました。 デジタル版では調べたい単語があればなぞって選択して「Define(もしくは辞書)」というメニューを選ぶとその場で意味がわかるのも非常に快適です。紙の本や雑誌と電子辞書をとっかえひっかえしながら、なんて、もうやってられません。 とはいえ、私が買った初代のiPadの画面は「Retina」ではなく、1024×768ピクセルという、まあごく普通の解像度。 これでもちょっと前までのノートPCと同じではあるのですが、めに近いところで観ることの多いタブレットとしては少々ものたりないもので、しばらく画面を眺めていると目の疲れが感じられます。最近老眼が進んだこともあって、文字サイズが小さい表示では輪郭がぼやけてかなりつらいのです。やっぱり紙に印刷された雑誌は圧倒的に読みやすいことが実感できます。 ついにRetina 先日から、めでたくRetinaディスプレイを搭載した新しいiPad(とはいっても、今週にはさらに新型が登場するそうですが)を使えることに。 それではさっそく、ということでこれまで古い機種で読んでいた雑誌を表示させてみました。 目から鱗、とはこのことです。 これまで何となくぼんやりとしていて読みにくく感じていた文字が、輪郭をきれいに塗り直したかのようにくっきりと浮かび上がってきます。少々小さめの文字でも以前ほどつらくはありません。 単語をなぞって表示させられる辞書の表示は文字が本文よりさらに小さめなのですが、こちらもなんの問題もなく読めます。 実感できました。Retina(だけでなく他の機種のも含めて)ディスプレイがあってこそ、タブレットは雑誌を読むための媒体として実用的になったといえます。 おそらくこの先もさらなる高精細化は進むでしょうが、現在のディスプレイがようやく「紙の代替」としてのスタートラインに立ったと感じられますね。 電子書籍も昨年あたりから急速に立ち上がってきた感じではありますが、雑誌のデジタル化にはバックナンバーがたまらずに片付けもいらない、という大きなメリットがあります。もちろんその場で引ける辞書機能も魅力です。 これは、あっという間に紙の雑誌との逆転の日がやってくるかもしれないな、と感じますね。 |

2013年9月 5日 (木)
インフォグラフィックス って、聞き慣れないでしょうか? Informationの「インフォ」と「Graphics」ですから、情報を伝えやすく構成された図版のこと。雑誌の図版なんかがこれですね。 で、最近さまざまなインフォグラフィックスをWEBで観ることができます。文章で読むよりもずっと簡単に情報が伝わるものが多く、絵心のない私は感心しっぱなしです。 今回私が見かけて楽しんでいるのは、「The Best Infographics About Teaching & Learning English As A Second (or Third!) Language」というまとめ記事。 英語学習に関わる5つのインフォグラフィックスが紹介されているのですが、どれもとてもわかりやすくて、いっそのことこの調子で語学教材をつくってくれないかと思えるほどです。 最初の一枚には、「言語を学ぶ利点」として、「Travel」「Money」「Intelligence」そして「Love」という4つのカテゴリーで、それぞれけっこうバラ色のことが書いてあります。 これによると、バイリンガルになると旅行中楽だし、良い仕事に就けるし、賢くなってしかもセクシーなんだそうです。 本当かぁ? もっとも教材に使われる○○ 語学教材にはドラマや映画などがよく使われます。 英語の教材として最も多く使われるTVドラマは、「FRIENDS」なんだそうです。私の大好きな「Big Bang Theory」は第6位にランクイン。でも、あのドラマって英語で聞いても早口で、筋はわかるものの言葉遊びの部分はほとんどわからないですけどね。 映画はやはり「ハリー・ポッター」だそうです。続いて「タイタニック」「トイ・ストーリー」、そして「スター・ウォーズ」。 コミックは「スパイダーマン」「スーパーマン」「バットマン」の順庵ですが、これって人気コンテストの結果ともあまり変わらないんじゃないか、とも思えますね。 一方で、英語教師が多く使うTVドラマは「Mr.ビーン」が「FRIENDS」を抑えてトップ。 映画のトップは同じく「ハリー・ポッター」ですが、第2位に「ウォレスとグルミット」が入ってるところなんか、なかなかお目が高いです。 ロマンティックで健康で 英語を母語として話し人が選ぶ、もっともロマンティックな言語は「フランス語」だそうです。これはまあ、納得としても、第二位が「英語」なのはちょっと身びいきが過ぎますね。 続いて「イタリア語」「スペイン語」「アラビア語」と続くのですが、なんだか普段からふれられる言葉から「ドイツ語」だけが落とされましたって感じです。 魅力的な人が多い、英語圏の国の第一位はアメリカ。うーん、情報の信頼度がだんだん下がってきました(笑) そのほかにも、外国語を学ぶと健康にも良いとか、クリエイティブで良い仕事が得られるとか、ずいぶんとバラ色なことが書いてあります。 まあ、これを鵜呑みにしたってしょうがないんですが、ゴガク疲れのときに眺めていると、気分が良くなってきてやる気が戻るくらいの効果は、あるかもしれません。 |

2013年9月 1日 (日)
ネット「サーフィン」の終わり インターネットが家庭でも使えるようになってきたのは、1995〜1996年ころ。 当時はまだ日本語のWEBサイトなどほとんどなくて、英語のサイトやネットニュースなどを見て回れるだけのものでした。 その後、「Yahoo」「AitaVista」「Infoseek」といった検索エンジンが登場し、リンクからリンクへとたどりながら目当ての情報を探す「ネットサーフィン」という言葉も生まれましたね。WEBサイトの価値を高める要素のひとつが、良質な情報へのリンク集でした。20年も前の話ではないのに、もうだいぶ昔のように感じられます。 検索エンジンの乱立状態は、Googleの登場で終止符を打ち、21世紀に入ってからは他の検索エンジンを使うことも少なくなりました。 続いてweblog、いわゆる「ブログ」が普及し始めるのと同時に利用が進んだのが、RSSでした。ブログやニュースサイトが更新されると、その更新情報がRSSとして配信され、これを読むRSSリーダーを使っていれば、チェック対象にしているサイトの更新状況が一つの画面で簡単に把握でき、設定によっては記事まで読めてしまうというもの。 これで、「ホームページのリンク集」の役割はほぼなくなりましたね。 そしてスマートホンやタブレットの普及が進んだこの数年、RSSリーダーに代わって使われているのが、キュレーションサービスです。 ようするに、数多くのニュースサイトやブログなどから、ある特定のテーマに沿った記事を集めて読みやすく編集してくれる、いわばセミカスタムメイドのオンライン雑誌サービス。パー怒鳴るニュースなどとも呼ばれます。 具体的には「Flipboard」や「Zite」などのサービスです。日本だと「Gunosy」なんかも人気でしょうか。 わざわざリンクをたどりながら目的の情報を探すのではなく、編集された情報を雑誌のように眺めるだけ。ネットはようやく、紙やテレビなどのメディアに近づいてきた、といえるかもしれません。 自分でも作れるオンラインマガジン 以前から、気になるサイトやニュース記事を自分なりにピックアップしてブログなどで公開する人気サイトはありました。 しかし、こうしたサイトの運営って大変そうでした。紹介したいと考える記事のURLへのリンクと、内容の簡単な紹介を毎日のようにブログの記事として編集し、更新しなければなりません。となると、一日分の情報をためておいて一度か二度、更新ということになります。よほどの動機付けがなければつつきません。 今年の春先に「Flipboard」のアプリがアップデートされ、この個人選定の記事ピックアップが実に簡単にできるようになり、かなり状況は変わりました。 実際にタブレットやスマートホン(iOSとAndroidのアプリが公開中です)で使っていればおわかりと思いますが、読んでいる記事が気になったら、「+」ボタンを押すだけで自分の「雑誌」への登録ができます。PCも含めてWEBブラウザで見ている時でも、同じようにワンタッチで登録できるブックマークレットも公開済み。 こうして雑誌に登録しておけば、ソーシャルブックマークと同様に他の人たちと共有ができるだけでなく、自分があとで読み返すためにも使えます。 「英語&外国語 学習リソース集」 以前も紹介したとおり、私は外国語の学習について気になる記事をピックアップしたマイ・マガジン「英語&外国語 学習リソース集」を3月から作成・公開しています。 閲覧数とフリップ数(読者が何ページをめくって眺めたか)が把握できるのですが、今朝の段階で348人、15,379フリップでした。 どうやらこの閲覧数は一定期間の閲覧ユーザー数を移動合計で表示しているようなのですが(たぶん1週間単位くらいではないかと)、6月初旬に100を超えて一時期横ばいになり、8月15日過ぎからまた増え始めています。Flipboardの日本人ユーザーが増えてきているのでしょうか。 日本語の記事だけではつまらない(日本語だと、いつも同じような内容の「英語学習法」や「TOEIC対策のTIPS」、そして単語や表現集みたいなのばっかりですから)ので、半分程度は英語の記事も混ざっています。 私が短時間で読み、内容を理解できる程度の記事なので、おそらく英語中級程度で読める程度のもの、しかもあまり長文でないものを選んでいますので、リーディングの素材集としてもお使いいただけるんじゃないかと思います。 ときおりFlipboardで「英語」「語学」などで類似のマガジンを検索してみるのですが、いまの時点では、日本語で作成しているマガジンの中ではもっとも多くの読者数を獲得できているようです。 もっとも、この先いつまで続くかわかりませんし、新たなマガジンにあっという間に追い越されちゃうかもしれませんけどね。 |

2013年8月25日 (日)
長文の基準 みなさんはどのくらいの文章量から「長文」と感じますか? 例えばこのブログは長文でしょうか。 これは単純に長さだけの問題ではなく、書き手の力量にもよりますけどね。長くても飽きさせない文章はあるし、それほどの分量がなくても投げ出しがちなものもある。 ネットにつながるのがPCばかりだった頃と違って、携帯電話やスマートホンなどの比率が高まっているので、以前よりは長文と判断される閾値は下がってきているようにも感じられます。 そもそも、この「ゴガクル」もモバイル版のトップページだと、ゴガクルブログへのリンクが一切ありませんから、モバイル中心のユーザーはこのブログの存在すら知らないかもしれません。 私の実感だと、PCでもタブレットでも、3回以上スクロールする文章だと、「あ、ちゃんと読まないと」という印象ですね。長い、というよりも、読み方のモード切替が必要な分量、といえます。 スクロール2回くらいなら、字面を目で追いかけていればだいたい内容が把握できますが、それ以上だとちゃんと部分部分を理解していかないと、途中で筆者の設定したストーリーラインが見えなくなってしまいがち。 この私的基準は、不思議なことに日本語でも英語でもだいたい同じです。 長い=しんどい、ではないけど 長文だからといって理解するのが大変かといえば、そうでもありません。140文字の制限のあるtwitterに流れるつぶやきが理解しやすいかといえば、そんなこと一概にはいえませんね。 ある程度の長さがある文章のほうが、必要な情報をきちんと盛り込めますし、論理建てがしっかりしていれば理解はしやすいものです。 とはいえ、長い文章だと読むのに時間を要する、という問題もあります。 これが日本語ならばともかく、英語他の外国語で書かれている場合、余計に時間を必要としますね。雑誌1ページは日本語ならば5分10分でおつりがきますが、英語だとちょっとギリギリ(もちろん内容や英文の難易度によりますけど)。 語学学習はとにかく継続が大切、となると、長い文章を三日おきに読むくらいなら、短いものを毎日読んだほうが良さそうです。 こと、語学学習と情報収集を兼ねて外国語の文章を読むのなら、短くまとまった文章を意識して選ぶのもひとつの考え方です。 私のおすすめ 私がこの観点で読んでいるのが、「Harvard Business Review」が運営するサイトでほぼ毎日更新される、「The Management Tip」という連載です。 この連載が適している理由は次の3つ。 1)内容に関心がある 2)短いのでたとえば昼休みにサッと読める 3)毎日更新される 1)は何度も書きましたね。英語学習のためだからといっても、関心のないテーマについて毎日英文を読み続けることなんて、そうは続きません。 私も一応は会社員であり、マネージャでもありますし、もともと経営学科を卒業もしていますから、「Harvard Business Review」の掲載記事のほとんどは関心の対象です。 2)についても、この連載は日によって多少の差はありますが、10行以内程度。 慣れてくれば5分10分で読み終えられます。きちんと日本語に訳しながら読んでも30分はかからないでしょう。 これならば、始業前や昼休み、あるいは通勤電車の中でもサッと読めますね。隙間時間が有効活用できたようで、気分も良くなります。 3)も大事です。 関心のある、適度な長さの文章を毎日探していたのでは、時間が無駄です。毎日更新されるということは、一定時間毎にアクセスすれば必ず新しい文章に出会えるわけですから、いちいち検索したり誰かに情報を求めたりする必要がありません。 会話に場数が必要であるように、読解力も量をこなさなければ向上しません。それも、ラクに読めるレベルだけではなく、多少がんばって読む対象が必要です(多少、のレベルをきちんと把握しましょう)。 短いからこそ続けられる、こういった情報源、ぜひ探してみましょう。 |

2013年8月22日 (木)
継続は力って、わかってるけど... 外国語の学習においては、「継続は力なり」は絶対の真実であると断言してかまわないでしょう。毎日短時間でも継続している人のほうが、たまに集中して長時間学ぶ人よりも、必ず遠くまでたどり着けます。 しかも、毎日10分20分の時間が捻出できないほど忙しい人というのは、そうはいません。1時間は無理でも、10分なら必ずあります。なので、「そんなの無理です」とはいえない。 でもねえ、やっぱりその10分の捻出ができないのが悲しい現実です。 その時間がないワケじゃなく、なんとなくボーッとしたい、スマートホンやPCで面白そうな動画を見つけちゃった、ツイッターに書き込んでたらついつい時間を忘れて...そんなもんです。 自律の不足だといわれればそれまでだし、「その程度の気持ちしかもってないんじゃ、無理だよ」と指弾されても認めるしかないのですが、でも、そんなものでしょう。 好きなことなら 学習の目的にもよりますが、関心のない教材や素材がいくらあっても、毎日どころか一日だって続けられません。 日本語だって一緒ですよね。「本を読まなきゃ」なんて思っていても、興味のない本を義務感で読んだって面白くないし、内容も頭に入ってこないので時間の無駄です。 外国語だって同じ。たとえば私はハリウッドスターの私生活になんか一切興味がないので、その手のブログやらゴシップ記事ばかり読まされたら、ものの3分で投げ出すでしょう。 なので、やっぱり好きなこと、多少の苦労は苦労じゃなくなるくらい関心のあることに集中するのが良いんじゃないかと。 あるいは、「まあ好き」くらいでかまわないので、そこで話題になっていることについてそこそこ知識なり経験があって、内容を理解しやすいものなんかも、良いですね。 たとえば、あのポップコーンについて たとえば、このニュースサイトの記事なんか、どうでしょう。 "What are the best snacks at the Tokyo Disney theme parks?"(http://www.themeparkinsider.com/flume/201308/3611/) タイトルでおわかりですね。みんな大好き東京ディズニーリゾートのスナックに関する記事です。スクロールすると長いですが、大丈夫、見慣れた風景や食べたことのあるあのスナックの写真がたくさんあるからで、文章量はそれほどでもありません。 これなら、パラグラフ単位で何度かにわけながらでも、読み進められますよね。 Google検索だけでなく、さまざまなニュースやブログから特定テーマの記事を集めてくれる、キュレーションサービスが増えてきています。自分の関心にあった記事が、しかも毎日配信されているので、なかから気になったものをピックアップして読むだけ。イマイチ乗れなかったら次の記事。 これなら、電車に乗って通勤や移動の間の10分間を学習タイムにできます。ツイッターやLINE(使ってないのでどんなもんだか知りませんが...)はちょっと我慢。ほんの10分、メッセージへの返事が遅れたからって、友達は減りゃしません。 |

2013年8月15日 (木)
翻訳ソフトウェアの進化 つい9年前、会社の研修で米国の大学での短期授業を受けた際に、一緒に渡米した同僚が使っていた自動翻訳ソフトは、正直なところ実用には程遠いものでした。 一週間の授業の最後に行うプレゼン資料は英語でなければならなかったので、日本語を手っ取り早く英語にする手段として使っていたのですが、そもそも「英語に直すことを前提としてない」日本語を、自動翻訳にかけてみてもまともな英文は出てきません。結局、通訳の方がフォローすることにして、説明は日本語でも可、というはなはだ中途半端な発表となりました。 このときは、私もまだ英会話教室に行き始めてようやく2年が過ぎたところで、英会話が何とかなる状態ではありません。もちろん、課題のプレゼン資料を英語で作成することなんてとても独力ではできなかったので、同じように自動翻訳を使いました。 注意するのは、主語述語の明確な、そして文と文とをつなぐ接続詞をきちんと使った日本語を書くことです。これで、あとの作業はかなり楽になります。 そのままでは使えないことはわかっていましたので、出てきた英文を最初からきちんと英語として読んでみる、というのがポイントです。日本人にとってもなんとなく不自然な言い回しや、やたらに難しい単語があれば、そこをアナログ式に手直しします。同じ単語や表現が続く場合にも、言い換え語がないかを確認。時間はかかりましたが、それなりに格好はつきました。 日進月歩のIT技術にとって9年というのはものすごく長いもので、今では手のひらに収まる携帯電話で、当時の翻訳をはるかに上回る実用性のある訳文が得られるようになりました。 しかも、今では数十の言語を相互に自動翻訳可能。このまま行けば、すぐにもSF映画でおなじみの翻訳装置が完成しそうな勢いです。もしかしたら、これから生まれてくる子供達には語学学習なんて不要になるかも? そうはうまくいかない いやいや、そうはうまくいきませんよね。 自動翻訳の精度が上がってきたとはいっても、現状では「とりあえず何が書いてあるかを理解する手助け」になるレベルです。 同じように未知の言語からの翻訳でも、日本語がわけがわからないのに対して、英語のほうはそれなりに理解のできる文章になっている、ということも多いですね。 Google翻訳は旅行中も大変便利に使っていますが、ダイレクトに日本語になおしても意味がわかるとは限らず、英語に訳してその英語を理解したほうが、正確に意味を把握できることが多いというのは、みなさん経験済みじゃないでしょうか。 また、たとえばドイツ語から日本語にした場合と、一度英語にしてから再度日本語に直した結果とが一致するケースがあるところをみると、そもそも各言語から日本語に翻訳しているのではなく、一度中間で英語を介在しているようにも思われます。 それならば、万能の仲介役である英語を理解できたほうが、現状では自動翻訳を効率良く使える、といえそうです。 やっぱり英語 日本人とフランス人とフィンランド人が話すのに、それぞれの言葉を理解できるように学ぶのは非現実的です。実際には、三人とも習得可能な一つの言語を選び、共通言語として使うことにするのが手っ取り早い解決策です。 で、その共通の言語が、今は(多分これからしばらくの間も)英語である、ということです。 これは、人と人とのコミュニケーションだけでなく、機械による言語変換でも同じだということでしょう。自動翻訳技術は各言語と英語との部分に開発を集中させれば、効率的に実用化が可能です。 日本語とドイツ語、フランス語、スペイン語...と延々と作り続けるのは、とても非効率です。 となると、仲介役である英語をダイレクトに理解できれば、コミュニケーションがより上手にできるようになる、という状況は、当面は変わらなそう。 むしろ、英語以外の言葉を学ぶ理由は、その言葉が使われる地域の文化や生活、人々によほどの興味がなければ、必要性とか効率性とは無縁の行為、となってしまいそうです。 なんだか、ドイツ語学習者としては気分の悪い結論なんですけどね。 |

2013年8月 3日 (土)
分厚いガイドブックは もういらない...とまでは言い切れないのですが、今回、ミュンヘンに四泊、エクスアンプロヴァンスに五泊の旅行を通じて、ガイドブックを持ち歩く必要は、ほぼありませんでした。 では、スマホ(Galaxy Note)やタブレット(iPad mini)でマップアプリを使いまくっていたのかというと、実はそうでもありません。結局使ったのは、前者ではガイドブックから切り離した市内地図、後者ではツーリストセンターで無料配布していたガイドマップ。これで十分。 ガイドブックは、あちこち行きたい場所やお店を事前にチェックしておき、渡り歩く旅には便利だと思います。 けれど、私の場合はあまり買い物好きでもないし、名所を順番に経巡るような歩き方もしません。なんとなく気の向くままに散歩しながら、気に入った場所があれば写真を撮り、目についたお店を冷やかす程度。マップで確認するのは、今自分がどこにいるのかということと、今晩のビールはどこで飲もうか、と考える時くらい。 マップアプリを使わなかった理由のもう一つが、スマホ内蔵のGPSの精度の低さでした。しばらく使っていても、自分が実際にいる場所とはかなりずれた位置しか示してくれず、これでは当てにありません。 普段東京で歩いている分には、多少の狂いがあっても修正しながら使えるのですが、初めて訪れた場所では邪魔になるだけです。それに、あまり画面に気を取られて歩いていると危険ですし。 辞書とGoogle翻訳 辞書はもちろん大変便利に使いました。何といっても活躍するのは、レストランなどで得体のしれないメニューを見つけた時、それが一体どんなものかを想像するとき。 だいたいこういう場合には食材や調理法を示す単語の意味がわからないので、その場で調べて確認します。もっとも、こういう時にお店に人にどんどんと質問してしまう積極的な人も多いでしょうけど。私はどうもそういうのが苦手なので。 ドイツでは未知の単語も比較的少ないし、iPadにはオフラインで使える辞書もインストールしてあったのですが、フランスでは少々使い勝手が落ちました。迷った挙句、辞書アプリは購入せずに渡航したので、使えるのはオンライン状態でないと利用できない、無料のGoogle翻訳だったので。 旅行中は、スマホのローミング契約はして行かずに、空港で受け渡しのできWiFiルーターをレンタルして行きましたのでネット回線はありました。ただ、バッテリーの持続時間に不安があったので頻繁に電源を切り替えていたために使い勝手はどうしても低下しました。 注)あるWiFiルーターのレンタル業者が、今年の四月に大規模な情報流出事件を起こし、さらには流出についての公表が大きく遅れたという事件がありました(ちなみに、被害者への対応は「自社レンタルサービスの割引」のみ)。私も被害者の一人で、おかげでカードを再発行しています(不正利用が一件取り消された形跡もありました)。もしお使いになるのであれば、この件を確認の上で、安心のできる業者を選ぶことをオススメします。 それでも、Android版のGoogle翻訳に搭載されている、カメラとの連携機能はとても便利。 メニューの該当部分をパチリと写して、翻訳させたい部分をなぞるだけですぐに訳語が表示されます。フランス語からダイレクトに日本語にすると、時折意味の通じないことがあるので、ほとんどフランス語から英語への自動翻訳で済ませました。料理なんかはだいたいわかるもんです。 意外に使わなかったのは ミュンヘンについては、市内の地下鉄(SバーンとUバーンがありますが)の運行状況をリアルタイム表示してくれるアプリがあって、「これは便利そうだ」と入れて行ったのですが、実際には使いませんでした。中心部では次から次へと電車がやってくるので、方向さえ気をつければアプリで何かを確認する必要などなかったのです。 同様に、上述のようにWiFiルーターを借りて行ったので、市内の無料WiFiスポットを検索するアプリも、一度か二度使っただけでした。 エクスアンプロヴァンスについては、市内のガイドブックアプリを持って行ったのですが、こちらも結構狭い街とあって、必要ありませんでした。半日も歩き回っていれば、概ねどこに何があるかが把握できてしまいます。 こうなれば、大まかな紙のマップさえあれば何とでもなってしまうのですね。 旅行の初日くらいは、せっかくなのでビジュアル旅行記でも作ろうかと、iPadでも写真を撮り、写真やフリーハンドの図形、文字等をレイアウトできる便利なアプリにあれこれ書きつけていました。 こちらも、本格的にあちこちを歩き始めると、いちいちカメラの他にiPadでの撮影が面倒になってしまい、あっという間にやめてしまいました。もともとマメなほうではないので、これはまあ予想通り。 一方で、妻は毎日の行動を結構細かく記録に残していたみたいです。まだ読ませてもらっていませんけど。 |

2013年7月 6日 (土)
私の目標 何度か書いたかもしれませんが、私が外国語を話せるように(また読み書きできるように)なりたい理由のひとつが、「世界中でビールが飲めるようになりたい」ことです。 ビールくらい、英語で頼めばだいたいのところで出てくるんですが、せっかくだからその土地のビールを、その土地のお店で、その土地の言葉で頼んで飲みたいじゃないですか。 お酒は至るところにあり(もちろん、宗教上の理由で飲めない場所も多いですが)、その土地の文化や歴史が生きています。 ビールと書きましたが、これはもちろんワインでも、その他のお酒でもOK。旅先で地元のお酒と地元のお料理とをいただく幸せに勝るものが、そうそうありましょうか。 そんなわけで、私はまだチェコ語は全く勉強していませんが、「Pivo, Prosím!」だけは知ってます。ホントは今年はプラハでビール、のつもりだったんですが。 ビール注文フレーズ集アプリ 先日、便利なiPadアプリは何かないかなと探していると、まるで私のためにつくられたかのようなものに出会いました。 その名も、「Pivo」。チェコ語で「ビール」。 「Beer」でも「Bier」でもなく、チェコ語であるところに作者のビール愛が、感じられます(ビール党には解説不要でしょうが、いま世界中で愛されている、黄金色のピルスナーは、チェコが発祥)。 このアプリ、なんと59もの言葉でビール注文フレーズが調べられて、かなり多くの言葉ではそれぞれのネイティブスピーカーによるビデオが見られます。 発音の助けとして、英語話者に読みやすい発音ガイドが併記されているので、ビデオがなくてもなんとなく読むことができます。キリル文字でも問題なし。 また、最近日本に上陸して話題となったニュースサイト「Huffinton Post」の本家では、「How To Drink When You're Abroad」という記事が掲載されています。 19の国々でのビール注文フレーズ、乾杯の言葉と、飲酒の際の習慣や特長がまとめられていて、これまた便利。乾杯フレーズは、上記のアプリでもほしいところですよね。 ちなみに、日本では「手酌はダメ、隣の人に注いであげて、お返しに注いでくれるのを待ちましょう」だって。うーん、これはどうかなあ。 もし居酒屋のカウンターで突然隣に座った外国人観光客がビールをお酌してくれたら、きっとこの記事のせいです。 |

2013年6月22日 (土)
「Phablet」ってなーんだ? さて問題です、「Phablet」ってなんでしょう? どれどれ、と辞書を調べても、この単語はおそらく載っていません。なぜなら、ここ1,2年に新たに使われ始めた新語だから。英和辞典に掲載されるとしても、もうしばらく先になるでしょう。 そういえば、「tweet」や「retweet」が、辞書に載るようになった、というニュースが最近流れましたっけ。 最近では、なにかわからない言葉があると、辞書ではなくoogle先生に質問する人がほとんどでしょうから、この単語も調べればすぐにわかります。 私の環境だと、最初に出てくるのは英語版のWikipediaの項へのリンクで、次のように定義されています。
ファブレットとは、5〜6.9インチのスクリーンをもつスマートホンの一種で、スマートホンとタブレットの機能を併せ持つことで二つの機器を同時に持ち歩く必要がなくなる。 でもよくわからない さて、普段からスマートホンなどのデジタル機器の動向に敏感な人ならばともかく、「スマートホンって、iPhoneとは違うの?」くらいに横目で眺めていると、上記の定義を見ても、それがいったい何なのかを具体的にイメージすることは難しいでしょう。 これだけだと、「そんなのたまにニュースや雑誌を見てりゃ、わかるはず」なんていう意見も出そうですから、別の例を出しましょう。 第二問です。「Eintopf」ってどんな料理でしょうか? 読み方は「アイントプフ」、直訳すると「一つの鍋」です。ドイツ語であることと、この意味を見れば、おそらくヨーロッパの料理に関心のある人であれば、「ああ、あれか」とおわかりではないかと。 でも、スマートホンやタブレットの最新情報を日々チェックしていても、アイントプフなんて食べたことはおろか、聞いたことさえない、というかたも多いのではないでしょうか。 ちなみに、同じくWikipediaでの亭語は、以下の通りです。
アイントプフは、ドイツの伝統的なシチューで、非常に多くの材料が用いられる。実際のところ、この名称はすべての具材を一つの鍋で煮るという調理方法を示しており、特定のレシピを指すものではない。 まあ、何となくわかったような、でも、日本の鍋物だってそうだよね...というところではないでしょうか。 そこで画像検索 私が、こうした目新しい言葉の具体的なイメージをつかむために多用しているのが、Google検索です。 ただし、普通に検索するのではなく「画像検索」を使います。Googleでの検索結果を表示する画面の上部には、検索語を入力するボックスのすぐ下あたりに「ウェブ 画像 地図...」と検索の範囲を切り替えるためのメニューが並んでいます。 ここで、「画像」をクリックしてみてください。 「Eintopf」で画像検索すると、ほら、おいしそうな料理の写真が並んでいますよね。これを見ると、たしかにさまざまなレシピがあることがわかります。 これなら、「そういえば、似たようなのを食べたことがある」と思い出せるのではないかと思います。普段から料理をしているかたであれば、これらの写真を見ただけでも自己流アイントプフをつくることだってできるでしょう。 時間があったら、「Phablet」でも同じように画像検索をしてみてください。 写真を見れば一目瞭然、スマートホンではあるけれど、液晶画面が非常に大きくて「iPad」のようなタブレット代わりにも使いやすくつくられたものだということが直感的に理解できます。 この画像検索のおかげで、海外の文化についても文章だけで想像するより、遥かに簡単に具体的なイメージをつかむことができます。 旅行ガイドブックで見られる写真には限りがありますが、これなら数多くの写真や、場合によってはビデオからより多くの情報が得られますね。かつては考えられなかったほどに便利です。 こういうことで喜んでいると、「そんなやり方では想像力が育たない」などとお叱りを受けそうですが、さてどんなもんでしょうか。 少なくとも私は、子供のころ「真っ赤なあまいぶどう酒」とか「豚の塩漬け肉」なんていう文字を見て、「きっとおいしいんだろうなあ」とは思いましたが、それ以上の想像なんてなかなかできませんでした。 あまり堅いことをいわず、より多くの文化に気軽に触れられるようになったことを、ポジティブに考えたほうが、きっと人生幸せだと、私は思います。 |

2013年6月16日 (日)
ニュースを読む 外国語の学習で、「読み書き」は「会話」に比べると重視されなくなっている印象を受けます。 たしかに、研究者や技術者、海外の情報を頻繁に扱う専門職などに就いていなければ、外国語で本や論文を読む必要のある場面は限られるでしょう。 けれど、旅行で使えればよい、としても、さまざまな施設の表示や各種のパンフレットなど、外国語を「読まねばならない」場面はゼロではありません。短く単純な文であれば、短時間で大意を把握できることはけっこう重要です。 幸いにして、「短く、シンプルで、必要以上に修辞的でない」文章が、私たちの周囲にはあふれかえっています。すなわち、ニュース記事がそれ。 長い論説もありますが、だいたいは十数行から数十行くらいの分量ですから、慣れた外国語ならば10分ほど、学習中でも30分ほどで読み終えられます。しかも、世界的なニュースであれば母語でもその内容を把握できますから、背景知識を含めて理解をするのがより容易です。 アップル社の発表 6月11日、PCやモバイル機器を扱うニュースサイトやブログは、アップル社の発表に関連するニュースで埋め尽くされました。 iPhoneやiPad向けの新OS、バッテリーでの稼働時間が大幅に伸びたノートPC、そしてなんだか別のものにしか見えないワークステーションなど、この発表だけでどれほどの広告宣伝効果があったのかと感心するばかりです。 いくつかのサイトで発表内容を日本語で把握したあとで、今回は「Der Spiegel」誌のサイトでドイツ語のニュース記事を読んでみました。 こういうときには、いちいち辞書は引かずにとりあえず意味を取ってみることにしています。特に身についた語彙が不十分な言葉の場合、読んでる時間よりも辞書を引く時間のほうが長くなってしまっては、苦行になってしまいます。 当然、未知の単語が次々に登場するのですが、基本的に書いてある内容はすでに理解しているので(同じ発表にもとづいた記事なので、ほとんど内容にはブレがありません)、何とか類推しつつ読み進められます。 おかげで、とりあえず最初から最後まで、10分程度で一度読み終えることができました。普通のニュースだったら、こうは行きません(ためしに、中央の洪水関連のニュースを読み始めましたが、20行くらいでイヤになっちゃいました)。 Die Bürosoftware さて、こうやって読んでみると、「あ、この言葉ではこんな風にいうのか」と、いまさらながらに気がつくことも少なくありません。 たとえば、今回のタイトルにした「Die Bürosoftware」という単語。「Büro」は事務所ですから、英語にすると「Office」、つまり、これはExcelなどに代表される「Office software」の意味です。 頭に「Die」がついているとおり、これは女性名詞。 「Büro + Software」による複合単語ですから、後ろのほうにある「Die Software」と性が一致して女性名詞となります。 ちなみにハードウェアのほうは「Die Hardware」。まんまですが、なぜ「Die Hartware」にならなかったんでしょうね? 辞書で引いてみると、「ハードディスク」も「Die Festplatte」の他に「Die Harddisk」と英語の綴りのまま入ってきているようです。 読み方は、同じ辞書によると「ゾフトヴェーア」だそうで、ここはきちんとドイツ語風です。 とはいえ、「Die Ware」は「ヴァーレ」になるので、本当なら「ゾフトヴァーレ」と読みたくなります。けれど、「Die Ware」は複数になると「Die Waren」なのに対して、「Die Software」は「Die Softwares」だそうなので、これはもう、外来語として新たにできた語だと考えるほうが、良さそうです。 ドイツ語の中にはフランス語からきた単語もけっこうあり、たとえば「Das Engagement」は「エンガゲメント」ではなく「アンガジェマーン」となります。 ちょっとややこしいですが、英語のように同じ「engage」を意味によって「アンガージュ」と読んだり「エンゲイジ」と読んだりする無節操さを考えると、たいした問題ではないですね。「resume」も、「レジュメ」「リジューム」の両方あるし。 |

2013年6月 6日 (木)
キュレーション オンラインのキュレーションサービス「Flipboard」については、何度か紹介しました。 今年になってから大きなバージョンアップがあり、その目玉は「マイ・マガジン」が作れるようになったことです。 これは、さまざまなオンラインの情報の中から気に入ったもの、気になったものを自分の「マガジン」に登録して公開できるというもの。いわば、「私のオススメコンテンツ集」が簡単に作れて共有できるサービス。 個人がWEBサイトを作り始めた頃、いかに「リンク集」を公開しているかが、そのサイトの魅力の一つとなっていた時期がありました。 また、WEBコンテンツのブックマークサービスでも、自分のブックマークを「アンテナ」として公開することができ、いわば「目利き」のアンテナを登録しておくことによって、情報探索を効率化する、という使い方ができました。 しかしこれらの場合、収集の対象となるのはサイト単位。例えば同じブログでも、記事のテーマによっては全く関心のない情報も通知されるので、必ずしも求めるタイプの情報かどうかはわかりませんでした。 キュレーションサービスは、基本的に個々の情報(ブログやニュースの個々の文章)単位で収集、分類されますから、概ね自分の求めるテーマや話題に沿った情報のみを集められるのが便利なところです。 私は、FlipboardやZiteなどのキュレーションサービスを使い始めてから、一からGoogle検索で情報を探すことがかなり減ってきましたし、ニュースサイトのトップページに最新記事を見に行くことも、ぐっと減りました。 キュレーションは「Curation」ですが、元になった「curate」は展示会などを企画する、という動詞であり、「curator」は博物館や美術館の学芸員を表します。 いわば、膨大なコレクションの中から、見学者の嗜好に合う展示品を選び、展示方法を考え、実行するというプロセスを、情報収集と整理に当てはめたサービスです。Ziteでは、開いて読んだ記事の傾向や、その際の評価結果に基づいて推奨される情報が変わるため、しばらく使っているうちに自分だけの嗜好に合った雑誌ができあがる、というわけです。 Flip it! 従来は、「どこかの目利き」が集めてきた情報を効率良く閲覧する道具だったFlipboardは、マイ・マガジンの導入によって、「自分なりに目利きをする」ための道具に進化しました。 各記事にはマイ・マガジンへの登録ボタンがつけられ、読んでいて気に入ったらその場で自分が作ったマガジンに簡単に登録できます。マガジンは複数作れるので、テーマ別に分類するのも簡単。あとで読むためのメモとして使っても良いし(自分だけが見られる設定も可能)、公開してももちろんOK。 2ヶ月ほど前に、私も「英語&外国語 学習リソース集」というマガジンを作り、語学学習関連で気になった情報を集め始めました。 今日現在、80ほどの記事をクリップして、閲覧者もようやく100人を超えました。すでに数千人以上の読者を持つ「マイ・マガジン」もあるようですから、100人を超えたくらいでは弱小もいいところですが、それでも自分が集めた記事集がこれだけの人たちに見てもらえて、もしかしたら数人のかたには情報源として使ってもらえているかもしれないというのは、嬉しいもんです。 もし、興味を持たれましたら、一度覗いてみてください。 |

2013年6月 2日 (日)
辞書してのWikipedia 前に一度書きました。オンラインの百科事典サイト「Wikipedia」は、特定の言葉や出来事を他の言語でどういうのかを調べるときに、とても便利です。 つい先日のドイツ語教室でも、ドイツで使われるパンの材料のひとつ「Dinkel」が出てきたのですが、この単語は手許のアクセス独和辞典(iPad版)には載っていません。 また、同じくiPadに入れてある独独辞典(Langenscheidet Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache)には項はあるものの、「eine Getreideart」すなわち「穀物の一種」としか記載されていないのです。 そこで、Wikipediaのドイツ語版で、「Dinkel」を表示させてみます。ページの左下に、各国語での同じ項目へのリンクが並んでいるはずです。 残念ながら、日本語のWikipediaにはこの項目はないようです。けれど、ほとんどの場合、英語版へのリンクはありますから、こちらをチェック。すると、「Spelt」という項目に飛びます。 料理好きならきっと「スペルト小麦」にすぐ結びつくのでしょう。私の場合は、さらに英和辞書で調べて確認しました。 ついでに日本語で「スペルト小麦」を調べてみると、国内の製粉会社による詳しい説明あって、「現在の普通小麦の原種にあたる小麦で、栽培は古代エジプトで始まり...」との説明が。 うーん、「古代エジプト」なんて、素敵すぎます。これは食べてみなくちゃ、という気になりますよね(え、なりませんか?) ぴったりのアプリが さて、このようにWikipediaを辞書代わりにするのはけっこう便利です。辞書にまだ掲載されない時事用語なんかもけっこう簡単に調べられますからね。 ただ、実際にやろうとすると意外に面倒です。 1)調べたい言語でWikipediaのサイトを開く 2)目的の語を入力して検索 3)複数項があったら目的に合致したものを選択 4)ページ左下の各国語版へのリンクから日本語を探す、あれば飛ぶ 5)なければ自分がわかる言語へ飛び、必要に応じて辞書で再度調べる というステップを踏まねばなりません。 PCで作業できる場合はともかく、スマートフォンやタブレットの画面だと、いかにも面倒ですよね。 世の中便利なもので、こんな用途にぴったりのアプリ(ただし、iOSだけのようです)があります。その名は「Translatica」。 一発多言語検索 このアプリは、要するになんらかの語を検索すると、各言語のWikipediaに掲載されている同じ項目へのリンクを抽出して一覧にしてくれるもの。 もとの検索の言語も自由に選べますから、今回の場合ならばまず「Deutsch」を選んで「Dinkel」を検索。すると、「English」から「中文」まで9つの言語へのリンクが並びます。それぞれをクリックすると、「Copy」か「View Article」が選べるので、好きなほうを選べばOK。 インストールした状態では、最初の言語選択に20ばかりのリストがあって日本語が次のページになってしまいますが、これは編集可能。編集画面ではこんなにも多くの言語でWikipediaがあるのかと、驚かされます。 ここで学習中の言語、あるいは旅先の言語などを登録しておけば、あとは辞書と同じように検索するだけ。 もとがWikipediaの情報なので、辞書と同じというわけにはいかないでしょうが、上述の通り辞書には出ていない語が多く含まれるのがポイント。 この便利なアプリ、有料とはいえたったの85円。最近の円安傾向で、いつiTunesストアの日本向け価格が改定されるかわかりませんし、いずれにせよ缶ジュースにも満たない低価格です。 iPadやiPhoneをお使いでしたら、一度お試しを。 |

2013年5月11日 (土)
SNSで研究材料を無料収集 昨日(2013年5月10日)早稲田大学で行われた、オンラインの外国語学習SNS「Lang-8」の創業者、喜洋洋氏の講演と、それに続くパネルディスカッションを聴講してきました。 内容的には、語学学習に終えるオンライン学習の意味合いや効果、起業、Lang-8のサービス内容そのものなど、いささか整理不足で散漫になった印象を受けました。ただ、喜氏の中国語学習体験に立脚した、「他にはないサービス」を事業化しようという意志と、起業してからの着実な歩みには感銘を受けました。具体的になにができるわけでもありませんが、今後の展開を応援します。 同時に、大学での「外国語教育」について、先日の黒田龍之助氏の講演とは別の方向から、問題を認識させられる場でもありました。 のっけから批判になって申し訳ないのですが、会場内で「Lang-8」を継続的に使っているユーザーの声が求められた際に、登場した「大学で英語を教えている」という人物の回答には少々驚きを禁じ得ませんでした。 この人物は、大学の講師であることを隠してユーザー登録し、学生の書いた英文を自分で書いたものとしてLang-8に投稿し、添削を受けてそのデータを研究用に集めているのだとか(講演の様子はUSTREAMで公開されることが予告されていますから、公開情報と考えて良いでしょう)。 そもそもユーザー同士が無償で相互に役立つことを基本として成り立っている場で、自らの立場を偽って研究の素材収集のために学生の文章を添削させているというのは、ずいぶんと身勝手な話です。 私ならば、このような研究材料の収集を無償で手伝わされているだけだったと知ったならば、きわめて不愉快でしょうね。こうした使い方を平然とするだけでなく、堂々とサービス提供者の前で公言するというのは、かなり非常識な振る舞いとして考えられません。 ハードルは下げるべきか? もう一つの疑問は、Lang-8というサービスの「問題点」として、「わざわざ文章を書いて投稿しなければならない」ことが何度も指摘されていたことです。もっと気軽に使えるようになってほしい、といった要望が目立ちました。 これに対して喜氏もハードルを下げていきたい旨の発言をしていましたが、それが事業上プラスかマイナスかは、喜氏ご自身の判断ですが、利害両面あることはたしかでしょう。 私の疑問は、たかが数行〜数十行の文章を書いて投稿することさえ面倒に感じている「ユーザー」を、動機づけてハードルを引き下げて、いったいどうしたいのか、ということです。 そもそもそれだけの努力を行っているのならば、外国語の習得などできるはずがありません。ハードルを下げるのは、「ちょっとやってみて、結局すぐに挫折する人たち」を、膨大に、しかも継続的に集めて全体のレベルを引き下げる結果を招くことは明らかです。 パネルディスカッションでは、「どのようにして学習モチベーションを高めるか」なるテーマでかなりの時間を使っていましたが、そもそもモチベーションを低い人々を無理に学習の場に引き寄せようとすること自体がナンセンスではないでしょうかね。 大学の授業で動機付け? こうした議論が当たり前に出てくるのは、大学という場でも「学び手のモチベーションを高める」ことが教える側の役割と認識されていることを示しているように思われます。 はたして、大学という場でそれは正しいのでしょうか。 いやしくも大学であれば、学生はなんらかの学習・研究に関心を持つことが求められます。 高校の延長で就職のための準備として大学に入ってきた学生もそれはたくさんいるでしょうが、その学生達はそもそも動機付けの対象でさえありません。学費を滞納さえしなければ、適当に遊んで卒業願うのが適切でしょう。 それなのに、大学側が懸命に動機付けをするなど、今時の学生は実にお気楽な「お客様」であるようです。 最後にパネラーの館岡洋子氏は、「SNSへの要望も良いが、リソースを示して、それをどう使うかは学習者次第でも良いのではないか」といった意味合いの言葉で締めくくっていましたが、私もまったく同感。 今回の講演とパネルディスカッションでは、主催者側の思い込みが強すぎて、結局議論の焦点が定まらないままに時間が経ってしまった感が否めません。それもまた、いまの大学という場が置かれている困難さの表れなのかも、しれませんが。 |

2013年4月10日 (水)
マイ語学の機能って 先日に引き続き、4月から始まったNHKの新サービス「マイ語学」のお話です。 このサイトへのID登録がないと、語学番組をストリーミングで聴けないとあって、おそらく登録者数はかなりに登っているのではないかと思われます。が、今日(4月10日)現在、サイトの機能としては、語学番組を視聴した履歴を管理する「出席簿」が提供されているだけと、ちょっとばかり寂しい感じです。 出席簿で表示される登録済み番組をクリックすると、出席状況を管理する画面を呼び出せます。 放送日別にタイトルが並んでいるリストに、いかにもクリックしてくれ、といわんばかりのアイコンがあるので押してみましょう。すると、各番組の紹介ページに。 え? 番組の紹介ページ? そのとおり。たとえば大人気番組「おとなの基礎英語」ならば、どのエピソードをクリックしても、表示されるのは同じ画面。表示されるキーフレーズは最新のものだけで、各エピソードでのキーフレーズが見られるわけでは、ありません。 「今週のフレーズでテストする」「キーフレーズを全部みる」というボタンが並んでいるのですが、その下には控えめに「※NHKエデュケーショナルが運営する「ゴガクル」に移動します。」と書かれています。 そう、ゴガクルの利用者にはおなじみのキーフレーズの一覧画面に、ここからリンクされているだけ。これって、以前と変わりません。 つまり、目下のところ、「マイ語学」=「語学番組視聴記録簿」なのですな。 予告はあるものの さて、マイ語学のサイトで使える機能がこれだけでは、さすがに不足だというのはおわかりのようで、以下のような表記が見つけられます。
うむむ、これまた微妙でして、たとえば「おと基礎」ならば月曜から木曜の22時50分、と決まっているわけです。 これが、「お気に入りの映画がついにテレビ放送される! 来週火曜日の20時35分から、絶対忘れないようにしなくちゃ!」ならばリマインド機能もありがたいのですが、半年もしくは一年間、決まった時間に放送される語学番組の場合には、それほどありがたみはないんじゃないでしょうか。 また、お薦め番組といわれても、限られた語学番組から「『おと基礎』を見続けているあなたには、『リトルチャロ4』もお薦め!」と推奨されても、ちょっと違いますよね。 おそらく言われなくても見ているか、もしくは何度か見て自分には合わないからとやめてしまっているかでしょうから。 そんなわけで、この「マイ語学」って、いかにポジティブになろうとしても困惑して苦笑を浮かべるしかない、どうにも困った状態。 ラジオ体操のハンコ この「出席簿」で私が思い出すのは、小学校の頃、夏休みになると必ず配られたラジオ体操の出席簿です。 夏休み期間中、ほぼ毎日のように学校の近くの公園などで朝からラジオ体操が行われ、出席するとハンコがもらえる。もちろん義務ではないし、皆勤賞だから何かもらえるわけでも、逆にハンコがゼロだと成績に影響するわけでもなく、ただ単にハンコを集めるだけ。 私はこの制度がとてつもなく苦手でした。 夏休みになると、生活のリズムが狂ってだらしなくなるのを少しでも防ぎたい、とでも思ったのでしょうが、そうまでして休み中の子供の生活を縛りつけようという意図が理解できません。まあ、友達に誘われるので数回は行くのですが、それっきりになりハンコがすべてたまったことなどありません。 語学学習も、体操と同じく毎日少しずつでも続けることには意味があります。 しかし、単にラジオを流し、テレビを眺めていたら急に英語が話せるようになるわけではなく、番組の視聴は学習のひとつのプロセスにすぎません。そこだけを取り出しても、学習者にとってはさして価値があるわけもなく、ただストリーミングを聴くために面倒でもログインしなければならない、というわけ。 ちょうど、友達と遊びに行きたかったら、一緒に公園でラジオ体操くらいしておかないと、なんとなく申し訳ないから、というのと同じ具合に「しょうがない」感じ。 そんなわけで、この「マイ語学」、さっさとゴガクルとも相談して学習者に役立つサービスに仕上げるか、じゃなかったら傷が深くならないうちに、やめちゃうか、決めた方がいいと思います。 |

2013年4月 8日 (月)
始まりましたが... いよいよ、語学番組新学期が始まり、ちょうど一週間の学習が終わったところです。 ストリーミングで学習されているかたも、今日から先週ぶんが聴けるようになっていますね。 もちろん、ラジオでは「まいにちドイツ語」を聴いているわけですが、平日朝は7時前に家を出て通勤をしているので、ちょうど放送時間には電車の中です。私の携帯電話は電波がちょっと弱まるとまったく通信ができなくなる特殊仕様?(DoCoMoさん、これなんとかしてよ)のため、「らじる★らじる」で聴くこともできません。 しょうがないので、これまで通りICレコーダで録音するか、もしくは翌週にストリーミングで聴くか、となるわけです。 第一週については、週末の土曜日に入門編の3回分を、そして今日応用編の2回分をまとめて聴きました。今日は平日だろうって? 自宅で給湯器の交換工事があったので、その立ち会いのために有休を取っているのです(で、ブログも更新作業中)。 さて、さすがに入門編では、とくにテキストも必要ないわけですが、応用編のほうはちょっと無理。ちゃんと聴こうと思ったらテキストなしだとちょっとついていけません。 なので、先月のうちにテキストを買っておいた...のですが、なぜか見あたらないのです。 どうも我が家には所々にブラックホールがあるようで、良くものがなくなります。「まいにちドイツ語」の4月テキストも、ちょうど講座が始まるころから行方不明となりました。 語学の前に、身の回りの整理整頓が先かもしれません。 マイ語学も、始まる ストリーミングといえば、今季からは利用のために「マイ語学」への登録とログインが必要になりましたね。 正直なところ、「マイ語学」でできることが単に視聴したかどうかの記録だけなので、この機能のためにわざわざ登録が必要になってしまったのは、利用者サービスとしてははなはだ微妙なのですが、きっとこれから機能追加があると期待しましょう。 サービスが微妙な理由のひとつが、「マイ語学」はNHK本体運営の「NHKオンライン」のサービスであるのに対して、このサイト「ゴガクル」はNHKエデュケーショナルの運営なんですな。 なので、両者の連携は皆無。おそらく、多くの人が使っている「おぼえた日記」もこの先連動はしないでしょうから、いまのまま「マイ語学」にさまざまな機能が追加されてしまうと、学習者はどちらかを選ばねばならないでしょうね。いやはや、会社というのは時折こういうわけのわかんないことをします。 NHKの語学番組はもちろん利用者も多く、しかも番組やテキストに対する評価も高く、これからますます広く使われてほしいと思います。 らじる★らじるやストリーミングなど、ラジオがなくても柔軟に学習ができるようになってきて、この先もコンピュータやモバイル機器を使った学習スタイルに合ったサービスが増えていくでしょうが、同じNHKグループ内で競合するようなサイトが運営されてしまうのは困りものです。 競合はサービス向上のためには役立つものなので、一概に統一せよとは思わないのですが、サイトがいくつあっても学習者は一人なのだということは、忘れないでほしいですね。 |

2013年3月16日 (土)
白と黒の煙 ローマ教皇を選出する「コンクラーヴェ」が終わり、新教皇フランチェスコ1世が誕生しました。 初の南米出身者ということもあるのか、教皇としての名前も一新して「1世」がついていますね。でもこういうのって、「2世」が登場してはじめて「1世」になるのでは、ないのですな。だれも名前を嗣がずに2世が続かなかったらどうなっちゃうんだろうか。 英国の「欠地王」ジョンは、2世が続かなかったために単に「ジョン王」であって「ジョン1世」ではないですよね。評判の悪いジョン王を引き合いに出しては、新教皇に失礼かもしれませんが。 さて、ローマ教皇における最近の「1世」ってだれだろうか、と調べてみると、意外なことにかなり近い時代のことで、1978年に位に就いた「ヨハネ・パウロ1世」がいます。彼のあとの「ヨハネ・パウロ2世」がかなり長く在位たので、私がローマ教皇としてまず思い出すのは、この名前です。 ヨハネ・パウロ1世はなんと33日間という短い在位にとどまった人で、ネット上の記事などを読んでみると、暗殺疑惑などといういささか物騒な話も出てきます。このあたりを追いかけた書籍もあるようなので、今度読んでみようかと思いますが。 その前の「1世」は さて、ヨハネ・パウロ1世の前の「1世」を調べてみると(Wikipediaの「ローマ教皇の一覧」という記事を参照しました)、なんと9世末の「マリヌス1世」まで1100年近くさかのぼってしまいます(「2世」が登場しなかった人はこの間にもいるようですが)。 9世紀にはあと二人、「ニコラウス1世」と「パスカリス1世」、8世紀には「ハドリアヌス1世」と「パウルス1世」と二人だけ。どうも、ローマ教皇の名前については、かなり以前から新たな「名跡」はつくられなくなってきているのですね。 この「1世」たちについてのWikipediaの記載は、おそらくは史料も多くはないのでしょう。非常にあっさりとしたものが多いようです(面倒なので日本語の記述しかみていませんが)。 その中で、オヤッと目についたのが、772年から795年の間在位していた、ハドリアヌス1世に関する記事です。ちょうど、フランク王国が現在のフランス・イタリア・ドイツにまたがる巨大な帝国となり、カール大帝(シャルルマーニュ)の治世にあたります。なお、カールにローマ皇帝の戴冠を行ったのは、ハドリアヌス1世の次の教皇であるレオ3世。 カールとの関わりについての記載のあとに、"theodiscus"なる項目が立てられ、786年にハドリアヌス1世にあてられた書簡についての記述が続いています。 これによると、この書簡に"theudiscus"という言葉が登場し、これが「ドイツ語」を表す最初の例であるのだとか。 英語版Wikipediaの"theodiscus"の項には、次のようなに記述されています。
ドイツってどいつ? 「ゲルマン民族の大移動」という言葉は、世界史が嫌いだったり苦手だったりしても記憶にあるでしょう。西ローマ衰退の直接原因などといわれます。 「ゲルマン」は「German」ですから、英語でドイツを意味する「German」と同じで、「ああ、ゲルマン民族の国だからGermanyなんだな」と、スッキリと理解できた気になります。でも、「ドイツ」ってのは一体どこから来たんだい? という疑問が出てきませんか? 私もただの素人なので、ちゃんとした論文にあたって調べているわけではなく、素人向けの本などでの解説によると、「民衆」や「民族」を意味するゲルマンの言葉から「ドイツ」という語が生まれて使われるようになったのだ、という理解をしていました。 どうやら、その最初の一歩がこの書簡に登場する"theodiscus"である、ということなのでしょう。ラテン語に対して「民衆の言葉」として表現されたこの言葉、当時はアングロ・サクソン系の王国が支配していたブリテンで使われていたゲルマン人の言葉を示していると考えられているようです。 この言葉がどんなふうに使われるようになり、最終的には「ドイツ人」「ドイツ」といった大きな概念に育っていったのか、実に興味深いところです。 かたや、ドイツ語は英語では「German」だし、フランス語だと「Allemand」です。後者はまあ、ライン地方のアラマンニ族からきているのでしょうが、近隣からも「ドイツ」とは読んでもらっていないのですね(逆に、ドイツ語でフランスは「Frankreich」すなわち「フランク帝国」というのも印象的ですぐにおぼえられます)。 特定の国や地域が、どんな経緯でいま使われている名前になってきたのか、それぞれに興味深い物語があります。 その中でも、「ドイツ」の成り立ちは、国民国家というよりも「汎ヨーロッパ/汎世界の帝国」という概念の残り火のような「神聖ローマ帝国」などという、今日のわれわれから見るといささかいびつな「国家」と、乱立する領邦との関わりの中から生まれてきたものだけに、なかなか「理解した気になる」のも困難です。 ドイツ人の意識の中で、この「ドイツ」という語は一体どんなふうに理解され、落ち着いているのか、もう少しちゃんとドイツ語が話せるようになったら、一度じっくりと聞いてみたいものです。 |

2013年1月27日 (日)
さて問題です さて、下記の歴史的な事件を、ドイツ語でなんというでしょうか? 1)大空位時代(1254年〜1273年) 2)95箇条の論題(1517年) 3)ビール純粋令(1516年) 4)アウグスブルクの宗教和議(1555年) 5)ヴェストファーレン条約(1648年) 6)神聖同盟(1815年) ドイツ語が得意なかたでも、突然これを聞かれると困るんじゃないでしょうか? 回答は以下の通りです。神聖同盟やヴァストファーレン条約のようにそのままのものもあれば、大空位時代のようにいわれればそうだよね...というのもあります。ビール純粋令の場合、どこにもビールとは書いてないんですね。単に純粋令。 ちなみに手元の和独辞書だと、上記のうち載っていたのは「ビール純粋令」だけです。 1)Interregnum 2)95 Thesen 3)Reinheitsgebot 4)Augsburger Reichs- und Religionsfrieden 5)Westfälischer Friede 6)Heilige Allianz 上記の例だと、「ドイツの歴史になんか興味ないし」といわれれば、それまでです。 では、たとえば「アメリカ同時多発テロ(9.11テロ)」や「ヘヴィメタル」「フリーズドライ」はいかが? 時事について、趣味の音楽や料理について話す時、こういった言葉が出てこなくて困ること、良くありませんか? まあ、「Neun-elf」といえばなんとか通じるし、「Heavy Metal」「Freeze-dry」でもきっとわかってはもらえるとは思いますが、ちゃんと通じるほうが良いですよね。 そんなときにはWikipedia 上記のような、ちょっとマニアックな名称や、最近になってからできた言葉、あるいは時事ネタなどは、辞書には掲載されていません。 なので、これらの言葉がめざす外国語でどう表現されているかを知るには、辞書をいくら引いても出てこないのですね。頑張って「Wastfalen Friede」は通じるかもしれませんが、「Große Leerstelle」で「大空位時代」とは理解してもらえないでしょう。 そんなとき、私が重宝しているのはWikipediaです。 もちろんみなさんご存じのオンライン百科事典。多くの人々が編集に参加しており、必ずしも記述が性格ではなかったり出典が明らかでない、あるいは存命中の人物の中小の場になっていたりと(場合によっては、自己宣伝のために記事を起こす人もいるらしく、やれやれです)、注意深く使う必要があるものの、とても便利です。 で、このWikipediaには他言語で同じ項目がある場合、そのリンクがずらりと並んでいるのですね。 たとえば、「フリーズドライ」の項を開くと、23のリンクがあるのがわかります。 ここで「Deutsch」を選んでみましょう。開いたページの項目名は、「Gefriertrocknung」となっています。なるほど「Gefrier」「trocknung」で、冷凍乾燥です。 ドイツ語やイタリア語、フランス語などであれば、この方法でほとんどの語を調べることができますし、がんばって記事を読めば関連する語も芋づる式にわかってきますね。 スマートフォンでも使えますし、Wikipediaを読むための専用アプリなんかもありますから、これならかなりお手軽。 ちなみに、「ヘヴィメタル」はドイツ語では「Metal」だそうです。「金属」は「Metall」で「重金属」は「Schwermetall」なので、実にトリッキー。 |

2012年12月22日 (土)
Googleロゴ 検索サービスでおなじみのGoogleですが、さまざまな記念日にあわせてそのトップページのロゴマークデザインが変わるのは、みなさんご存知かと思います。最近では、ほぼ毎日なんらかの記念日になっているような... 先日の木曜日(12月20日)は、世界中で知られているあのお話がロゴデザインになって登場。もちろん、クリックすると物語がちゃんと進行しました。毎度手が込んでいます。 クリック、クリック、無事赤ずきんとおばあさんが救われ、オオカミはなぜか刑務所に。 グリム兄弟によるメルヒェン集の第1版が出版されたのが1812年の12月で、今年200周年を迎えたのだそうです。 グリム童話といえば、ほとんどのかたは子供のころから絵本や児童向け文学全集などでおなじみでしょうし、ディズニーのアニメーションからホラーまで、幅広い映画やドラマの原作にもなっています。おそらく、「グリム童話を一編も知らない」というひとは極めて少数なのではないかと。 「本当は怖い~」なんていう本がヒットしたのは、あれ何年前でしたっけ? 短いのが良い グリム兄弟といえば、もっぱら童話集の作者(編者?)として知られていますが、言語学者としての業績が高く評価されています。 ドイツ語学習者の多くが発音に苦労する「Ä,Ö,Ü」の「ウムラウト」という呼称も、長兄ヤーコプの造語なのだとか。 200年前、19世紀のはじめといえば、ちょうどナポレオンがヨーロッパを席巻していた時期に当たります。 1806年には神聖ローマ帝国の「解散」が宣言され、ここから半世紀の後にプロイセンを中心としたドイツ帝国が成立するまで、ドイツはそれまでの実態通りの分裂状態となります。ライプツィヒの戦いでプロイセン、オーストリア、ロシアなどがナポレオンを破ったのが1813年10月のことですから、ドイツが「帝国」を失い、フランスの支配から逃れようともがいていた時期に、グリム童話集が世に送り出されたということになります。 時代背景を考えると、これは単に子供向けの本ではなく、ドイツ人、ドイツ文化にとっての記念碑的な存在であったことが想像できますね。 さて、ドイツ語の学習者にとっては、グリム童話は優れたリーディング教材でもあります。 なんといっても短いのが良い。長いと途中で疲れますし、連続して何時間も集中して外国語を読む時間を捻出するのは、だれにとっても簡単ではありません。 また、マイナーなものをあえて選ばなければ、話の筋はだいたいわかっているので理解しやすいところもありがたいところです。これが初めて読む小説だと、話に入り込む前に睡魔が襲ってきます。 しかも無料 もちろんドイツ語教材として本を買うこともできますが、グリム童話をただ読みたいだけならば、さまざまなサイトから無料で入手可能です。 最近ついに日本でもサービスを開始したAmazonのKindleストアでも、さまざまなバージョンのものがやすいものは100円から、1000円までの範囲で販売されていますので、あちこち探す手間を省きたければこれでも良いでしょう。(英語だと無料がたくさん並んでますね) 以前探してみたときには、この童話を読み上げた音声ファイルが無料で公開されているのも見かけました。たぶんまだあるでしょう。 オーディオブックよろしく、リスニング教材として使うこともできますね。インターネット以前には、こんなに簡単に教材がそろうなんて考えられませんでした。 そんなこんなで、200周年の記念に、年内にひとつくらい、グリム童話の懐かしいお話を外国語で読んでみてはいかがでしょうか。 |

2012年6月24日 (日)
なぜヘルシンキ? 今日はちょうどお昼前後に散髪の予約をしてしまったこともあって、一日自宅で過ごしていました。 こうなると、録画したドラマ(今日は「CHUCK」のシーズン3)を消化したり、あるいは見るともなくテレビがかかっていたりで、なかなか勉強はできません。 で、たまたまかかっていた、ディズニーのアイスショーの宣伝番組の冒頭でびっくり。 レポーターの中川翔子さんが寒い寒いと騒いでいるのは、なんとフィンランドの首都ヘルシンキの大聖堂前、Senaatintori(元老院広場)ではないですか。 なんでわざわざこんなところまで、と思ったのですが、たまたま取材の日程でのショーの巡回先がここで、ディズニーの許可が下りたのでしょう。残念なことに、ヘルシンキ市内を紹介する映像はほんのちょっとだけでした。 なんか違う ディズニーのアイスショーですから、もちろん登場するのはミッキーマウスとミニーマウス、そして長編映画に登場するプリンセスです(もっとも、なかには「これって明らかに王族じゃないよね」というキャラクターも混じっています。何でもかんでもヒロインはプリンセス?)。 で、ショーのあいだ流れる音楽もおなじみのディズニーの映画音楽。 でも、なんかちょっと違います。普段聞き慣れている音が聞こえてきません。 それもそのはず、子供にも理解しやすいよう、日本では日本語の歌詞で歌われるように、フィンランドではフィンランド語の歌詞で歌われているので、聞き慣れたメロディでも歌は聞き慣れない言葉です。 途中で会場の子供達への取材シーンもありましたが、もちろんフィンランド語。単語レベルでたまに知っているものがあるとはいえ、全体としてはまったくわかりません。 よく知っている音楽だけに、耳慣れない言葉で歌われるとか選って違和感が大きくなるものですね。 これで勉強も良いかも ふと思い立って、YouTubeで「Disney music suomi」などと検索してみたところ、けっこうたくさんの動画がひっかかってきました。 その中から、字幕付きと書いてあるものを選んで再生してみると、うまい具合に英語とフィンランド語の字幕付きで(上下にそれぞれ出ます)リトルマーメイドの「Part of Your World」を聴けました。 音だけで聴いていたのではちんぷんかんぷんでも、字幕があるとときおり知っている単語が登場します。 何度も聴いているだけに、歌詞のだいたいの意味はわかっていますし、英語の字幕も同じタイミングで流れてくるので意味を照合するのも簡単。日本語字幕だと、照合してもあまりうまい具合には突き合わせできませんが、英語ならばかなりの度合いで単語同士の比定ができます。 単に旅のフレーズ集を耳から聞くよりも、このほうが耳にも心地よいし、勉強と思わなければ音楽を聴いていればいいのだから、学習(というよりは、耳慣らし程度ですが)としてはお手軽かもしれません。 たまたまアニメーション映画の主題歌で調べてみましたが、よく知っている曲が他にないか、ちょっと調べてみようかと思います。 |

2012年6月 9日 (土)
学習と日常のあいだ 語学学習がある程度進んできて、読み書きや会話が多少はできるようになってきた状態、いわば中級にさしかかったあたりから学習用の教材探しに苦労するようになります。 この時期になると、それぞれ「○○語を使ってなにがしたいか?」という目標が学習者毎に変わってくるので、教材の内容や想定水準、扱うテーマなどによって好みがはっきりしてきます。しかし、個々の好みや関心に合わせた教材をつくっても、数がまとまるわけではないので売れない、したがって思い通りの教材が世に出ることが少なく出会えない、ということなのだろうと私は思っています。 いわば、「学習」から「日常」に、外国語との付き合いかたが変わらざるを得ないタイミングが、やってきただけなのでしょう。 そもそも「バイエルン王国の歴史」に興味のある人が、いつまでも挨拶とか旅行会話の教材を使っていても仕方ありません。 それならば、やはり手っ取り早いのはバイエルンの歴史に関する本を読むことであり、あるいはドイツ語による講座があればそれを受講することであり、同じ関心を持つ人と話せる環境を手に入れることでしょう。 とはいえ、本を読む以外はちょっと難しいですよね。不可能じゃないけど、そもそも大都市部以外ではそう簡単には機会がないし、仕事を続けながらではバイエルンに2ヶ月滞在して、なんてわけにもいきません。 さらには本を読むとはいっても、難易度が高すぎたり厚すぎたりして、途中で挫折することも容易に考えられます。 以前ならば、ここら辺で「やっぱむずかしいよね」で終わっちゃっていたのですが、インターネットの普及はいろんなことを簡単にしてくれました。 たとえば「バイエルンの歴史」なので、「Bayerische Geschichte」で検索してみます。私の環境では最初に出てくるのがドイツ語版Wikipediaの記事「Geschichte Bayerns」です。Wikipediaの記述はときおり不正確なこともありますが、まずは一通りの知識を得るには十分でしょう。それほど長くもありません。 そしてすぐしたには「Haus der Bayerischen Geschichte」なるサイトが出てきます。アウグスブルクにあるバイエルン歴史館のサイトですが、さまざまなテーマについて比較的短い紹介文を読むことができますね。 PCで探して、タブレットで読む これは私だけかもしれませんが、PCでこうした情報を探し出しても、なかなか集中して読むことができません。 以前は、もったいないと思いながらもサイトの情報をプリントアウトして持ち歩き、電車の中や喫茶店で読んでいました。これって、たしかに読みやすいのですが、読み終えたあとの紙の処分に困るのですね。また読むかもしれないと思って取っておいても、整理しておかないものだから結局はただのゴミになります ところが放っておいても物事は便利になっていくもので、「Instapaper」というサービスとiPadなどのタブレットを使うことで、プリントアウトいらずで、しかも快適にネットの文章を読めるようになっています。 もちろん、iPadでなくても、他のタブレットや画面が大きめのスマートフォンでもかまいません。若いかたならiPhoneの画面でも平気かもしれませんけどね。 このサービス、WEBで見つけた記事を「これはあとで読もう」と思ったら、登録しておくだけ。邪魔な宣伝やメニュー部分を省いて、本文を読みやすい形で保管しておいてくれます。 いったいどうやったらこんな風にうまい具合に情報を省けるのか、私にはわかりませんが、理屈がわからなくても便利に使うことはできます。 上記のように検索経由であったり、Twitterやfacebookで紹介のあった記事が気になったら、次々に登録しておけばあとでじっくりと(しかも本文だけを快適に)読むだけ。ちょうどプリントアウトして持ち歩くのと同じ具合です。 なにもお金を出して教材を買わなくたって、リーディング教材はいくらでも転がっています。しかも、それを気軽に保管し、快適に読めるサービスもある。なんと「Instapaper」は無料サービスです。 最近になって、ついにAndroidにも対応されました(それまでもサードパーティのアプリはあったのですが、綿新環境ではなぜか古い記事しか同期されずに読めませんでした。いまはもう大丈夫です)。 PCだって不要で、スマートフォンならばアプリ間の連携がうまく考えられていますから、「共有」機能を使ってほぼワンタッチで自分の「Instapaper」に記事を送ることができます。文字が小さいからと拡大したりといった作業さえ不要で、じっくりと読めるわけです。 教材がない、と悩んでいる中級学習者のかたがたは、ぜひスマートフォンやタブレットで「Instapaper」を試してみてください。 |

2012年5月24日 (木)
早すぎます インターネットが家庭からも使えるようになったのが1995年か96年くらいだったでしょうか。正確なところはわかりませんが、まだ20年は経っていません(それでも、当時生まれた甥っ子がもう高校生ですけどね...)。 しかしこの15年ほどの変化は実にすさまじいものです。子供のころに読んだ小説やマンガに登場した、エアカーが走る未来都市も、月面植民地もできませんでしたが、当時の想像をはるかに超えた世界に、私たちは住んでいます。 はじめは電子メールやネットニュースなどの文字中心のコミュニケーションだったものが、WEBブラウザで写真や図表などの画像が見られるようになり、すぐに音声が扱えるように。 ビデオだって最初の頃はマッチ箱大の絵がカクカクと駒落ちしながら動くものだったのに、いまではハイビジョン映像のストリーミングさえ可能です。ベルリン・フィルのコンサート中継を自宅で高画質で見られるなんていっても、10年前の私は信用しなかったでしょう。 年は取りたくないもので、5年くらい前からは段々とこうした変化に乗り遅れることが多くなってきました。 新しいサービスを使って自分の生活を便利に変化させるスピードよりも、次の新しいものが生まれるスピードのほうが早くなってしまったのですね。こうなると、新しいものにはすぐに飛びつかずに、じっと様子を見て「一個飛ばし」で取り入れるのがちょうど良かったりします。 雑誌で読みたいのは10ページだけ 最近は雑誌をちっとも買っていません。見出しに惹かれたとしても、「なんだ、この特集たった10ページか。あとの100ページは要らないし」と棚に戻してしまうことが増えました。 雑誌の「特集」が10ページとか20ページしかないのは、今に始まったことではありません。それでも、かつては情報料そのものが少なかったために、その10ページのために雑誌を買うことに抵抗がなかったのですね。 なので、今では雑誌を買うのは、その号の内容がほぼまるごと特定の関心あるテーマに関連しているときくらいです。 10ページにはお金は払わないけれど、100ページならOK、という感じでしょうか。これだと、毎号テーマが変わるたびに売れ行きの差が激しくなって、つくる方は大変だろうな、と思うのですが。 最近になって、この傾向にさらに拍車をかけるようなサービスが続々と登場しています。 その一つが「ソーシャルリーダー」とか「パーソナライズド・マガジン」とか呼ばれているもの。具体的には、つい最近日本語サービスが始まって話題になった「Flipboard」や「zite」などです。 簡単に言うと、関心のあるジャンルを選んでおけば、WEBの多様な情報の中からいくつかの記事やニュースをピックアップしてきれいにレイアウトしてまとめてくれるサービスです。自分で検索サービスやRSSリーダーを使って探すよりも、ずっと効率よく情報がまとまります。いわば、新聞やテレビの情報番組、そして雑誌がやっていた機能がオンライン上に移ったようなもの。 外国語のニュースを読む 良く外国語の習得、とくにリーディングの訓練のために、その言語のニュースサイトや新聞社の記事を読もう、というのを聞きます。 たしかに、これを続けるとけっこうなスピードで外国語が読めるようになり、語彙や表現も増えて効果的なのですが、「関心のある記事」を探し続けるのって、それなりの手間と時間がかかってしまいます。よほど「相性の良い」サイトでも見つけられない限りは、続かないケースも多いのではないかと思います。 たとえば、「zite」には33のカテゴリーがあって、ここから関心あるものを選ぶことができます。 くわえて、自分なりのキーワードを追加することもできるので、ある程度絞り込まれた状態から記事を探せるという点で非常に便利です。 読んだ記事が良かったら右側にある「Did you enjoy reading this?」に「YES」を、そうでなければ「NO」を選んで行くと、その後の掲載記事に好みを反映させることができます。また、記事の書き手や掲載サイト、記事に出てくるキーワードをクリックしておけば、それを加味したものが増えるという仕掛けです。 もちろん、気に入った記事をtwitterやfacebookで紹介するのも簡単。 全ての記事ではありませんが、タブレット(iPad版を主に使っていますが、Android用のアプリもあります)で読みやすいレイアウトになっていて、その場で文字の大きさも変更できますから、いちいちWEBサイトの表示を二本指で拡大表示する煩わしさもありません。 自分好みの記事を検索して探す、文字を調整して読む、次からも類似の記事を読めるようにブックマークしたり、著者の名前を覚えておく...いずれも、やればできることばかりですが、ひとつひとつが重なるとストレスが大きくなって面倒になります。 煩わしさや面倒は語学の大敵。ほとんどの場合、ちょっとおっくうなことが重なるだけで、学習意欲はしぼんでしまうものです。 ソーシャルリーダーなどの新サービスは、「外国語を読む」ことの手間や面倒を大きく引き下げてくれそうですし、しかもどんどんと改善されていくことでしょう。画面をめくりながら記事を見つけ、読んで閉じて...この手軽さは、PCでは味わえないものです。 いまや、外国語を「読む」用途には、PCよりもタブレットのほうがずっと優れた環境といえるかもしれません。 |

2012年4月22日 (日)
アルバムとシングル 街の「レコード店」が「CD店」になり、いまやネット配信に主流が移って店舗がどんどんと減っています。 LPレコードのアルバムがほしいけれど2000円以上もしてはなかなかお小遣いではまかなえず、中からシングルカットされた単曲をドーナツ盤で買って何度も何度も繰り返し聴き続けて親に呆れられた、というのも今は昔。 ウォークマンが登場して音楽を場所を選ばずに自分一人で聴けるようになり、iPodが持ち歩ける音楽の量を大幅に増やし、そして音楽データそのものをネット上において手元の機器の容量が制約ではなくなりつつあります。 音楽だけでなく、映画やドラマなどのビデオも含めて、あらゆるコンテンツについて、「買ったコンテンツをディスクやメモリに保管して持ち歩く」時代は過ぎ去ろうとしているように思えます。 こうなると、アルバムとかシングルとかいった概念も、急速に消えていくでしょうね。 むしろアルバム単位の形にこだわることのほうが、音楽に関しては古めかしくなっていくのかもしれません。 iTunes Storeなんかだと、アルバムの中の曲が単曲でも買えますから、シングルカットされない特定の曲だけのためにアルバムを買う必要さえなくなっています。 ただし、単曲で販売する曲を長さで区別しているようで、交響曲の特定楽章だけが単体で買える、というおかしなことも発生するのですが。 短編集とシングル盤 音楽においてアルバムの枠組みが消えつつあるのと対照的なのが書籍です。 たとえば、トム・ゴドウィンの名作短編「冷たい方程式」を読みたいと思い立った読者がいたとします。この作品はハヤカワ文庫から他の作品と組み合わせたアンソロジーとして販売されていますが、読みたいのはこの作品だけでも、他の8編の短編小説とセットでないと買えません。 また、特定の短編小説や短いエッセイだけが知られている作家の場合、その作品が何らかの形でアンソロジー等に採録されなければ、読まれることなく埋もれていく可能性もあります。 もちろん、アンソロジーで当初の目当てとは違う作品の魅力に気がつき、そこから読む本の幅が拡がっていくというメリットは見逃せません。 しかし、それならば特定の作品をキーにしたリコメンド機能によって代替可能です。まあ、古い読者である私自身も、現在のショッピングサイトのリコメンド機能に満足しているわけではありませんが... 短いということは、その言語を外国語として読む読者にとってもありがたいことです。 読書が趣味といっても、長編小説をじっくりと読むのはそうそう簡単ではありません。時間もかかるし、その間他の本が読めなくなっちゃいます。負担が大きすぎては長続きしないのが趣味でも学習でも一緒のこと。 短い小説やエッセイならば、そこそこの時間でひとつの作品を読み終えることができ、飽きたりくたびれたりということがありません。 本をばら売り 短編小説を単体で買えないのか、というニーズに対応できそうなのが、「Kindle Singles」というサービス。 ようするに、Kindle専用(といっても、専用機だけでなく、iPadやスマートフォン、PCやMacでもKindle向けの本は読めます)の電子書籍を、従来の「本」の単位でまとめるのではなく、短い文章をばら売りにしてしまおう、というもの。 当然長編小説などよりはやすく、$0.99から$2.99程度で購入ができます。 これならば、一冊の「本」にまとまらない作品を販売することができるようになり、たとえば人生でたった一編だけの傑作短編を書き上げた作家でも、広くその作品を販売することができるわけです。 他におもしろいと思ったのは、旅行ガイドのばら売りです。 旅行ガイドは、たとえばアメリカ西海岸とか国単位といった少し広い範囲を扱いますが、ロサンゼルスに旅行に行くだけなのにラスベガスやサンフランシスコの情報は不要。持ち歩くにしても重たくなります。 都市ごとや狭いエリア毎にばら売りされていて、しかも電子書籍としてスマートフォンやタブレットで持ち歩ければ、荷物は実質増えません(スマートフォンを持っていくのが荷物でいやだ、というなら話は別ですが)。 Kindle Singlesにはまだ200に満たない「本」しかなく、ここで好きな本が見つけられるとはいえない状態です。 けれど、これが拡充されていけば、本の読み方が大きく変わるかもしれません。 |

2012年2月22日 (水)
時間繰り上げ すでに4月からの新年度の語学番組の情報が発表されています。 このブログにも書いたとおり、2月7日の発表会には私も参加させていただきましたが、内容よりもテレビ講座の放送時刻に驚きました。 Yuhさんのブログにもリンクがありますが、まずはテレビ番組の放送時刻表をご覧ください。 月曜部は22時から「テレビでハングル講座」、22時25分から「テレビでイタリア語」、そして50分から「おとなの基礎英語」と並びます。 同じように、火曜から木曜も英語番組、EURO24、そしておとなの基礎英語と続き、22時台のEテレは語学番組の時間帯となっています(金曜日は別)。従来の語学番組時間帯であった23時台は、月曜の「スーパープレゼンテーション」を除き語学番組が消滅。完全に1時間繰り上がった形です。 私はそれほど影響がないのですが、この時間帯はドラマやらバラエティ番組やらが多いところで、普段観ている番組とバッティングしてしまう、というかたも多いのじゃないでしょうか。 一週遅れの昼の時間帯にある再放送を観たり、あるいは録画してタイムシフトで勉強、というかたが増えそうにも思えます。 1時台は録画じゃないと 上記の発表会でも異彩を放っていた戦場カメラマン、渡辺陽一氏が生徒役となる「テレビでアラビア語」はおもしろそうだなと思っているのですが、この放送時刻は水曜の1時(火曜深夜)です。 さすがに火曜日はドイツ語教室で精根尽き果てることも多い(なので、このブログも再開後は水曜更新に変更)ため、夜中まで起きていての学習は無理そうです。観るとしても録画しないとダメかな。 「テレビでロシア語」も同じように水曜深夜です。夜型のかたも多いでしょうが、さすがに1時からの25分間では、眠くて勉強にならないのではないかな。 これにくらべると、ドイツ語を含む欧州4言語は恵まれているとは言えそうです。 やはり、録画・録音してしまうと「いつでも観られる(聴ける)し」と安心してため込んでしまいがちです(少なくとも私はそう、「実践ビジネス英語」最後にちゃんと聴いたのはいつの放送回だったっけ...)。リアルタイムで観るのに越したことはないでしょう。 録画したらお風呂で語学は? 最近のスマートホンやタブレットの中には、防水性能を持つものが増えましたね。 こうしたものの中には、レコーダーやテレビ本体で録画した番組を無線LAN経由で再生できる機能を持っているものもあるようです。 iPadやiPhoneの防水ケースなども、いくつか販売されています。 こうしたスマートホンやタブレットを使えば、前よりもずっと簡単にお風呂で語学番組を観ることもできますね。 シャワーだけで済ませてしまうかたも少なくないでしょうが、半身浴でじっくり10分20分と浸かると、非常に体が温まります。半身浴のお供に語学番組なんてのも良いんじゃないでしょうか。 お風呂で歌うと声が響いて上手に聞こえますが、外国語の発音もきれいに聞こえるかも? さて、ロンドン五輪に向けたサッカーのアジア最終予選もいよいよ後半が始まります。 サッカーを気にしながら書いているので、なんだか散漫な内容になってしまいましたが、本日はこれにて。 |

2011年10月 8日 (土)
Phone4S iPhoneの最新版、iPhone4SがAppleから発表されました。昨日の予約開始日には、店頭に列もできていたようです。 今回は、ソフトバンクだけでなくauからも発売されることも大きな話題です。発売前から、規格上の通信速度やら、月次のコストやら、はたまた通信と通話が同時にできるとかどうとか、舌戦のほうもかなり活発です。 発表の直後には、Appleの創業者であり、最近ではAppleそのものといっても良いほどの存在感を示していた前CEO、スティーブ・ジョブズ氏の死去のニュースが飛びこんできました。 私自身も含めて、企業のトップの死がこれほどまでに多くの人々に強い感情を引き起こしたことなど、なかったのではないでしょうか。私たちの年代にとって、彼は時代のアイコンといっても良いほどの存在でした。 正直な話、木曜日は私もどこか仕事にも身が入らないままに一日を過ごしました。 ジョブズ氏の冥福をお祈りしたいと思います。 マウスを持って「コンピュータ!」 初期の一体型Macを見るたびに、スタートレックの映画第4作「故郷への長い道」のシーンを思い出します。 1980年代のアメリカにタイムスリップした宇宙船エンタープライズの機関部長スコッティが、Macを前にして「コンピュータ!」と語りかけ、反応しないのを見てしばしいぶかしんだのち、マウスを見つけてニヤリとし手に持って再度「コンピュータ!!」 コンピュータを音声で操作するアイディアはかなり以前からあって、まだWindowsのバージョンが3だったころ、やっとPCにCDドライブが搭載され始めたころにも、マイクから特定のコマンドを叫ぶといくつかの操作が可能になりました。 ただし、ちゃんと認識されないことも多く、またできることも少なすぎて実用的とはいえませんでしたけどね。 Siriに期待 iPhone4Sの新機能として一部で話題になっているのが、「Siri」です。 これは、音声によってiPhoneを操作するテクノロジですが、従来と違うのは決められたフレーズやコマンドだけを解釈できるのではなく、さまざまな表現にも対応できる、とされています。 たとえば、天気を知りたいときにも「今日の天気は?」だけでなく、「傘は必要?」と尋ねても良いとのこと。 SF映画に出てくる、自然な言葉で対話できるコンピュータの実現も、そう遠くはないのかもしれないと期待させてくれますね。 現在のところ、この機能に対応しているのは英語、ドイツ語、フランス語の3つ。英語に関しては米英豪の発音に対応しているとのことです。 なんだ日本語に対応していないのでは使い物にならない、という考え方もあるでしょうが、絶好の外国語練習台にもなりそうです。 カタカナ発音でも認識してくれるとそうでもないでしょうが、自然な英語(あるいはドイツ語やフランス語)に近い発音でないとちゃんと聞き取ってくれないのなら、より自然な発音に近づけるための簡易な実験台にもなりそうです。 この技術がより高度になっていけば、電話の操作だけでなく会話の相手をコンピュータがやってくれるのだって、わりと近いうちに実現できるかもしれません。 ただ、日本語対応していないから、日本で販売されるiPhoneからはこの機能が使えない、なんてことにならなければよいのですが。 |

2011年8月 9日 (火)
サボり中です 7月の中旬に台風がやってきて以来、東京でも最高気温が30℃に届かない日が多くてかなり過ごしやすい日が続きました。 このまま秋になってくれればラクなのに、と思ったのですが、そううまくはいかないものです。今週に入ってからはいつも通りの蒸し暑さが戻ってきました。今年は冷房も控えめに、ということで、こう暑くては外国語の勉強にもなかなか身が入りません。 ちょうどうまい具合に、このところ仕事のほうもだいぶ忙しくなってきました。 蒸し暑さと忙しさが重なっては、英語やドイツ語の勉強どころじゃないですね。そんなわけで、8月に入ってからは「テレビでイタリア語」「テレビでドイツ語」を観た程度で、他にはほとんど勉強できていません。 毎日継続なんてできない 「継続は力なり」といいますが、そもそもこういう言葉が頻繁に引用されること自体、誰もが「継続できない」ことの表れともいえます。 私は語学学習の最大の敵は、「継続できない」ことではなく「継続できない自分には外国語は無理だ」と思わされてしまうことじゃないかと思ってます。どんな状況でも15分30分の学習を欠かさない、それは立派なことです。でも、立派な人は少数だから立派なのですね。 勉強する気力がないときにはサボっちゃえばいいと思うのですが、サボったことが罪悪感や無力感につながるとすれば大問題。 こういうときには、勉強ではないけれど、外国語に無理なく触れる程度にしておくのも一つの手です。 好きな映画を言語で観るとか(勉強ではないのだから、そもそも台詞なんか聞き取れなくても話がわかるほど繰り返し見たものがいいです)、洋楽をかけるとか。 なんとかしのぐ 私は「ただ聞き流すだけで何とかかんとか」といった英語教材の効用は一切信用していません。ただ、学習効果などまったく期待せずに、「サボってしまった」罪悪感を持たないようにするためだけならば、多少は意味があるかもしれません。 でもまあ、そのためにお金を出して教材を買うのはさすがにムダでしょうね。ネットが使えれば無料のビデオや音声がたくさん手に入りますから。 たとえば次に行きたい旅行先を紹介したビデオなんかはどうでしょう。 旅行代理店や専門誌などが、さまざまな旅行先やサービスの紹介ビデオを公開していますから、まずは動画サイトなどで目的地で検索、良さそうなビデオを公開している業者のサイトに行けばいろいろと見つかります。 先週末は、妻と二人で犬ぞりレースのビデオをあれこれと探しては観ていました。都合3時間くらいは英語を読んだり聞いたりしていたと思います。 「継続は力なり」というのは、とりあえずなにもしたくないときにも、自分が納得のできる程度に何かでしのぐ、ということも含めてで良いのなら、私のような凡人でもなんとかなりそうです。 |

2011年6月11日 (土)
ムラ社会が苦手 日本はムラ社会だ、閉鎖的だ、なんてよくいわれますが、それが心地よいと思っている人はそれほどは多くないのではないでしょうか。 みんなと一緒、横並び、というのは競争がないぶん楽ではありますが、はみ出してしまうことを恐れながら暮らすのは ― それを一度意識してしまうと ― 逆にストレスの多いものです。そのストレスが今度は「はみ出しているあの人を『修正』しなければ」になってしまうと、悲劇に悲劇を重ねることに。 私は窮屈な関係が嫌いなので、団体行動がとても苦手です。旅行もツアーには入らずに行き先、宿、移動手段をすべて自分で確保します(インターネットのおかげですけどね)。 会社では、オフィス全体での行事があってもなるべく言い訳を作って参加しません。ときには仕事を円滑に進めるために出かけて行って、ニコニコしながらじっと時間が過ぎるのを待ってることもあります。 こんなわけですから、最近の川本さんのブログ記事は衝撃! 他人の目線が英語学習に影響を(You Can Do It!) なんと、「英語の勉強を始めたら、陰口の対象になっていた(超まとめ)」というもの。うっそー、という感じですが、よくよく考えたらありそうな話とも感じます。 きっとご本人にとってはとてもストレスのたまる環境でしょう。だって、英語の勉強したからって誰にも迷惑はかけません。世の中には周囲を巻き込んで迷惑をまき散らし、本人だけがご満悦、という「趣味」はいくらでもありますが、おそらく英語の勉強は無害の極といってもよいでしょう。 なぜただの「趣味」にならないか 「一か月後に海外赴任!」とか「TOEICのスコアが昇格に影響」なんていう人たちを除けば、英語はヨガや読書や韓流ドラマと同じく、単なる趣味です。 何か迷惑をこうむっていない限りは、人の趣味に文句をつけてよい理由など存在しません。家族を顧みずにゴルフに明け暮れている部長さんがいても、それはその家族の問題です。相談を受けたわけでもないのに「それはまずいんじゃないですか?」などと口出しするようなものではありません。 では、なぜ英語だと嫌がらせや陰口の対象になることがあるのか? 乱暴にいっちゃうと、「それだけ多くの人たちに英語コンプレックスがあるから」ではないのかな、と思います。英語は気になる、話せないとなんだか時代に遅れている気がする、あるいは英語が得意な人は何か特殊な才能や環境に恵まれた人に思える。 なので、「英語ができない仲間」から離れようとする人が目の前にいるのはちょっと面白くない、てな感じ? 世の中のたくさんの人たちが「英語は気になる」「でも勉強しようとは思わない」。 だからこそ、ただCDを聞き流しているだけで「自然に英語が口から出てくる!」なんていう、はなはだ効果の疑わしい教材が評判になっちゃったりもするのでしょう。 こういう教材がよろしくないと思うのは、たまたま相性よく学習成果が出る人たち以上に、「結局何をやってもダメだった」という無力感を味わう人たちのほうがずっと多いように思われるからです。なにかを習得するために、まったく苦労しなくてよいなんてことが、あるはずがない(苦労を苦労と感じなかった、ということならあるでしょう)。 でも趣味だよね おそらく、日本人は世界中の先進国の中で、もっとも生活するうえで英語の必要度が低い国の一つじゃないでしょうか。 生きるために必要でない限りは、やっぱり英語は趣味です。趣味である以上は、やっぱり生け花やパッチワークやフェルト人形と変わらない。英語を陰口のタネにするのは、英語学習者が悪いのではなくて、陰口をたたく人の心の問題です(まあ、陰口ってそういうものだけど)。 趣味を持つだけであれこれと干渉を受ける生活環境は、とてもストレスがたまるものだと思います。 だからといって、さっさと引っ越すなんてことは簡単ではありません(簡単なら、もうやってるでしょうしね)。なので、やるべきことは「同じように感じている知人を作る」ことでしょう。 普段から顔を合わせられる関係でもよいし、オンラインだけのつながりでもOK。同じように外国語を趣味として、ときおり陰口やら嫌がらせに遭遇しつつも、正面から受け取らずにいなせる人たちとの関係を作ることが大事なんじゃないかと思います。 思い起こせば、私も英会話教室に行き始めたころはとにかく聴けない、話せないだったので、何度も途中で嫌になりました。 それでも続いたのは、教室に行くと自分と同じくらい苦労していて、きっと同じように「嫌になってる」人たちに会えたからです。友人といった関係ではありませんでしたが、軽い連帯感のようなものはあるわけです。 日本人にとって「英語なんて特別じゃない」ものになるには、地域差もあるでしょうが、もうしばらくかかりそうです。なので、当面は仲間をできるだけ増やす、という工夫は、ストレスをため込まないために大事ではないかと思います。 |

2011年5月 7日 (土)
FacebookはFacebook ドイツ語はわりと外来語の取り入れにも柔軟なようで、電話機はFernsprecherなる単語はあるものの、やはりTelefonです。TelephonじゃなくTelefonであるところに、ちょっとだけ維持を感じますが。 最近になって出現したサービス名だと、やはりわざわざ現地語での名前などつけないようで、Twitterはドイツ語でもTwitter、そしてFacebookもやっぱりFacebookです。 こうしたネットのサービスでは、使用する言語の切り替えも簡単にできます。 以前はTwitterをドイツ語モードで使っていたのですが、サイト上の言語がドイツ語になるだけでなく、「○○さんがあなたをフォローしましたよ」といった通知メールもドイツ語になるので、最近では日本語に戻しています。 Twitterに続いて最近注目を集めているのはFacebookです。 このゴガクルブログにも、「f|Share」という青いボタンがついているのに気がついているかたも多いでしょう。これがFacebookでこの記事をリンクして紹介するためのボタンです。 今年になってから使い始め、ずっと日本語で使っていたのですが、ちょっとドイツ語モードに変えてみました。 Gefällt mir! Facebookでは、ネット上のさまざまなコンテンツ、写真やブログの記事などを「Like!」として友人とシェアすることができます。匿名の関係ではなく、実際に人となりのわかっている友人同志で関心のある話題やおもしろいコンテンツを共有できるしくみです。 この「Like!」は、日本語では、「いいね!」となっています。直訳してしまうと「好き!」ですが、なかなか気の利いた訳をしたものだと感心します。 この「いいね!」は、ドイツ語では「Gefällt mir」となっています。 こんなところで使われていると、ドイツ語文法の難関の一つである「再帰動詞」は、決して古語や文語のようなものではなく日常的に使われる言葉なのだと実感できますね。 ちなみに「コメントする」のほうは「Kommentieren」で、こちらはあまりおもしろみはありません。 そして「シェアする」は「Teilen」で、こちらもすんなりと理解できます。 「いいね!」の訳として使われているというのは、普段使う表現としてとてもポピュラーだということでしょうから、「これ気に入った」というときにはどんどんと「Das gefällt mir!」と使って良さそうです。 mit 〜 befreundet Facebookで良くお目にかかるフレーズがもう一つあります。 「AさんがBさんと友達になりました」、というのがそれで、ようするにある人がFacebookを使っている友人や知人を見つけ「友達になる」リクエストをして承認されたときにこの一文が表示されるのです。 Facebookでは発信したメッセージは意図的に設定しない限り友人として設定した人にしか見えません(なので、実名で登録しても突然意図しない人物にからまれたりする心配は少ないわけですね)。 当然友達がなければただの独り言になってしまうし、誰のメッセージも読むことができません。Facebookを使っていて普段から交流したい友人や知人の存在なしには、ありがたみのないサービスです。 さてこの「友達になりました」は、ドイツ語モードでは「A ist jetzt mit B befreundet.」となっています。 辞書で調べると(まあ、調べなくても想像はつくのですが)、befreundenは「友達になる、親しくなる」という動詞です。ただし、こちらも再帰動詞として掲載されていて、過去完了の場合は「haben」と結びつきます。 したがって、このケースでは動詞ではなく過去分詞が形容詞として用いられていると考えるべきでしょう。手元の辞書には「Mit ihr bin ich schon lange befreundet./彼女とは私はもう長い間友達だ」という例文が載っています。 Facebookのようなコミュニケーションツールは、毎日のように頻繁に使われることが多くなるでしょう。 なので、こうしたサービスを外国語のモードで使うことで、実際に使うことの少ない外国語を使う機会にもなります。もちろん、メニューが外国語になっているだけではすぐになれちゃうでしょうから、学習中の言葉でメッセージを書き込んでみるのも良いでしょう。 同じ言葉を勉強中の仲間がいれば、一緒に外国語でメッセージをやりとりするようにすれば貴重の練習の場にもなります。 ぜひお試しあれ。 |

2011年3月15日 (火)
不安は続く 地震とそれに続く津波で大きな被害が出たばかりでなく、原子力発電所の状況はなかなか良い方向には向かっていないようです。 距離のある東京に住んでいても、かなり不安なのですから、近隣にお住まいのかたがたの不安感はいかばかりかと思います。現地でのプロのかたがたの活動が効果を発揮することを祈るばかりです。 地震の発生から4日以上が経過しました。 正直なところ、この間外国語の勉強はちょっとお留守になってます。なにをやっていても、なかなか集中できないのですね。 テレビでニュース映像を流しながら、ネットでもさまざまな情報を集めてはため息をついていました。 外国のニュースでは 外国の、といっても、Googleニュースで米国、英国とドイツのトピックを拾い読みしていただけなのですが、金曜から土曜にかけて地震と津波の被害の大きさについての報道が一段落したあとで、より大きく取り上げられたのは冒頭でも触れた原発の問題でした。 日本国内での報道は、不安をあおることを恐れたのか、どちらかといえば確定できた情報を伝えることを意識していたようでした。一方で、英語やドイツ語でのニュースは早くから原発の状況が大きなリスクであることを伝えていたように思います。 どちらが良いかは一概にはいえませんが、私としては、異なる見解に触れたおかげでその後の状況の悪化についてもそれほど驚くことはありませんでした。 そもそも、二重三重の安全対策がうまく機能しなくなっている状態なのですから、それほど楽観視できる状況ではなかったといえます。ニュースや政府からの発表にも、多くのかたは不安感を拭えずにいたのではないでしょうか。 国内のニュースだけでなく、海外での報道を並行して見ることで、必ずしも状況を楽観視できないことが理解できました。私はどちらかといえば物事を楽観視したがるほうですから、国内のニュースだけではどうしても理解が偏ってしまっていただろうと思います。 最初に発生した水素爆発についても、BBCなどのサイトで爆発の瞬間のビデオが流れていました。爆発の原因や性質を素人の私が判断できるわけではありませんが、安心を求める自分へのアラートには十分でした。複数の情報源を確保することの大切さを思い知ったように感じています。 多様な視点に触れる 外国語を学ぶ目的の一つに、日本語だけではない情報に触れる機会をつくることで、多様な物事の見方ができるチャンスが増える、ということがあります。 1ページ2ページのニュースを読むのにも多大な時間を要するようであれば、はじめから原発に関する海外での報道を読んでみようという気にはならなかったでしょう。 今回の原発に関しては、明らかなデマがTwitterなどを通じて流れたりもしています。そこそこ名の売れた学者さん(ただし専門外)が、かなり無責任な風説を流しているのも目にしました。 そうかと思えば、国や電力会社、あるいはマスメディアへの不信感や反発だけでいいかげんで現場で苦労されているかたがたへの配慮のない言葉を見て、不愉快になったりもします。残念ながら、ネットではこうしたネガティブなだけの情報に触れることも少なくありません。 だからこそ、外国のものを含めてさまざまな情報に触れ、専門知識や経験を持っているであろう人からの情報と、そうでないものとをきちんと区別して取り入れることが重要なのだと思います。 外国語のニュースを多少なりとも読めることで取り入れられる情報の多様性は確実に高まりました。リスニングが不得手だったこともあって、リーディングに学習が偏っているのは、コミュニケーションのためにはマイナス要因でもあるのですが、それなりにメリットもあったのだな、と感じられました。 |

2011年1月15日 (土)
毎日2章 月曜日に購入して読み始めた、iPadアプリによるドイツ語リーディング教材「Tod in der Oper」は全部で12章。ほぼ毎日2〜3章のペースで、金曜日に読了しました。 ドイツ語の小説を毎日2章なんていうととても早いかのようですが、実際には1章あたり数ページしかありません。語彙力が十分にあれば、読むだけなら数時間も必要ないでしょう。 前回も書きましたが、とりあえず意味がわかれば良い、というのではなく、文の構造がしっかりとわかるまで読んで、類推のつくものでもはっきりとわからない単語は辞書で調べながら読み進めました。 なので、通勤電車の中での30分弱で1章というのは、それほど悪くないペースだったと思います。 とにかく単語が とはいえ、その「はっきりわからない単語」が2行につき一度くらい登場します。われながら驚くほどの語彙力のなさです。 その都度、スペルを覚えてから辞書ソフトに切り替えて検索するのですが、そのたった数秒のあいだに覚えたはずのスペルが飛んでしまい、再度切り替えたりと生産性は非常に低いです。ここは、せめて辞書アプリに引き渡すためのコピーくらいは認めてもらいたいところ。 辞書に掲載されている訳語ですぐにぴったりと意味がとおる場合は良いのですが、とくに小説の場合にはそううまくはいきません。 ドイツ語の場合は再帰動詞として使われているかどうかもきちんと見ておかないといけませんし、特定の前置詞を組み合わせられた際の用法を探してようやくしっくりとくることも少なくありません。 1章にかかっている30分のうち、小説を読んでいるのは20分で残りの10分は辞書を読んでいるんじゃないか、といった状態です。 もう少し読んでみよう 今年は語彙を増やそう、というのがテーマなので、上記のような生産性の低い読み方もそれほどは悪くないでしょう。 最近めっきりと記憶力が衰えてしまっていますが、さすがに同じ単語を3回も調べればようやく次には意味を思い出せるようになります。 それでも、1週間も放っておくと元の木阿弥になってしまうものです。 ここは、同じシリーズでもう何冊か読んでみましょう。600円といえば、そう厚くない文庫本と同じ値段です。 日本語の300ページの本ならば通勤時だけでも2日はかからないでしょうから、同じ値段で楽しめる時間は倍以上という解釈もできますし。 |

2011年1月11日 (火)
書店では2000円以上 ドイツ語リーディングの教材として書かれた、とても薄くて手軽な推理小説を買ってみました。 ドイツのCornelsenから出版されている、「Patrick Reich - Privatdetektiv für alle Fälle / 私立探偵パトリック・ライヒ」シリーズの一冊、「Tod in der Oper / オペラ座に死す(かな?)」です。 章ごとに理解度をチェックする問題もついて、全部で56ページという薄さですから、初級にまだ足をとらわれている私でも途中で投げ出さずに読める分量。 しかもミステリーで舞台はカッセルのオペラ劇場と、まるで私のために用意されたような教材です。 この本、最初に見つけた書店では、2000円以上の値段がついていました。 さすがにちょっと高めだなあ、と思い、自宅のパソコンからAmazonで調べてみると約半額です。しかし、在庫が切れていて最長で4週間後の出荷になるそう。 こういうのは意欲がわいたときにやらないと、あっという間にやる気が逃げちゃうんですよね。 なんとiPadアプリが ひとまず、この本を読んで教材としての評価をしているブログなどがないものかと検索してみると、なんと同じ内容のiPadアプリがあるのがわかりました。 しかもお値段なんと600円です。Amazonで紙の本を買う半額、書店で買う4分の1近く。問題があるとすれば「iPadやiPhoneがないと読めない」ことでしょうが、これは私にはKein Problemです。 さっそく購入してインストール。 なぜかインストールに一度失敗しましたが二度目で無事に完了。さっそく今朝から「まいにちドイツ語」をちょっと中断して読み始めています。 「Eine kleine Kaffeepause」と同じく、文毎に主語と動詞の関係、関係詞の示す語などがきちんと理解できるまで何度か読み返します。意味が類推できないものはiPadに入れてある辞書で調べながら読み進むので、だいたい1章に15〜20分はかかります。すごくノロノロ。 辞書アプリとの連携はイマイチ 単語を辞書で引くのも手軽だろうと思ったのですが、ここはちょっとうまくいきませんでした。 目的の単語を選択してコピーし、辞書の検索画面で貼り付ければ良さそうなのですが、なんとこのアプリでは「コピーはできません」というメッセージが出てきます。 かわりに、選択部分をメール作成画面に貼り付ける、という機能はあるのですが、辞書を引くのに二段階の操作はちょっと面倒。結局、スペルを覚えてから辞書に切り替え、入力して調べねばなりません。 この辺は、ワンタッチで辞書の検索画面に単語を遅れるようになっていると良いのですが(読み終えたら出版社に要望してみることにしましょう)。 ただいま第5章まで読みましたが、まだ犯罪は行われていません。いかにも怪しそうな人物は出てくるのですが、肝心の私立探偵Reichさんも登場前です。 このシリーズ、全部で8作がiPadアプリとして販売されています。最初の一冊がおもしろかったら、順番に全部読んでみましょうか。ミステリー小説に出てくる単語をもとに語彙を増やして、果たして役に立つかどうかは問題ですが... |

2011年1月 4日 (火)
ただいまiPod同期中 1年ほど前からiPodの容量不足のため、CDを購入するたびに「今度はどれを外して同期するか?」に頭を悩ませていたのですが、ちょっと遅れてきたサンタクロース(別名、妻)にお願いして買い換え。 さすがに160GBあると手持ちの音楽はほぼすべて入れられます。ただいま、103GB分の音楽データを絶賛転送中、いつまでかかるかは不明ですが... これまでは80GBのハードディスクタイプと、32GBのiPod touchを併用していて、前者に音楽を、後者にはビデオと語学教材を入れていたのです。 しかしCDの増加に伴って前者はパンク、新たに買ったCDを後者に入れてしのいでいましたがさすがに足りなくなってきて、最近では容量不足のためにアプリのインストールさえままならない状態でした。 意外に快適iPod touchでの辞書 もともとiPadでドイツ語を勉強できるようにと購入した独和辞典のアプリですが、当然、iPod touch(要するに電話機能のないiPhone)でも使えます。 最初は「こんな小さな画面では」と思っていましたが、荷物を小さくしたいときにも簡単に持ち歩けるので、ちょっとしたときにも辞書が引けるのはけっこう便利です。 年末に買った本、「Eine kleine Kaffeepause」を読むのに、わざわざ専用の電子辞書やiPadを取り出すのは面倒でも、iPodならば小さく扱いやすいので簡単です。 多少慣れは必要ですが、片手で十分操作が可能なので本を閉じたりする必要もありません。 本を読みながらあまり頻繁に辞書を引くのはリズムを損ないますが、どうしても疑問ならその場で調べたほうがすっきりします。 電子辞書はスマートホンに? 電子書籍ならばiPadで読みながら辞書に切り替えて(紙の本をスキャンしているので、残念ながらワンタッチで辞書には飛べません)、という使い方ができます。 けれど、紙の本を読んでいる場合にはiPodくらいの大きさで使える辞書が実用的だということがわかりました。きっと携帯電話やスマートホンでも同じように使えるでしょうね。 音楽が入り切らなくなってこれ以上アプリを追加することも難しかったのですが、上述のとおり大容量のiPodを追加したので、touchの空き容量を増やすことができそうです。 私は電子辞書を買うたびに(といってもこれまでに2台だけですが)、「なぜ自分にとって必要な辞書を選べないのか?」と不思議に思っていました。 必要のないコンテンツがてんこ盛りの一方で、肝心の辞書はなかなか選べません。追加コンテンツとして販売されていないものも多くあります。 iPhoneをはじめとしたスマートホンやタブレット型の端末では、自分にとって必要な辞書だけを選んでインストールできます。 その多くは有料アプリとして提供されていますから追加の費用がかかるのは事実ですが、紙の辞書に比べて極端に高価でもありませんし、今後多くの辞書や教材が登場するのは間違いのないところでしょう。 携帯ひとつで何でもできるわけではないでしょうが、電子辞書は近い将来、スマートホンにとって代わられてしまうかもしれません。 |

2010年11月23日 (火)
おっと、20時を過ぎて、アジア大会での男子サッカー日本代表の決勝進出を喜びつつ、オーストラリアのエコツアーの番組を観ていたら、思い出しちゃいました。 今日は火曜日ですよね。休日だったのですっかり日曜モードです。 iPadのOSをバージョンアップ iPhoneやiPod touchはだいぶ前にOSが4.0、続いて4.1へとバージョンアップされていたのですが、iPadもようやくiOS4.2へのバージョンアップが始まりました。 私のiPod touchは2008年の秋に買ったもので、すでに2世代前ということもあり、OSのバージョンアップ後はひとつひとつの動作が一呼吸ずつ遅くなり、機能がアップした実感よりも動作がのろくなったマイナスの印象ばかりが強いです。 このため、iPadも同じようなことになるのではないかと心配していたのですが、すでにバージョンアップを終えたユーザーから「使えねー」といった声も聞こえてこなかったため、iTunesでバージョンアップ作業を行いました。 結論からいうと、今回のバージョンアップでかなり語学学習のツールとしても使い勝手が向上しています。 マルチタスクに対応したため、異なるアプリ間の切り替えが非常に簡単で早くなりました。 たとえば、ある単語の意味を独和辞典で調べたあとで、もう少し詳しく知りたいと思い独独辞典で引きなおすためには、いちど独和辞典を終了させ、ホーム画面から独独辞典を起動して、という操作が必要でした。 今回のバージョンアップ後は、画面下部にあるボタンを二回押すと起動しているアプリが一覧表示されるので、ダイレクトに独独辞典を選べばワンタッチで切り替えができるようになっています。 文章で書くとさして変わりがないようにも思えますが、実際に操作してみるとかなりの違いです。なぜ最初からこの状態で出荷しなかったのかと思えるほど自然です。 未完成な部分も ただしアプリによって切り替え時の挙動が違っているなどの問題は残っています。 たとえば、「アクセス独和辞典」は切り替えると直前の状態を維持していますが、「Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache」は語の検索画面に戻ってしまいます。このあたりは、そのうちに改善されていくことでしょう。 また、アプリ間の連携も完全とはいえません。 上記の例で書いたとおり、独和辞典で調べた語を別の辞書で調べ直そうとすると、アプリを切り替えてから再度同じ語を検索せねばなりません。異なるアプリ間で情報を受け渡す連携は、今の段階では非常に限られたものです(語を選んでコピーしておくくらいならばできるのですが)。 辞書が単独で動くだけでも非常に便利ではありますが、もともと「電子書籍リーダー」としての前評判も高く、さまざまなフォーマットのデータを表示できるiPadです。読んでいる文章中の語句を辞書で調べたいという機会は少なくありません。 こうしたときも、語を選んでコピーし、辞書アプリに切り替えて検索する、という手順を踏まなければなりません。Kindleのようなアプリでは、最初から辞書が内蔵されていて簡単に調べることも可能ですが、それはあくまでも各アプリの内部でのみ実現されているものです。 あまり高度な連携機能を求めてしまうと、パソコンと同じになってしまって動作が遅くなったりする原因にもなるのかもしれませんが、こういう「不便さ」というのは、あっという間に新しい技術によって克服されていくものです。 今回のバージョンアップで、iPadはますます「使える」語学学習ツールになってきたように思われます。Androidによるタブレットとの競争で、より買いやすく、高機能になっていくのでしょうね。 |

2010年11月16日 (火)
Twitter Twitter を始めて3ヶ月ほどになりますが、まあ、それほどたくさんつぶやいているわけでもなく、だらだらと使っている感じです。 もともとコミュニケーションが得意なほうではないので、こんなものでしょう。 日本語だけでなく、たまに気が向くと英語やドイツ語つぶやいています。以前書いたとおり、同じ140文字といっても、漢字が使える日本語とアルファベットだけの英語やドイツ語とでは書ける情報量にかなりの違いがあります。 日本語の場合、そもそも主語が省略できるし体言止めを使えばどんどんと文章量は減ります。子供のころから俳句や短歌などに親しんでいることもあって、少ない文字で豊富な情報を表現する技術に、日本人は長けているのかもしれません。 もしかすると、日本語はTwitterととても相性のよい言葉なのかな、とも思ったり。 Wein trinken ボージョレー・ヌーヴォーの解禁までもう少しですが、我が家では先日来すでにイタリアの新酒「Novello」を楽しんでます。 ボージョレーよりもちょっと安めの2000円弱で買ったのですが、新酒といってもコクや渋みも楽しめて、個性的なのがNovelloの魅力です。まあ、ボージョレー・ヌーヴォーの場合にはブドウ品種まで決まっているのですから、単に新酒だ、というだけのNovelloと比べるのはフェアではないかもしれませんが。 かなり楽しんだのでさっそくドイツ語でつぶやいてみました。 あとで見返すとどうも怪しいドイツ語なのですが、まあ、辞書も見ずに覚えている単語だけで書くのですから、多少の間違いや不自然な表現は許してもらいましょう。 むしろ、時間をかけずにさっと文章を組み立てる訓練としては、役立つのではないかと思います。 ドイツからのフォロー 書いて二日ほどして、突然ドイツから二件のフォローがありました。 フォロー主の情報を見てみると、どうやらニュルンベルクとウィーンのワインショップのようです。おそらくはときおり「Wein」などの単語で検索をして、関係ありそうならばフォローしているのでしょう。 まさか、遠い東京で日本人が思いついたようにインチキドイツ語を書いているのだとは知らないのでしょうね。 ドイツ語の勉強がてらワインの話題も読めるのは、けっこうお得かもしれません。自分の興味ある話題であれば、外国語でもわりと苦になりませんから。 あまりフォロー対象も増やしてこなかったのですが、学習中の言葉を短いセンテンス単位で読めるのは(多少、短縮のために不自然な表現かもしれませんが)、それなりによい教材になりそうです。 |

2010年10月19日 (火)
まず最初にひとこと。千葉ロッテマリーンズ、日本シリーズ進出おめでとう!!! Twitterの気軽さ 最近はIT関連の新サービスにすぐに手を出すことがなくなってしまいました。 われながらオッサンになったなあ、とため息をつきつつも、そもそも人づきあいが上手なほうでもないし、どちらかといえば話し下手。新しいツールが出たからといって、急にコミュニケーション能力が上がるわけでもないのです。 それでも、ちょっと前からTwitter は使い始めてみました。 なぜか「-」は使えなかったので、アンダーバーに変更して「d_mate」。でも、語学関連のつぶやきはほとんどありません。 WEBサイトでの表示言語をドイツ語にしているのですが、おかげで「○○さんがあなたをフォローしました」というメールももちろんドイツ語で届きます。「Follow」は「Folge」なんですな。 ブログに記事を書くとなると、一応は起承転結があるように意識するのですが、140文字しか書けないTwitterならばちょっとした感想や雑記でも問題ありません、というか、それしか書けません。 気軽に書けるので、特にiPhoneや携帯電話と相性が良いのでしょうね。あまりやりすぎるとプライバシー大公開になっちゃいそうですが。 140字は長いか短いか さて、Twitterには一回のつぶやきが「140字」という制限があります。 使い始める前は、足りないなと思っていたのですが、実際にはこれってけっこう「書きで」のある文字数だということがわかりました。 こうして書いた上のパラグラフは98文字です。 さらに42文字書けるわけで、うまく工夫すれば一回のつぶやきで十分に内容のある文を書くこともできそうです。 ところが、これは表意文字を使える言葉ならでは。英語やドイツ語でつぶやいてみると、印象はがらりと変わります。 Heute morgen bin ich um 8 Uhr aufgestanden. Es war schönes Wetter. Dann habe ich geduscht und gefrühstückt. これで107文字です。一方日本語ではどうなるかというと、 今朝は8時に起床、天気がよい。シャワーを浴びて朝食をとった。 こちらはたったの30文字。まあ、ドイツ語だってもっと短くできるでしょうから、この例で判断しちゃうのも乱暴なのですが、それにしても圧倒的な差です。 だって、「起床」と「aufgestanden bin」、「朝食をとった」と「gefrühstückt habe」と比べるだけでも、かなりの文字数の違いがあります。 漢字が使える日本語と比べると、アルファベットのみで言葉を書き表す欧米語にとっては「140字」はかなりの制限だといえるでしょう。 でも練習にはちょうど良い 別にブログには長文を掲載しなきゃならないなんて決まりはないのだから、学習中の言葉でブログを書いても良さそうなものですが、どうしてもまとまった内容の文章に仕上げなくちゃ、という意識が働いてしまいます。 私はこれまでに何度か、英文のブログにトライして、続けられずに中断しているのですが、どだい母国語と同じように加工とすると無理があるわけです。 Twitterの140文字という制限は、ちょうどひとつかふたつのセンテンスでの作文練習にはむしろもってこい。やりたくてもこれ以上は書けないのだから、気が楽というものです。 たとえば、2週ほど前にこんな風に書きました。 Jetzt höre ich 1. Sinfonie von Mahler auf Digital Concert Hall von Berliner Philharmoniker. Er ist mein Lieblingskomponist. これで124文字あります。 ほんとはこのあとに「Es ist schön, dass man jederzeit in die Berliner Philharmonie gehen kann.」くらいを続けたかったところですが、これだけで73文字もあってとても無理でした。 なので、ホントにワンセンテンスの練習です。でもこれを続けるのって、けっこう表現の幅を拡げられるんではないかと。 すでに「Twitterで英語」みたいな本がいくつか出ているようですが、別に本なんか読まなくても、とにかくワンセンテンスずつつぶやいてみるのは簡単です。もちろん、読むのだって簡単。 そんなわけで、英語やドイツ語でのつぶやき、けっこうオススメの学習法ですよ。 |

2010年9月18日 (土)
まずは録音 春先の発売以来品薄状態だったAppleの「iPad」も、いまではかなり余裕をもって買えるようになっていますね。さっそくさまざまな形で語学学習に活用されているかたも多いのではないかと思います。 今回は、私がiPadを使ってNHKラジオ講座を聴く手順について。慣れているかたには「こんなん常識じゃんか」というレベルのはなしですので、「iPadやiPhoneを使うと、ラジオ講座が聴けるのかな?」と迷っているかたがたが対象です。 音楽を聴く機能については、iPhoneなどとほぼ変わりませんから、まずはラジオ講座を録音してMP3やAACといったデジタルプレーヤで聴けるデータにするのが第一歩です。 これには、川本さんのブログにもあるようにラジオを録音できるICレコーダーを使うのが最も簡単です。タイマー録音ももちろん可能ですから、録音ができたら本体をパソコンにつないでデータをコピーします。デジカメの写真をパソコンにコピーするのとほとんど手順は変わりません。 多くのレコーダーはMP3形式で録音してくれると思いますので、iPhoneやiPadに限らずほとんどの携帯プレーヤーで聴くことができるはずです。 お次はテキスト iPad購入前までは、上記の要領でiPodに転送したラジオ番組を聴きながら、紙のテキストを読んでいました。 一ヶ月分のテキストは軽くてコンパクトなので、これはこれであまり問題はありません。しかし、アンコール講座ではテキストがちょっと厚くてかさばりますし、iPadがあるとせっかくの大画面でテキストを見ながら聴きたくもなります。 ここで登場するのは、ドキュメントスキャナと呼ばれる製品です。 小型のプリンタのような形状ですが、紙を印刷するのではなく、紙をスキャンしてコンピュータにデータとして取り込む機能を持っています。 私が使っているものでは、最大で1分あたり20枚のスピードで読み取ってくれますから、120ページ強ある「まいにちドイツ語」のテキストでもほんの数分で読み取りが完了します。 こうして読み込んだデータはPDF形式で保存されますので、iPadやKindleに転送すればそのままで読むことができます(iPadの場合、なんらかの電子書籍リーダーを導入する必要があります)。 ちなみに「まいにちドイツ語」の場合、スキャナのオススメ設定で20MB前後のデータになります。iPadならば16GB〜64GBの容量がありますので、たとえば半年分程度をため込んでもさして負担にはなりません。 スキャナで読み取る際には、本を解体する必要があります。本として綴じられたままでは、スキャンできませんからね。 このために大型の断裁機を買うかたもいらっしゃるようですが、ラジオ講座テキスト程度ならばカッターでも簡単に切れます。けがをしないように注意してください。 一度切ってしまうともう本としては読めません。資源ゴミになってしまいますが、考えようによっては保管スペースが不要になるともいえます。 iPadへ転送! さて、これでラジオ講座の音声データ(MP3)とテキスト(PDF)が無事にデジタル化できました(ちなみにNHKテキストはPDF版も販売されていますが、権利保護の関係から自由にこうした機器に転送して使えるものではありません)。 これらのデータは、iTunesというパソコン用のアプリケーションでiPadに転送します。 なお、こうしてデジタル化したデータは、もちろん自分の学習用として使うことしかできません。人にあげたり売ったりしちゃ、ダメです(当たり前ですね)。 これで、iPadでラジオ番組を聴きながら、テキストを参照することができるようになります。複数の番組を入れておけば、ドイツ語に疲れたらリトル・チャロ、さらに飽きたら実践ビジネス英語と、簡単に切り替えながら学習が続けられます。 iPhoneでもPDFファイルを表示することは可能ですので、ほぼ同じ手順で準備すれば可能でしょう。ただし、画面が小さいので私はちょっとやる気がしませんけれど。若ければ平気かも。 これで準備完了です。 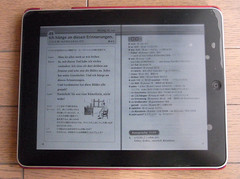 勉強したくなったらiPadを取り出し、まずiPodアプリで聴きたい回を選んで再生、続いてお好きな文書閲覧アプリでPDF文書にしたテキストを開けば、どこでもそこがあなたの学習ルーム。 まあ、街中で歩きながらやると危険ですので、電車の中や喫茶店などでどうぞ。語学講座番組は15分ほどですから、ちょっと移動時間の合間にも簡単に勉強ができますね。 写真では私が液晶保護シールを貼り損ねたためにちょっと汚いですが、実際にはとてもよく見えます。 |

2010年7月17日 (土)
Kindleとの3週間 突然の値下げ(ってことは、新バージョン登場間近?)に衝動買いした電子書籍リーダー「Kindle2」が届いてから3週間が経過しました。 いまや日本語であっても「紙の本」を持ち歩くのがだんだんいやになってきています。こうなると早くハードの日本語への対応と、日本語のほんの販売を始めてもらいたいですね。文庫や新書ならば最初から買いやすい値段なのだから、紙と同じ値段でも良いですよ。 ただ、今のところ読んでいるのは、Amazonで購入した本ではありません。 定期購読者向けにWEBで配信されている雑誌の記事をKindleの形式に変換したり、Feedbooksなどで入手できるパブリックドメインの本がほとんどです。また、「青空文庫」の作品をKindleで読みやすいPDFに変換してくれる「青空キンドル」も重宝に使わせてもらっています。 WEBよりKindle 昨日読み終えたのは、フィンランド出身の作曲家であり指揮者でもあるEsa-Pekka Salonenが作曲家グスタフ・マーラーを語ったインタビューのスクリプトです。 約12分のインタビューからの起こしなのでそう長いものではありませんが、私が普段使っている画面で10回ほどスクロールする必要があります。このくらいの長さになると、コンピュータの画面上で集中して読み続けるのは少々苦痛になります。 試しにこのインタビュー記事をKindle形式に変換して、電子書籍として読んでみました。 コンピュータの画面よりは読みやすいだろうと思っていましたが、結果は予想を大きく上回るものでした。これは「文章を読む」という観点からは全然別次元のものです。 世の中のすべてのWEB上の文章を電子書籍リーダーで読めれば、同じ文章からずっと多くの情報を読み取れるだろうと思えるほどの違いです。 まず電子書籍リーダーには余計な情報は表示されませんから、目の前の文章への集中度が全く違います。 その上、電子インクによる表示画面はずっと見ていても紙の本と同様に目が疲れにくく、長時間の読書を想定するなら、液晶画面などとは比べるべくもないほどです。少なくとも長い文章を読むのなら、私には液晶画面は考えられません。 WORD文書も 5月から毎週通っている、英語で授業が行われる大学でのグループ課題では、電子メールとファイル共有サービスを使って作業を進めます。 このファイルを読んで内容をチェックする際にも、WORD文書をKindleの形式に変換して読んでみました。 こちらも、細かな図表は別として、テキスト部分についてははるかに読みやすく、内容のチェックが短時間でできました。 おうやら、少なくとも私にとっては、文字重宝を読むのであればコンピュータの画面よりも電子ペーパーを用いた電子書籍リーダーのほうがはるかに優れた機器だといえそうです。 私が買ったKindle2では、画面サイズが文庫本と同じ程度なのでA4サイズの文書を表示するには少々狭すぎます。文字も小さくなりすぎますね。 そんなわけで、大画面のKindle DXも買っちゃおうかな、という誘惑に駆られています。 他での必要もあって、この2ヶ月ほどはかなり集中的に英語の文章を読み続けているので、英語を読むスピードがだいぶ早くなってきました。 そろそろ無料で読める文章だけでなく、小説を買って読んでみても、良いかもしれません。 |

2010年6月12日 (土)
さあ、FIFAワールドカップ 南アフリカ大会が始まりました。 寝不足が続く日々になりそうですが、日本時間で20時半から始まる試合が多いのはかなり助かります。これから一ヶ月は語学の勉強どころではないかも。 4ヶ月と11日 2月1日からドイツ語で「5行日記」をつけ始めて、早くも4ヶ月以上が経過しました。 この間、数日分をまとめて書くことはありましたが、一日も抜けなく130日間続いています。印象に残った日のぶんを5日くらい書けば良かった夏休みの宿題でさえ、最終日になってからあわてて手をつけていたのを思えば、私も大人になったものです。 突然ながら、ドイツ語で日記を書いてみる(2010.2.2) ドイツ語で日記、継続中(2010.2.16) keinとnicht(2010.3.2) 三日坊主とはよく言ったもので、たしかになにかを始めてやめてしまうときって、わりと早い段階で中断してしまうものです。 必ずしも三日とは限らないでしょうが、最初の一週間、最初の10日くらいをどう乗り切れるかが、そのあとしばらく続けられるかどうかの分かれ目になるように思います。 書けることを書く (最初の部分を書いてから、韓国-ギリシャ戦が始まり、45分間中断) さてこのドイツ語日記、2月からのをざっと眺めてみたのですが、書いている分量は始めた当初からほとんど変わっていません。 おおむねセンテンス数で6〜10、多くても100語程度です。毎日書くのにかかる時間は15分から20分程度です。 このくらいの時間ならば、お昼休みにでも、あるいは帰宅後でも、さっと書けます。 逆にこれ以上の時間、30分以上を要するようだと毎日書くのは大変ですし、きっと続かないでしょう。たくさん書こうとがんばるのはかえって逆効果かもしれません。 15分で終わらせる秘訣は、「書けないことは書かない」です。 たとえば映画を観て、「家族の信頼感について考えさせられた」なんていう感想を書きたいとします。でも、これをドイツ語で表すのは、いまの私にはそう簡単なことではありません。 ここで文法解説やら辞書やらをひっくり返しながら適切な表現を探すことも可能でしょうが、それでは時間がかかってしまいます。 日本語を一度忘れて、「Das ist ein Film über das familiäre Vertrauen und sehr interessant.」くらいに言い換えます。これなら、「信頼感って、どういうのかな」と辞書を引けばすみますね。 Twitterも ちかごろ英語でTwitter、なんていうのも話題になっているようです。 長い文章とは違って、とりあえずワンセンテンスですませられるのもお手軽。その場で思ったことでよいので日記よりもさらに気軽に書けますね。 私も少し前からつぶやき始めたのですが、日本語だけでなく、英語とドイツ語も使います。ワンセンテンスなのでそんなに苦労はないし、まあ、多少間違ってもいいや、と思える気軽さがあります。始めてからしばらくのあいだは設定画面で使用言語をドイツ語にしておいたのですが、「○○さんがあなたをフォローしましたよ」という内容のメールがドイツ語で来るようになったので、慌てて日本語に戻しました。 ちなみに「Follow」は「Folgen」だそうです。 おっと、韓国-ギリシャ戦の後半が始まってしまいました。立ち上がりから韓国のチャンスが続いて目が離せません。 日記は「Evernote」という、文章やWEBのメモなどさまざまなデータを登録できるパーソナルデータベースに登録しておけば、どのマシンからでも同じように使えます。 Twitterなら、外出先でiPodやPDAからも読み書きが可能です。 ここでパク・チソンが相手パスを奪ってビューティフルゴールです。 いや、ダメですね。試合を観ながら書いてても。 まあとにかく、毎日短時間でも聴く・読むだけでなく、話す・書くといったアウトプットの時間を確保するのは、きっと役立つと思います。 |

2010年5月 8日 (土)
フィンランド語トラベル用語 トラブル用語、じゃありません。トラベル用語です。 前回も書きましたが、オンラインの学習サイトでの単語とフレーズの反復訓練を、ちょうど4週間前から始めています。今日までに28日間でトータル学習時間は約9時間半だそうですから、平均すると毎日20分程度になります。ちりも積もれば山とはこのこと。これまでにドイツ語とフィンランド語をあわせて109単語を「学習完了」したことになっています。もっとも、ドイツ語57単語のうち、半分以上は既知の語でしたけど。 一回あたり10語を学習すると、フィンランド語のように未知の言語だとはじめは15分ほどかかりますが、学習が進んで記憶の確認が中心になってくると5分以内で終わります。 したがって、お昼休みにもできますし、帰宅後に夕食の前、お風呂の前にちょっとだけ、という細切れ学習が可能なのが特長です。憶えたと思った語が久しぶりに出題されると「あれれ、なんだっけ?」となることが意外に多く、反復訓練の有効さが実感できます。 フィンランド語は「トラベル用語」なるゴールを93%まで完了した段階です。78語のうち52語が学習完了、つまり「まあ今のところはちゃんと憶えてます」というところ。一日あたり2語に満たないスローペースではありますが、単語帳とにらめっこするよりもずっと効果的なのはたしかです。 最近は、通勤時に駅に到着すると「rautatieasema(鉄道駅)!」、券売機が目に入ると「lippumyymälä(切符売り場)!」、通過電車を眺めながら「pikajuna(急行列車)!」、電車に乗りながら「juna(列車)!」などとつぶやいてます。 次の学習は48時間後 最初の3週間は毎日のように「次回の学習:今がオススメ」となっていたので、「これっていつもじゃないか」と思いつつ学習を繰り返していたのですが、ある日突然「次の学習:48時間後」なる表示が。 つまりは、「とりあえず憶えてきたようだけど、2日もしたら忘れるだろうから、その頃再開してね」ということです。この学習アプリ、ほんとに良くできてます。現に、上記のように復習していた単語以外は、時間をおいて復習すると思い出すのに一呼吸が必要です。おそらく数週間も放置したらほぼ完全に忘れてしまうでしょう。 年齢や記憶力にもよるでしょうが、短期集中で学習すればある程度の単語やフレーズを頭に詰め込むことは可能です。 語学に限らず、中学高校大学と、試験前に知識を詰め込んで合格点を取り、あっという間に忘れてしまうことを繰り返しながら生きてきました。きっとみなさんも大なり小なり、身に覚えがあるのではないでしょうか。試験前でなくても、毎日繰り返し繰り返し、休まずに勉強するのが効果的だと教えられてきました。 なので、学習アプリが「今日は勉強しちゃダメだよ/やってもムダだよ」というのは画期的なことではないかと。 学習アイテムの追加は少しずつ 同時にスタートしたドイツ語のほうも、89%まで終了して同じように「しばらく間をおけ」といわれています。 そこで、新たにフィンランド語の基礎フレーズを学習アイテムに追加しました。前回のものは名詞ばかりでしたが、今回は動詞や形容詞なども含まれていて、今のところは「うへー、こんなの憶えられないよ」と泣き言モードに逆戻りです。 でもきっとだいじょうぶ、「トラベル用語」だって最初はそうでしたから、信じて繰り返せば、数週間後には半分以上が記憶に残っているはず。そうなれば、フレーズの単語を入れ替えながら使える表現が少しずつ増え始めるはずです。 とはいえ、ここで調子に乗って学習アイテムを増やしては、どれも消化不良になること間違いなし。しばらくは各言語ひとつずつを、順番に終了させていくくらいが良いでしょう。 これは参考書や問題集についても言えていて、学習のはじめにはついあれもこれもと手を出してしまいがちですが、結局きちんとできるのは少数です。よほどあわないのならともかく、選んだ教材をひとつずつ確実に終わらせていくことが、着実に前進している実感につながります。 思えば、受験のために勉強していた頃(ずうっっと昔ですが)にも、問題集は各科目につきひとつだけ(選択の基準は、「問題部分と同じくらい、解答と解説部分が厚いこと」でした)と決めていた科目は成績も良かったのでした。 少しずつといいながらも、NHKのラジオ講座(今シーズンは「まいにちドイツ語」と「実践ビジネス英語」)、テレビの「EURO24」、ドイツ語教室のテキスト、そしてオンライン学習サイトと、使う教材は思いのほか拡がってしまっています。 しばらくは新しいことに手は出さずに、いま取り組んでいる教材にしっかりと集中するのがきっとよさそう。でも、新しもの好きなんで、ついつい目新しい教材を見つけると手を出しちゃうんですけどね。 |

2010年5月 4日 (火)
GWはいかがお過ごしでしょうか? 私の別のブログではアクセス数がわかるのですが、それによるとだいたい大型連休中は普段の半分以下しかアクセスがなくなります(もっとも、今年に関していえば、このところ更新をサボっていることも原因でしょうけど)。つまり、みなさんパソコンの前なんかには座っていなくて、どこかへでかけているということですね。 私は映画をふたつ、ミッフィーの原画の展示会にでかけたくらいで、遠出はしていません。自宅でも録画してあったものなど映画を5つ観たので、一応は「GW中は映画三昧でした」くらいは言えそうです。 苦手な苦手な単語の暗記 さて、年齢を重ねると丸暗記というのは苦手になるものですが、実は私は十代のころから苦手でなりませんでした。なんの脈絡もなく、出てきた単語や熟語を記憶するというのが苦痛だったのです。 それに、こんなこというと叱られるかもしれないけど、丸暗記ってなんだかバカっぽじゃないですか。何も考えず、疑問も持たずに目の前に出されたお皿を平らげているようで...級友が「試験に出る英単語」なんかを最初の「intellect」から順に暗記しているのを見ながら、その輪に加わることもありませんでした(「出る単」一応買ったのだけど)。 子供のころから嫌いなことは徹底してサボり続けたためか、大学受験をはじめとして、至るところで語彙力の不足に悩まされ続け、未だに解消していないのは、何度かこのブログにも書いたとおりです。 後から考えれば、嫌だろうが苦手だろうが、中学高校の時期に詰め込んでおけば良かったとは思います。その証拠に、あのころ覚えた単語の多くは未だに忘れていませんし、日常会話では中学高校で習う単語だけでも十分なほどの分量もありました。 でも、後悔先に立たず。 よって、新たに始めたドイツ語では、地道におぼえていくしかないのですが、こちらも単語帳をつくって...という暗記方式はやっぱりできなくて、テキストやラジオ講座に登場した単語を使いながら語彙に加えていく、というはなはだ時間のかかるやり方に終始してます。 オンラインの学習サイトで 先日の記事でもちょっと触れましたが、少し前からオンラインの語学学習サイト「samrt.fm」を使い始めています。 あまり欲張ってもしかたがないので、いま学習中なのはドイツ語とフィンランド語の「ゴール」(学習用の単語やフレーズの「束」をこう呼んでいるようです)をひとつずつ。特に後者については、まったく未知の言語だけにほぼ「単語の丸暗記」状態となっています。 学習ソフトが良くできていて、まず単語と訳、あれば例文が表示されてスペリングの練習をしたあと、おぼえたかどうかが次々とチェックされます。まずは訳語を4つないし8つの候補から選び、次に日本語から該当する単語を4つの中から答え、最後は正しいスペルでタイプできるかどうかが試されます。 これを立て続けにやれば、短期的に正解はできるでしょうが、ポイントはさまざまな単語がランダムに出てきて、しばらくたって忘れたころを見計らってタイピングが求められるところ。見事なほどに忘れていて、最初の一文字さえ出てこないことも少なくありません。 それでも5回10回と繰り返すうちに、だんだんと記憶に残ってくるから不思議です。 でもやっぱり丸暗記は苦手 それでも、やはり単語間の関係や脈絡もなく、ひとつずつ順に暗記していくというのは、決して得意ではありません。やはり、単語を構成する要素が共通しているもの、既に知っている言語と似通っているもの(これが少ないので、フィンランド語は余計に大変)のほうが、理解も記憶も早くなります。 一例を挙げましょう。 フィンランド語で「往復切符」は「menopaluulippu」です。さて、これを単独ですぐにおぼえられますか? 無理ですよね?(「軽いよ!」というかたは、うらやましいです) いきなりこんな長い単語、当然おぼえられずに四苦八苦しました。けれど、少し進んでいくうちに、今度は「片道切符」が登場したのです。今度は「menolippu」。そして、ほどなく「航空券」というのも出てきました、「lentolippu」です。 こうしてうまくつながり始めると、記憶の回路がうまく回り始めます。 上記の3つの単語の共通点は、「lippu」ですね。おそらくこれが「切符」とか「チケット」という意味なのは確実です。 そして、全2者には「meno-」という共通の要素があります。「片道切符」が「往路の切符」のことであれば、おそらく「meno」は行き、そして「paluu」が帰りではないか。 手許にはフィンランド語の辞書がないので、Google翻訳に登場してもらうと、「meno」は「expenditure」「going」「go」といった意味で、「paluu」は「return」「comeback」といった意味だとあります。どうやらビンゴでした。したがって、帰路のみの片道切符は「paluulippu」で良いはず。 「lentolippu(航空券)」のあとには、「lentokenttä(空港)」「lentokone(航空機)」などが出てきました。 トラベル関連の単語集だったので、相互に関連することばがわりと早めに出てきますから、単なる機械的な暗記なのは最初の数回だけ。次々に単語同志がつながり始めます。こうなると、だいぶ錆び付いてきた記憶力も、なんとかやる気を出すようです。 短くて良いんじゃ... この「smart.fm」で注意すべき点があるとすれば、学習用のゴールはユーザーも参加してつくれる、ということでしょう。手持ちの参考書などからピックアップして単語やフレーズを登録できるので、場合によっては実際に使われている言葉とずれる可能性もあります。 たとえば、私が苦労しておぼえた単語に「sisäänkäynti(入口)」と「uloskäynti(出口)」があります。共通の要素である「käynti」は、Google翻訳によると「visit」「call」といった意味なのだとか。そして、その前の要素は「sisään」が「in」で「ulos」が「out」だそうです。 でまあ、なんとかおぼえましたよ。いまこの記事を書いている最中も、ちゃんと上記の単語は記憶に頼って書き、あとで確認したらちゃんとあってました。 でもね、ためしに「sisään ulos」で検索をかけてみると、なんとこのふたつは後ろの「käynti」なしでも、それぞれ「入口」と「出口」で通じるのだとか。がーん、わざわざ難しいのおぼえちゃったよー ま、こんなこともあるわけですが、なにも間違いをおぼえてしまったわけではありません。 フィンランド語については、なんとしても話せるようになろうというよりは、将来旅行にいった際に(フィンランドは近いうちに必ず行きたい国のひとつなので)、多少は話せたほうが楽しいだろう、という程度です。厳密さは要求しませんし、許容範囲でしょう。 本気で取り組みたくなったら、そのときに修正すればよいわけで。 昔は(なんて書くと年寄り臭いですね)、ノートに何度も書いたりするしかなかった単語の暗記が、いまではPCや携帯電話を使って、手軽に、しかも効果的にできるようになっています。 記憶力が減退したぶんは、こうしたハイテク(?)で補えるわけで、前は苦痛でしかたのなかった単語の暗記も、心を入れ替えてちょっとずつ取り組んでいこうと思ってます。なにせ、ある程度話せるようになったら、あとは「いつでも使える引き出し」に入っている表現の量が、重要ですから。 |





