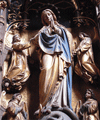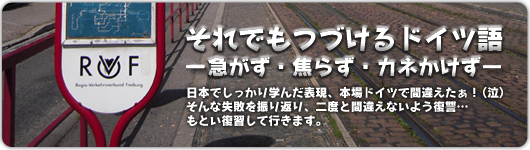
2011年5月27日 (金)
Guten Morgen! Wie geht's?
Lorenz von Stein 伊藤博文がヴィーンで教えを請うた法律顧問
日本の人たちの生き方に極めて独特な個性を与えているものが5つある としてシュタインは独自の見解を述べているのですが、オオトリがこれ:
古い全く不合理な日本の文字に替えてアルファベットを導入しようとしている 最近の羅馬字会の運動がすみやかに成果を収めんことを熱烈に希望して
出たー(≧▽≦;) これが噂の羅馬字会っ!(って初めて知った)
漢字廃止どころか,日本語を廃止して英語を公用語にすることを提唱した初代文部大臣
出たー(≧▽≦;;) とまぁ、今ここでジョークに出来るからいいものの。ねぇ。
たまに院のゼミで話題に上ってましたけど、その時は「ふーん」てなものでして、 でも今、改めてここで文字にしてみて、 「それがなぜいけないか」を明確に意識することが出来るようになっていた自分を 自分で誉めたいと思います。よくやった☆ Kando-shita☆ Aho-chauka☆
しかしドイツ語って難しいね。知らない分野=知らない単語⇒知らない言語。
あと、見開いて右側に優れた日本語訳が載っているんでどうしてもそっち見ちゃうけど ドイツ語と日本語の構造的な違い、と書くと難しい議論に聴こえるけどそうではなくて ドイツ語の良さってこういう文章になると特に出て来るよなぁ、と思いつつ眺めてました。 |

2011年5月26日 (木)
Guten Tag! Wie geht's?
Hermann Roesler 明治憲法草案を書いたドイツ人 1888年
合ってるかな、自信ないけど、
Bleiben Sie harmonisch, bis zur nächsten Forge.
Prof. Zöllner の最後のお言葉、イイな~とメモっといて再放送を聴いたら、 そっか、これがキーワードだったんですよね。
Harmonie
好ましいことではないかもしれませんが 巻末のフリートークのスクリプトから日本語の部分を転記させていただきます。
テクストでのレースラーの立ち位置はどのあたりにあったのでしょう?
レースラーが依拠したのはドイツの国家法で,ヨーロッパの中では特殊なものだった。 フランスやイギリスではリベラルな法ができていて,政治の中では競争的な戦いが 想定されていた。誰もが誰に対しても戦う,それを収めるのが法である,というわけだ。 それに対してドイツでは,競争的に戦うのではなく調和的に済ませられる可能性を信じた。 レースラーやシュタインは,国家を一つの体と見なし,体の各パーツはきちんと体が動くよう それぞれの仕事をすべきだ,という考え方を持った。 このモデルを日本人は喜んで取り入れた。
Staatskörper (国家という身体)
今の日本のそれを形容するイイ表現を日本語ででもひねり出したかったのですが ダニエルの口癖しか思い浮かばなかった(^_^;)
ボロボロ |

2011年5月20日 (金)
Guten Morgen! Wie geht's?
Franz Eckert (2) 君が代が誕生するまで 1880年
今日の放送、お聴き逃しなく! 午後の再放送&次週ストリーミング、必聴です!
「君が代」候補がいくつもあったなんて全然知らなかったですし、 「君が代」雅楽バージョン、昨日の放送をふまえて聴くと感動しますよ。 「君が代」って、日本の国歌にしかなり得ない音楽だったんだ! って。
そしてそれを生み出したのがドイツ人だということに、ますます感動しましたね。 やっぱり日本人の「音楽」とは「ドイツ」との縁(えにし)ありき、だったんですね。
この感動、うまく伝えられないんですけど、とにかく、とてもイイ放送でした。
Übrigens: 没後100周年のマーラーですが、 流行ってるものは遠ざけたくなる天邪鬼でして(だから『ロン○ケ』とかも観たことないの) でも昨日これ聴いててなんだかむずむずしちゃいました。すごいイイと思った。 Gustav Mahler: Klavierquartett a-Moll Ludmilla Berlinsky (Klavier) Mitglieder des Borodin Streichquartetts SWR2 Mahler-Zyklus なんてのも企画してくれてたのに、もったいないことした。
今やってるのはコレ: Die Schwetzinger SWR Festspiele in SWR2 夜ライヴ放送してるんですけど、オンデマンドで聴けるみたいです! 特に17日のチェロとクラヴィアの回、イイ曲ばかりで悶絶しました! アンコールで思わず「おぉぉぉぉ(≧O≦)」と叫んでしまった。 Ernest Bloch: "Prayers" aus "From Jewish Life" お時間のある方、ぜひぜひ聴いてみて下さい。ダウンロード出来ないのが残念至極... |

2011年5月19日 (木)
Guten Tag! Wie geht's heute? Mir geht es besser, und meinen Pflanzen auch!!
今日の放送はあっという間でした。再放送もしっかり聴かないと。
Franz Eckert (1) 日本音楽と西洋音楽とのはざまで 1880年頃
現在の私たちの頭にはドレミファソラシドというヨーロッパ生まれの音階が 当然のように刷り込まれていますが,江戸時代には全く別の音階で歌われていました。 日本音楽はしばしばファとシの音を書いた「四七(よな)抜き」の五音音階(Pentatonik) であるだけでなく,一つ一つの音の高さも微妙に揺れていますから, 日独が出会って互いに相手の音楽を初めて聞いたときには, 大きなカルチャーショックだったに違いありません。 (テキスト85ページから抜粋)
現在の日本人の「音楽」とは「西洋」のそれであって決して「日本」古来のそれではない ということに気付かされたのが三十路を超えた頃というのがなんともはや情けなや。
今まさに流れているクラシック音楽にしたって五線譜上にキレイに乗っかれるものであって 五線譜上にキレイに乗っかれない雅楽や浄瑠璃の方がアタラシイ感じがしてしまう。
しばらくご無沙汰していますが5年ほど文楽を聴きに通って相当「聴いた」はずなのに 歌えない。あの独特の旋律を文字通り「身に付ける」のはもはや不可能に近い。
先日ご紹介した『蓼喰う虫』の中には ハイカラな江戸っ子「美佐子」の習っている「長唄」と 古風な京女「お久」の習っている「地歌」と 両方出て来るのに結局聴き比べることなく終わってしまった。
そういう経験をもとに今日の放送を聴いて感じたことは 昨年度の「短歌をドイツ語で」の際にも感じたことですが
このエッカートという人の素晴らしい才能と惜しみない努力に対する賛美、そして 日本語の奥深さ、でしょうか。 「端唄」の「春雨」、とてもイイと思いました。どうイイかを日本語で表せないくらい。 ぜひ、今日の再放送を、来週のストリーミング放送を、お聴き下さいませ。
今まさに流れてい「た」クラシック音楽はちなみに: Johannes Brahms: Klarinettenquintett h-Moll op. 115 Chen Halevi (Klarinette) Keller-Quartett Johann Sebastian Bach: Violinkonzert a-Moll BWV 1041 Daniel Hope (Violine) Chamber Orchestra of Europe |

2011年5月13日 (金)
Guten Morgen! Wie geht's?
Max von Brandt 北海道はドイツの理想的な植民地!? 1865/67年
O nein. Unmöglich. Aber,
2011年2月5日の朝日新聞は,「戊辰戦争でプロイセンに提携持ちかけ」と題して, 1868年の戊辰戦争のさなか,明治政府と戦う会津・庄内の両藩が蝦夷の分領地を ブラントに売却しようとしていたことを示す資料が発見されたと報じました。
Was?
1859年,幕府が東北地方の6藩(南部・仙台・会津・津軽・秋田・庄内)に対し, 蝦夷の各地をあてがい,「分領・分治」するように命じた
Ach... das wusste ich nicht... (Meine Heimatstadt hat 庄内藩 gehört...)
Heute besuche ich wahrscheinlich die Kathedrale St. Marien. Hoffentlich kann ich euch morgen einige Fotos zeigen. Also, bis morgen♪
|

2011年5月12日 (木)
Guten Tag! Wie geht's? Mir ist heute ganz kalt...(;_;) Mir wird morgen ganz heiß!? O nein! (>_<) Mir werde ではない、ですよね、主語は es ですもんね、姿が見えないだけで...
Japanische Gesandtschaft in Berlin サムライに大騒ぎするベルリン子たち
Berliner Allgemeine Zeitung も Professor Zöllner も超ノリノリだったのに あまりの寒さに...じゃなかった あまりの難しさにイマイチノリきれませんでした...
そう、互いに好奇心むき出しなんだけど、全体としては好意的なんですよね。 ここらへん、ドイツ&ヤーパンの相性の良さを感じますよね。
窓から銅銭を投げてやるなんてなかなかやるなぁ、サムライも(笑)
ぱおきちさんが、今夜のSWR2の「ヨハネ受難曲」のライヴ放送を教えて下さいました。 詳細はこちらでどうぞ。Vielen Dank, ぱおきちさん☆
うー、ホント寒いですね。反対に明日は思い切り暑くなるとのこと、 体調管理が難しいところですが、気を付けて乗り切りましょう。Bis morgen♪ |

2011年5月 6日 (金)
Lange nicht gesehen! Wie geht's dir heute? Und wie war deine Golden-Week? Ich wollte die zwölf(!) kleine Gemüse in den Kästen einpflanzen, aber leider konnte es noch nicht, denn die Temperatur war zu niedrig. Wir haben unser kleines Garten geputzt, sind kaum ausgegangen, und... hm, ich habe nichts besonderes gemacht... Ach ja, die Golden-Week ist noch nicht fertig! Viel Spaß bis zum Wochenende! お久しブリーフ! 元気ですか? GWはいかがでした? 私といえば、12人(!)の野菜の苗達をプランターに植え付けたかったんですけど まだ出来てませんのです、気温が低過ぎて。 ちょっとだけ狭庭を整備して、ほとんど外出もせず... 「GW、これやりましたっ!」ってこと、なんもないな... いやいや、まだ終わってないよ、GW。週末までしっかり楽しみましょう! ってゆか世のお母さん方もお父さん方もそろそろもうウン●リしてきて 今日辺りほっと一息ついてたりするんじゃない? とかこゆマズイことはドイツ語で書きたいんだけど書けない(^_^;) 最後の一文はかなーりアヤシイです。たぶんマチガイ。なんかイイ言い方ないかな。
Guido von Rehfues 難航する条約批准 1864年
「批准」という日本語の意味を知ってる自分エライと思ってしまった自分だいじょぶか。 でもって このドイツ語は「批准する」という動詞ではなかろうかと推察出来た自分エラカッタけど それ以外の約85%ちんぷんかんぷんの自分ちっともだいじょばない。 GW明け一発目だからさ~ってそゆ問題じゃなさそうです(汗)
あれま、最初のページの2行目にちゃんと出てますね、「Ratifizierung」。 だから推察出来ただけだったりして...いやいや、そんなことはない。はず。
ここまで話が難しいと、せっかく近付き始めた 「少しだけ聴き取れるドイツ語」から 「まったく聴き取れないこれは何語?」へと逆戻りしてしまいそうになるけど ここはしっかり踏ん張って。
さてと、レッスンの準備すっかな。Bis Morgen!! |

2011年4月28日 (木)
Guten Morgen! Wie geht's? Hast du in der Golden-Week schon etwas vor? 「ゴールデンウィーク」に対応するドイツ語は存在しないのでまんま 「Golden-Week」で良い、とダぁニエルが言ってました。
Henry Heusken und Hori Toshihiro あぶなっかしい条約締結 1861年
ほんと、あぶなっかしい...いやむしろ「アブナイ」わけですよ、だって タイトルにある Henry Heusken は プロイセン使節団のために通訳者として使えたオランダ人ですが, 1861年1月14日の夜,攘夷を唱える侍たちに襲われ,命を落としてしまいました。 おまけに プロイセンとの条約交渉を取り仕切っていた堀利熙が突然切腹してしまったのは,... ですよ。「歴史から消された名前」というわけですよね...
Preuszen : Preußen の ß を文字どおりエス・ツェット(s+z)で表記したもの 「ß」ってだから「エス・ツェット」って読むんだ~(☆0☆)20年間ずっと知らんかった~
そうそう、この「ドイツ語が見てきたNIPPON」も2カ月目に突入したわけですけど 5月号のラインナップ、ご覧になりました? おもしろそうよ~! 知りたい? しょうがないな~。じゃ、68ページを転記したげますわ。
今月取り上げるのは・・・
9 Henry Heusken und Hori Toshihiro ・・・ あぶなっかしい条約締結 ペリーが来航して日米和親条約が結ばれて以来,次々に国交を求める諸外国に続いて ドイツ,当時のプロイセンの使節もやってきました。
10 Guido von Rehfues ・・・ 難航する条約批准 プロイセンとの条約はようやく結ばれたものの,批准手続きに訪れた使節団と幕府の間には 大きな軋轢が生じます。
11 Japanische Gesandtschaft in Berlin ・・・ サムライに大騒ぎするベルリン子たち ヨーロッパ諸国との条約締結の後,日本から初の使節団が派遣されました。 初めて日本人を見たベルリンの人々の反応はどうだったでしょう?
12 Max von Brandt ・・・ 北海道はドイツの理想的な植民地!? 後に駐日ドイツ帝国全権公使となったフォン・ブラントは,明治維新直前に当時の蝦夷を訪れて, どのような感心をいただいたでしょう?
13 Franz Eckert (1) ・・・ 日本音楽と西洋音楽とのはざまで 明治政府のいわゆる「お雇い外国人」として西洋音楽を紹介したエッカートは, 日本の伝統的な音楽に深く興味をひかれます。
14 Franz Eckert (2) ・・・ 君が代が誕生するまで エッカートが関わった日本の国歌を作る作業は,困難と試行錯誤の連続でした。
15 Hermann Roesler ・・・ 明治憲法草案を書いたドイツ人 近代国家としての法整備に特に影響を与えたのはドイツの法律でした。 政府の法律顧問レースラーは,国家の根本的な体制について述べています。
16 Lorenz von Stein ・・・ 伊藤博文がヴィーンで教えを請うた法律顧問 日本の憲法制定にあたり,調査のためヴィーンに滞在した伊藤は, 法律の第一人者フォン・シュタインに助言を求めます。
ね? 歴史ギライの私でも、早起きして聴くぞ~って気になりますわよ。
さて、明日から黄金週間に突入ですが、皆様ご予定は? えっと、私は... Wir müssen unbedingt eine Gurke, eine Eierpflanze, zwei Paprika und fünf(!) Tomaten in die Töpfe einpflanzen. Ach ja, vorher müssen wir Komposterde kaufen gehen. とにもかくにもキュウリとナスとピーマンとトマト五人衆の植え付け。 あーそーだ、その前に培養土買いに行かないとだ。 「ナス」はすぐ出たけど「培養土」が出なくて困った。これで通じるかしら。 müssen は次回の「テレビでドイツ語」の動詞24。
Am 6. Mai fängt unser Deutschunterricht wieder an, deshalb schreibe ich ab diesem Tag wieder diesen Blog. Also, bis dann, schöne Golden-Week! 5月6日からドイツ語レッスンが再開するので、私もここ「は」その日から再開します。 では、ステキなゴールデンウィークを♪
追伸: Heute habe ich zum Frühstück deutsches Brötchen gegessen. Eine Brezel, natürlich, und eine Nussschnecke. Ganz lecker!! Aber... wie liest man dieses Koreanisch...? つづきは「おぼえた日記」で!
自分への追伸: GW中も時々は「おぼえた日記」書くぞ! 書くぜ! 書くか?
追追伸: |