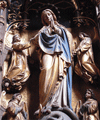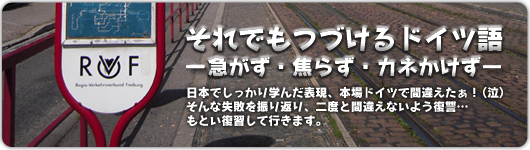
2009年2月 3日 (火)
Hallo! Ich bin 'maringe'. Wie geht's? はろー! 「まりんげ」です。お元気ですか?
皆さん、ゴガクルのクリスマスカード&年賀状、お使いになりました!? マックスのカード、めちゃくちゃカワイかったですよねー☆
そう、私は今年度上半期の「テレビでドイツ語」が大好きだったんです。 ロマンチック街道は十代の頃からの憧れの場所。実はこの初回放送を観て 「そうだ、ロマンチック街道へ行こう!」と決意したんですよ。
昨夏はフランクフルトからヴュルツブルクに直行。 宿をとってゆっくり観光し、ローテンブルクへも日帰り旅行しました。 いやー、楽しかった...
が! ローテンブルクでもやってしまったんですよ、聖ヤコプ教会で。 見学料を払う時、写真撮っていいか一応聞いとくか~と自信満々でひとこと。
KANN ich hier fotografieren?
さすが観光地。受付の女性は「もちろん。でもフラッシュは無しでね」と にこやかに答えてくれましたが、内心ではこう思っていたはず。
(なぜ私に聞く?)
...冗談です、親切そうな人でした。でもいきなりこんなこと聞かれてもねぇ。
私はここで写真を撮れますか?
そりゃあ撮れるだろうよ、カメラ持ってんだから! あんたいったい何べん練習したの、このフレーズ! レッスンでも習ったし、石井クンが練習するの見てたでしょうが! 正解は、
DARF ich hier fotografieren?
んもう、ich を man にすべきかどうかってレベルじゃないですよ。 帰国後、先生に懺悔しました...とほほ。 お詫びに、その時に撮った「聖血の祭壇」の写真をどうぞ...
|

2009年2月10日 (火)
Wer bist du denn? ということで、遅れ馳せながら自己紹介をさせていただきます。 ...別に知りたくない? いや、でも、ドイツ語の学習歴くらいは お伝えしておこうかなーと思いまして。
プロフィールにも書きました通り、私は現在ドイツ語「リベンジ」中です。 なぜ「リベンジ」か。それは...
大学在学中の4年間ずっとドイツ語を学んでいたのに、 ドイツ語が全く話せなかったからです!!!
...こんな大きな声(!×3+太字)で言うことではありません、お恥ずかしい。 でも第二外国語が必修だった「元」大学生の皆さんならおわかりいただけるでしょう、 当時の第二外国語は文法と読解がメインでありまして、 聴く・話すというテクニックについては自主的に学ばないと身に付かないものでした。
いえ、ここで大学のカリキュラムについて議論するつもりは全く無くて、私の話。 もう少し遡って言えば、中学・高校の「英語」の成績はまあまあ良く、 それを活かして大学に滑り込んだわけですが、入ってからが大変だったのです。 1年生と2年生は週4コマあったんですよ、英語の授業が。読・話・書・聴、の4コマ。
当時の大変さについて語るとまた長くなるので、ひとことで言います。
ぜんぜん聴き取れない!!! ぜんぜん話せない!!!
あれ、ふたことになっちゃった。まいっか、それより 問題はドイツ語にあったのではなく、英語時代から抱えていたものだったのです。 18歳までの私にとって、外国語とは「勉強するもの」、つまり 「与えられた問いを読み、そこから答えを導き出すもの」、でした。
でも違った。外国語も日本語と同じ、コミュニケーションのツール。 相手の意思を聴き取り、自分の意思を伝えるために習得すべきもの、だったのです。 でも当時の私には、それを自主的に習得しようという意欲も動機もありませんでした。
社会人になり、生活もマンネリ化してきた頃、ふと思ったんです。 「十代の頃に考えてた『なりたい自分』って、どんなんだったっけ?」 |

2009年2月13日 (金)
「なりたかった自分」、それは 「外国語が話せる自分」、でした。
なぜって? うーん。なんとなくです。この辺り、もう限界が見え隠れ(汗)。
それはともかく、その「外国語が話せる自分」に少しでも近付こうと 外国語の「リベンジ」を始めたのですが、最初に取り掛かったのは 実は「英会話」だったのです。ドイツ語会話じゃなく。
当時は勤め人でしたから、外国語といえば英会話。 それに英会話は実に様々な学習ツールがありますから、 三日坊主な私にもピッタリなものが見付かるのではないかと思ったのです。
リベンジ・スタートに際し、私は強く心に決めました。
受験英語のような勉強スタイルには絶対に戻らないっ!!!
具体策: A.辞書を引かない B.日本語に訳さない C.間違いを恐れない
ふっ、何をいまさら...という感じですよね。 でも、私にとっての「外国語学習」は、この3つが全てだったんですよ。
それら3つの封印を決意した私は、「受験英語」ではない、「英会話」を学び始めました。
my英会話・三段跳び: 1.書いていい...わけないか、いま日本で一番人気のプロゴルファー君のアレです(笑) 2.NHKのラジオ講座 3.オープンカレッジの英会話レッスン
英会話を学んでいた頃の自分が何をどう感じていたか、今となっては忘却の彼方ですが、 初めてレッスンに出た時の衝撃だけは忘れられません。
うわー、先生、日本人なのに、英語しゃべってるよー!!!
スゴイでしょ~。笑えないよな~。冷汗だよな~。 でも、受験英語が得意だったからこその「弊害」ですよね、これって。 だって、それまで習った先生は全員日本人だったんだし、 C.の克服を実感できるまで、丸2年かかりましたもの。丸2年ですよ。
そして英会話リベンジから3年目、 今ならドイツ語を学び始めても大丈夫かもしれない!と根拠の無い確信を抱いた私は ドイツ語レッスンのクラスへと足を踏み入れたのでした... あ、ちょっと待って、
<教訓> B.と C.を克服したら A.もちゃんとやるべし
さもないと、私みたいな「ボキャ貧」になってしまいますぜ(泣)。 |

2009年2月17日 (火)
前回の復讐。じゃない、復習。最初の変換で「復讐」が出るうちのパソコンって...
A.辞書を引かない B.日本語に訳さない C.間違いを恐れない
日本人なんだから日本語で考えるのが当たり前だし 単語の意味がわからんかったら語学にならんだろうが
おっしゃるとおり。って誰としゃべってんの。 でも、私は敢えて、この3つを封印しました。これこそが「壁」だと思ったからです。
a.意味の分からない単語は全て辞書を引く b.全文きっちり日本語に訳す c.先生に指されそうな問題は絶対に間違えないように何度も確認する
これは12歳から18歳まで、ずっとやってきたこと。英語の「勉強」のために。 でも、6年間あんなに頑張ったのに、英語を話せるようにはならなかった。 むしろ、英語を話そうとしても口から出て来なかった。間違えるのが怖くて。 ということは、「勉強」とは違ったやり方でやらなきゃダメなのかも?と思ったんです。
語学習得のプロセスに正解はありません。その人の個性、適性、育った環境など、 様々な条件に影響されるので、こうすれば良い、こうしてはダメ、という答えは無いはず。
でも私は経験上、これら3つの努力を「敢えて封印する」、これこそが 語学の「壁」を乗り越えるための最初の、そして欠かせないステップだと確信しています。
てゆ~か~。って歳でもないけど。
a'.辞書で引いた単語の意味を次の日まで覚えていた例がないんだもーん b'.ドイツ語で話し掛けられたらドイツ語で返さなきゃいけないんだもーん c'.レッスンでは間違えないと先生が注意してくれないんだもーん
...単にセンスが無く覚えが悪いだけのような気もしなくもないけど、気にしない。
ここだけの話、c'.は冗談ではなく、重要です。 1分毎にレッスンを停める生徒は嫌われますけど、そうじゃなくって 間違えないんだったらわざわざ高いカネ払って通う必要がないじゃあ~りませんか。
<教訓> レッスンとは、間違えるために行くところであ~る |

2009年2月20日 (金)
あんたは本当に日本語に訳してないのかね? と聞かれたらどうしよう。
いえ、日本語に訳すこともあります。むしろレッスン中は日本語で考えてるし、 表現のニュアンスの違いや文法事項の確認なんかは日本語じゃないと無理。
うーん、どう表現すればいいのかなー。
「ein Apfelkuchen」 ↓ 「リンゴケーキ1個」 ↓ という流れではダメだと思ったんですよね。脳の中の話ですが。
「ein Apfelkuchen」 ↓ という流れでなければならない。そしてイメージが浮かんだなら、その後の ↓ 「リンゴケーキ1個」 という流れは要らない。言い換えると、
「ein Apfelkuchen」と「リンゴケーキ1個」とを結び付けるのではなく 「ein Apfelkuchen」と(リンゴケーキの具体的イメージ)とを結び付ける
じゃあどうすればそうなるんだ、と聞かれても答えられないなー。うーん。 「日本語に訳す」という行為を止めることで、徐々に慣れて行ったのかな。
試しにドイツ語を書いてみます。
Gestern habe ich diesen Apfelkuchen gegessen. Der war sehr lecker! Möchtest du auch einen essen? Ach, leider gibt es keinen mehr!
ドイツ語の正確性はさておき(間違ってるかも。あはは~気にしな~い)
こんなの日本語に訳すなんて時間の無駄!!(笑)
ドイツ語は単語のポジションが厳密に決まっている変テコな言語。失敬。 話す・書く場合は次に来る単語を選びながら出力しなければなりません。 ここが英語と大きく違うところ。シャドウイングがドイツ語にフィットしないのはそのせい?
シャドウイングはさておき、聞く・読む場合はドイツ語も英語も同じ。 脳に入力されてくる単語の持つイメージをつなげていけば、全体の意味が取れるはず。
つまり、新しい単語や表現に直面した時にすべきことは、 その単語や表現の示す「日本語」ではなく、 その単語や表現の持つ「イメージ」を覚えるべき、ということになるのかな。
ちなみに例はドイツ語で書きましたが、脳の切り替えは英会話で始めたトライです。 |

2009年2月24日 (火)
かくして英会話を踏み台にした私はドイツ語会話の世界へと足を踏み入れたのでした... おしまい。
...終わってない!!! 語学に終わりなし!!!
ですが、私の場合、先に英会話をやって、語学に対する恐怖心と言いますか、 「間違ってたらどうしよ」→「恥ずかしい」→「だから黙っとこ」みたいな悪循環を 断ち切れたことが良かったと思うんです。謙虚さは日本人の美徳、でもそれでは アイスバインの国:ドイツに喰らい付いて行くことは出来ません。かる~く吹き飛ばされます。 そんな可憐な乙女だったとは、今じゃ誰も信じちゃくれませんけどねぇ。えぇ。
いやなに、毎週ふてぶてしい態度で教室に寝そべっている私にもそんな時代があったのだ、 ってことをわかってもらいたくてねぇ...って誰に?
でも。ここで声を大にして言いたい。
皆さん。レッスン代のモトを取りましょう。
しかしこれは難しい。1コマいくらで、レッスン中に話せた時間が何分、しめて... なーんてやってはいけません。わりにあわねー!と、行くのがイヤになります。
そりゃ私だってダニエル・ブリュールくん似の先生探してマンツーマンで習いたいよ。 でもダンナ、そりゃショセン、ムリな話でさぁ。あたしゃケチケチ星人ですからねぇ...
いや、言いたいのはそういうことではなくて せっかく高いお金払って通ってるレッスン中はせめて耳をダンボにして...って古いか、 つまりレッスン中の先生の説明・指摘・注意・訂正・駄洒落...は要らないけど、 そういうものはなるべくたくさん吸収して帰りましょうよ、ということなのです。
これは自分への戒めも含めて、敢えて、書こう。
それ、さっき他の人がやった間違いと同じなんですけど。
自分以外の生徒の発言や質問、聞いてない人が多過ぎる。 自分には関係ないって思ってるのかな。間違いこそが習得の第一歩なんだし、 そういう時にこそ、先生が的確なアドバイスを言ってくれたりするのにねぇ。
いつも駄洒落ばっか言ってる先生に習ってるようにも取れるけど... ま、いっか。間違ってない(笑)。 |

2009年2月 6日 (金)
Hallo! Wie geht's?
明日から朝1回のみの上映になるとの情報を小耳に挟み、急遽ネタ変更。
Haben Sie schon diesen Film gesehen? この映画、ご覧になりました?
http://ja.wikipedia.org/wiki/そして、私たちは愛に帰る http://de.wikipedia.org/wiki/Auf_der_anderen_Seite
現在都内で公開中の、ファティ・アキン監督 『Auf der anderen Seite』。 どうしてまたこんな邦題がついているのか摩訶不思議ですが(ちょっと気に入らない)
Ich habe diesen Film...あーまたやっちゃった! モノが主語だモノが! もとい、
Dieser Film hat mir sehr gefallen!! とっても気に入りました!
ファティ・アキン監督の作品、実は初めて観たのですが、 ドイツ映画ならではの緻密なストーリー構成を持ちながら、 映像の色味や音楽など、感覚に訴えかけて来る要素は これまで観たドイツ映画とは少しテイストが違って、なんというか... とても新鮮で、でもなぜか少し懐かしい感じがしました。
そして「ドイツ語を学ぶなら、こういう側面も知っておかないとな」という意識を 改めてしっかりと植え付けてもらった、そんな印象を受けました。
トルコは...恥ずかしながらその理由を知ったのはつい最近ですが、 100年以上前から、日本と強い絆で結ばれている国。
また、ドイツを訪れたことのある人なら、ドイツとトルコとの深い関係を 実際に目で見、肌で感じたことが、一度はあるのではないでしょうか。
「ドイツ語を学ぶ日本人」として、自分には何が出来るだろう...と考えながら イスタンブールの街を歩いているような錯覚に陥った私でした。
ご覧になった方、ぜひぜひコメントをお寄せ下さい!! シネスイッチ銀座にて上映中: http://www.cineswitch.com/ |

2009年2月27日 (金)
そこのケチケチ星人さん! そう、そこのあなた! ラジオ講座、おひとついかが?
...あ、私のことね。Genau, ich komme aus ケチケチ星。 受信料のモト取ったるわい! と学生の頃から聴いてますよ、ラジオ講座。Aber...
最後まで聴き続けたこと、ほとんどないのよねー。
ゴガクルブログセレクションから追い出されるかしらん? でも本当のことだから仕方ない。
いやー、続かないっすよ、ラジオ講座。長年続けていらっしゃる皆様、本当に尊敬します。 特にドイツ語ってさー。朝早いしー。進むの速いしー。ついていけないよー。ねー。
ラジオ講座やテレビ講座の内容や構成についてはまた別の機会に書かせていただきますが、 半年続くか続かないかは、受講生と講座との「相性」で決まってしまうように思います。
実は旅行欲があまりない私、旅行会話に特化した講座というのはあんまり... いや、ものすごく役には立つんですけど...テレビ講座なら観るかなー、という感じです。
多和田葉子さんがおっしゃっていたように、ドイツ語は「建物」のような言語。 土台から少しずつ着実に学んで行くのが、結局は一番の近道だったりしますのでね...
しかーし! 「ケチなのにモノグサ」という矛盾を抱える私を変えた講座がコレ!!!
2006年上半期 『ゲンのバイオリン』
埃かぶってたテキストを発掘。モノグサなので携帯カメラで失礼。 この年は表紙デザインからして秀逸。捨てられなかった理由はそれ...だけじゃない。
これを聴いた時、感動した。とにかくおもしろいんだもの、ストーリーが。それに 太田先生の練習問題への誘い方(誘ってない)が私好みでドキドキ。もちろん完走よー。 あー、もっかい走りたいなー。あの感動、もっかい味わいたい... よし、決めた!
わたくし、3月1日から毎日、『ゲンのバイオリン』を読み直しますっ!
...でもこの講座、けっこう、難しいのよね。皆さん、いかがでした? そうでもない? 私はヒィヒィ言いながらやってた記憶があるわー。録音機器が全て故障中で(実は今も) 朝と昼と両方聴いてたけど、それでも練習問題は相当キツかったし...
いや、何も急ぐ必要は無いんだった。 ゲンの旅に同行しながら、私自身の経験を書き加えて行けばいいんだもんね。
2006年上半期のテキストをお持ちの皆さん! そう、そこのあなた! 2007年下半期のテキストをお持ちの皆さん! そうそう、あなたも!
Lesen wir ab dem 1. März 'Das Geheimnis der Geige' zusammen!
それと... 太田先生、サイン下さいっ! キャー (≧▽≦) 言っちゃったー |