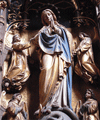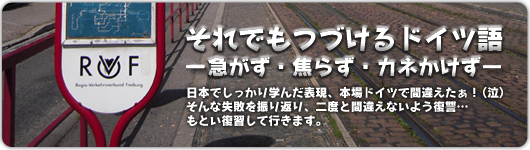
2012年9月29日 (土)
| いつものことですが、2回観てちょうど、でした。 以下、ネタバレとまではいかないですが、 これから観ようと考えている方はご注意下さい。 Mein bester Feind という原題なのですが、私、これと見間違えちゃって、 Mein bester Freund 勝手にそう考えてもう一度観直してみたら、より一層、おもしろかったです。 一度目は、特に前半、まったく笑えなかったんですけど、 二度目は、笑わせどころがよくわかりました。 笑わせてしまうところがすごいよね、といつも思います、ドイツ(語)映画観てて。 ヴィクトルとルディの関係、Freundschaft と言っていいのか、難しいとこだけど(笑) とてもおもしろかった。台詞にない気持ちを動きを感じ取る作業を、ずっとしていました。 ドイツ語に関しては、とても難しかった、特にルディのドイツ語は非常に特徴があって 聴く人が聴けばそれがどういうドイツ語かわかるんだろうけど、私にはわからなかったです。 ウィーンに詳しい人が観たら全然違うのかも。 ドイツ(語)映画の好きなところは、前にも書いたかもしれませんが、 善悪をハッキリつけないところです。この作品についてはそれがよく出ていて どっちの味方、みたいな安易な観方を許さない何かがある、そこがとても気に入りました。 作品の出来は、どうかわからないです、そんなの私に決められない、でも 観てよかったです。やっぱドイツ(語)映画が一番だな、と改めて思いました。 |

2012年3月27日 (火)
Danke, WOWOW!
http://ja.wikipedia.org/wiki/ありあまるごちそう 各種リンクあり 原題の『WE FEED THE WORLD』について解説の森達也さんが触れていらっしゃいましたが この場合の feed は文法どおり他動詞として考えた方が、自動詞としてではなく、 と今思いましたがさておき、
揺さぶられるものがたくさんありました。 売れ残ってしまった大好きなドイツパンの末期。 お安い日を狙って買いに行く鶏ムネ肉パックの経歴。 EUができて便利になってよかったとばかり考えていた自分の軽さ。
飽食の時代と言われてますが私は 極力、買い過ぎない、買い溜めない、買ったら捨てない、ように生活しています。 その前に「買いたいけど買えない」という事情がのさばるのでね(笑) とはいえ、ついさっき目の当たりにした問題が、私の個人努力でもって 何か解決されるかといえば、まったくもって解決されないことをわかっていて それでも私に出来ることは私に出来ることを極力つづけていくことだけ、それと
外国語を学ぶことの意味、目的、効果、みたいなものを ほんの少しだけですが実感できたような気がしました。自己満足でしょうが。
d-mateさんが4月号について書いていらっしゃるのを読んでちょっと焦って(笑) NHK出版のサイトで「試し読み」させてもらったら 3年目の正直か今年こそ4カ国共通キーセンテンスで構成されるらしい EURO24が気になって、予定通り再放送(翌週の正午~)を観るつもりですが
特にドイツ語、今日観たのとまったく違うものを発して来ると思うんです。 今まで観て来たドイツを紹介するテレビ番組がもれなくそうだったように。
良い悪いじゃなく、私は、たくさんのことをインプットしていかなきゃいけない、と。 たくさんというのは、数、質、内容、様々という意味です。 |

2010年1月16日 (土)
Danke, WOWOW!
http://ja.wikipedia.org/wiki/そして、私たちは愛に帰る http://de.wikipedia.org/wiki/Auf_der_anderen_Seite
約1年ぶりに観ました。 →前回のエントリ 映画館で観るより、自宅で録画してゆっくり...の方が性に合って来た今日この頃。
私が映画に求めているものは何なのか、だんだんハッキリしてきました。
緻密な「構成」と、そこに精巧に組み込まれた 映画でなければ許されない「偶然」(映画なら、アリ)。
社会から「問題」を切り取って映し出すこと。 ただしその際には「滑稽」を含ませること。
しんどい人生、それでも自分は生きてみよう、と思わせる何か。
この作品はこれらがバランス良く組み合わされている上に 「色」と「音」がまた素晴らしい。
映し出されるブレーメンの街並を見ながら 「私がここに再び立つ日は来るのだろうか」としみじみ思ったり。
ブレーメンは2008年に訪れた街なのですが 「8月のみ3年間滞在した記憶」というのはおもしろいもので なんというか、高級ハンバーガーを食べる時のように(食べたことないけど) ぐしゃっ! とつぶしてひとつにまとめたような感じでして、 既に一昨年のことなんだけど、昨年のことのような気がしてなりません。 2007年8月+2008年8月+2009年8月と3ヶ月連続しているような、そんな感じ。 |

2009年11月14日 (土)
Danke, WOWOW!
http://www.alcine-terran.com/maruta/ http://de.wikipedia.org/wiki/Die Herbstzeitlosen (2006)
「ドイチェ」ではなく、スイス映画。こちらも久々の鑑賞。 雨の中、レディースデーの行列に並んだことを思い出しました。それはさておき、
当時は「おもしろいけど、ちょっと中途半端」という印象を抱いたのですが 改めてじっくり観てみると、なんのなんの。2度目でも充分おもしろいでないの!
「おじいちゃん・おばあちゃん」世代と 「おとうさん・おかあさん」世代との温度差がなかなかシビアに描かれていて 実は「ぼく・わたし」世代(あまり描かれていないけど)とに挟まれた 「おとうさん・おかあさん」世代が一番しんどいのかもしれないなぁ... って私も一応その世代に入るのか? ヤバイ! それはさておき、
せっかくの人生、楽しく生きようでないの! という明るい気持ちになれる90分。 主人公のマルタだけでなく、3人の「ともだち」の生き方(の変化)も楽しめます。
欲を言えば、美しいランジェリーをもっとたくさん見たかったなぁ。 私にとっての「目の保養」は、昨夏訪れたベルンの街並み(^▽^)♪
ちなみに、ドイツ語の勉強にはなりませんでした... 「これ何語?」な時間が大半を占めます。恐るべし、スイス! |

2009年10月31日 (土)
Danke, WOWOW!
http://ja.wikipedia.org/wiki/わが教え子、ヒトラー http://de.wikipedia.org/wiki/Mein Führer - Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler
ということで久々の鑑賞。 これを観てエントリ1本書こうと決めていたのですけど...
何をどう語ればよいのやら。二度目だからこその迷い。
数々の対立要素も、実は互いを必要としている濃密な関係だったりする。 この構成の重厚さこそがドイツ映画の醍醐味のひとつ。
そして これ以上ないほど重く暗いテーマを扱っているのに、観客を笑わせようとする。 私の知っているドイツ映画は皆そう。多かれ少なかれ必ず「滑稽」を組み込んでいる。 日本映画には無い、なんというか、勇気...心意気...大胆さ...うーん、 なんと呼べばよいのかわからないけど、私はそこに、毎回、うなってしまうのです。
そこには「過去とどう向き合っていくか」という問題に対する 日本(人)とドイツ(人)との姿勢の違いが表れているのかもしれません。 |

2009年3月11日 (水)
ちょっとひと休み、大好きなドイツ映画をご紹介。
http://ja.wikipedia.org/wiki/グッバイ、レーニン! http://de.wikipedia.org/wiki/Good_Bye,_Lenin!
言わずと知れた『グッバイ、レーニン!』、ご覧になった方も多いと思いますが 私は昨夏の語学コースの授業で初めて観ました。 キーとなる言葉・事件・文化などについて先生が事前に資料を作って来てくれて それを読んで来ることが宿題だったので、ドイツ語字幕を手掛かりに わからないなりに楽しめた、つもりでしたが...
日本語字幕版を観て、やっと謎が解けた~!という箇所多数(笑)。
織り込まれたモチーフやエピソード、全て解読するのは不可能だけど、 観るたびに「重なり」や「つながり」や「対比」が次々と見えて来るところがおもしろい。
もちろん中心にあるのは確固たる親子愛なんだけど、 周囲、つまり孫、息子の恋人、近所の人々、そして国家や社会との 直接的・間接的な触れ合いによって、その有りようが少しずつ変わって行く。
母を取り囲む、息子が作り上げた「DDR」。 しかしその母も、実は心の中に「秘密」を隠していた。
アレックスが夢見た宇宙みたい。構図としてね。 そして彼が作り上げた「DDR」とはどんな国家・社会だったか。
国家や社会の有りようも大事だけど、でもやっぱり一番大事なのは 新しい命の誕生なのかなぁ、とも思ったりする今日この頃。 |

2009年2月 6日 (金)
Hallo! Wie geht's?
明日から朝1回のみの上映になるとの情報を小耳に挟み、急遽ネタ変更。
Haben Sie schon diesen Film gesehen? この映画、ご覧になりました?
http://ja.wikipedia.org/wiki/そして、私たちは愛に帰る http://de.wikipedia.org/wiki/Auf_der_anderen_Seite
現在都内で公開中の、ファティ・アキン監督 『Auf der anderen Seite』。 どうしてまたこんな邦題がついているのか摩訶不思議ですが(ちょっと気に入らない)
Ich habe diesen Film...あーまたやっちゃった! モノが主語だモノが! もとい、
Dieser Film hat mir sehr gefallen!! とっても気に入りました!
ファティ・アキン監督の作品、実は初めて観たのですが、 ドイツ映画ならではの緻密なストーリー構成を持ちながら、 映像の色味や音楽など、感覚に訴えかけて来る要素は これまで観たドイツ映画とは少しテイストが違って、なんというか... とても新鮮で、でもなぜか少し懐かしい感じがしました。
そして「ドイツ語を学ぶなら、こういう側面も知っておかないとな」という意識を 改めてしっかりと植え付けてもらった、そんな印象を受けました。
トルコは...恥ずかしながらその理由を知ったのはつい最近ですが、 100年以上前から、日本と強い絆で結ばれている国。
また、ドイツを訪れたことのある人なら、ドイツとトルコとの深い関係を 実際に目で見、肌で感じたことが、一度はあるのではないでしょうか。
「ドイツ語を学ぶ日本人」として、自分には何が出来るだろう...と考えながら イスタンブールの街を歩いているような錯覚に陥った私でした。
ご覧になった方、ぜひぜひコメントをお寄せ下さい!! シネスイッチ銀座にて上映中: http://www.cineswitch.com/ |